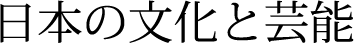
世知辛いのはいずこも同じだが、世界無形遺産にも指定されている人形浄瑠璃「文楽」の豊竹十九大夫が、文楽の技芸員の互助組織の積立金約5000万円を横領していたと報道された。芸術選奨という立派な賞までもらっており、その世界での先達にもなろうという76歳の大ベテランが、みっともないを通り越して情けない。
ちょうど、三宅周太郎という私どもの仕事の大先輩に当たる演劇評論家の「文楽の研究」という岩波文庫を読み終わった時、このニュースを知った。この本は、文楽の世界で清貧に甘んじながら、ただひたすら芸道を求める人々の姿を丹念に追いかけ、調べたものである。コツコツと一生を歌舞伎と文楽の研究や批評に没頭し、栄誉を求めることをしなかった著者の姿に感動し、「自分ももっと勉強しなくては」と早々と来年の抱負を決めて年を越そうとしていただけに、腹立ちもなおさらだ。
今でこそ東京では文楽が大人気ですぐにチケットが完売になるが、いわゆる「食えない」時代の長さは歌舞伎の比ではない。義太夫を語る大夫、三味線弾き、人形遣いの三つの役割が揃って良い舞台が生まれる。そのための修行は並大抵のものではない。少しでも芸がまずければ、師匠や先輩に三味線の撥で殴られ、下駄で蹴られ、そうして芸を自分の身につけてきたのだ。苦心を重ねて名人上手と呼ばれるようになったとしても、湯水のようにお金が入って来るわけではない。それでも、文楽が好きで仕方がないから、辛い修行にも耐え、貧乏にも耐える。「いい芸」がしたいからだ。
三宅周太郎はそういう愛すべき芸人たちを含めた文楽を愛し、昭和五年にこの本を出した後、何度も手を加えて、昭和二十七年に決定版とも言えるものにした。そうした地道な努力もまた、文楽を語るにふさわしい仕事であり、著者の熱意と愛着を感じる。
今の時代でも決して経済的に恵まれているとは言えない文楽の技芸員の積立金は、休演した際に出演料の代わりに支払われたり、冠婚葬祭の費用に充てたりするものだ。積み立てをすることそのものが楽ではない人もいるはずだ。その代表理事をしていた時に、5000万円もの大金を横領するなど、文楽の面汚し、である。即刻廃業を命じられたが、それは当然のことで、芸に賭けるべき「魂」が腐り、「欲」にまみれた結果である。
十九大夫の師匠は、「名人」と言われた豊竹古靭大夫(ルビ:こうつぼたゆう)という。「悪声」と言われながらも浄瑠璃を徹底的に研究し、後に宮家から「少掾」(ルビ:しょうじょう)の号を賜るまでに上り詰めた人だ。
その弟子がこんな無様な真似をしたのでは、清貧に甘んじて生涯を貫いた芸界の人々や、今、青雲の志を抱いて苦労しながら修行に励んでいる人たちに申し訳がない。同じ芸事の世界に住む人間として涙が出そうに悔しい話だ。「芸人だから清貧を貫け」というつもりはないし、そんな権利もないが、この大夫が伝統ある文楽の歴史を作った先人たちやそれを愛する人々に与えた罪は、お金の金額よりもはるかに大きい。
幸四郎早稲田へ帰る
十月二十八日、早稲田大学の大隈講堂が揺れた。創立百二十五周年記念イベントの棹尾を飾る歌舞伎十八番の内「勧進帳」。早稲田大学出身の松本幸四郎が、母校のお祝いのために、先ごろ重要文化財に指定された大隈講堂で一回限り演じた弁慶に、千百人の観客がどよめき、酔った。富樫は子息の市川染五郎、義経は一門の市川高麗蔵である。
学生や校友たちで埋め尽くされた講堂の仮設の花道を飛び六法で引っ込む弁慶の姿に手拍子が起き、幕が閉まっても拍手は鳴り止まなかった。歌舞伎には異例のカーテンコールが行われ、深々と頭を下げる出演者たち。それでも拍手が止まず、幸四郎がかつての学び舎に対して素敵なメッセージを送った。劇場で聴く喝采とは違った熱気に包まれた舞台であった。
来年にも上演回数が千回に達しようという幸四郎の弁慶。そのうち、二回を早稲田大学で演じている。もう一回は今から二十五年前、創立百周年の記念行事である。
森光子の「放浪記」を筆頭に、一人の役者が回数を重ねて演じている芝居はたくさんある。しかし、そのどれもが、ただ「回数が多い」という数字だけの問題ではない。その役者の当たり役であるのは当然だが、前回より今回、今回より次回の舞台が良くなければ、何度も演じることはできない。従って、数を重ねるだけ自分に課したハードルはどんどん高くなる。それを毎回必死で超えているうちに、回数が重ねられてゆく。幸四郎の「勧進帳」もそうして積み上げられてきた舞台なのだ。
今回、母校の記念行事に、校友の一人として快くこの舞台を引き受けた幸四郎は、決して環境が良いとは言えない舞台で、早稲田の学生に「勧進帳」を見せた。その心意気に感じた観客も多かっただろう。
学生の多くは初めて歌舞伎に接したはずである。留学生の姿も観られた。公演終了後、多くの感動の声が寄せられたと聞くが、大学生という感性の豊かな時期に、自分の大学で生の芝居を観るというチャンスはそうあるものではない。しかも、その主役が自分の先輩であれば、そこで感じるものも多いだろう。
情操教育や生きた文化に触れることはどの年代でも大切だ。まして、それが自国の誇るべき伝統芸能の一つ、歌舞伎である。一時間十分の舞台から学べることはいくつもあっただろう。至近距離で役者の細かい表情まで観られる贅沢な状況で、一つの道をひたすら歩んでいる先輩が自分の「芸」と共に「生き方」を見せている。めったにあることではないが、こうしたことこそ、生きた教育と言えるのではないか。
芝居が娯楽であるのは事実だが、時としてその効用は大きい。
演劇制作体「地人会」が今月いっぱいで二十五年にわたる演劇活動に終止符を打つことになった。演出家で代表でもある木村光一と地人会の「体力」が続かなくなった、というのがその理由である。残念だ。
「地人会」は劇団ではない。専属の役者は一人もいない。あくまでも演劇制作体であり、公演のたびにその作品に最も適すると思われる役者や演出家を招き、制作する集団だ。木村光一自らが演出に当たるケースも多い。
私は1982年の第2回公演から地人会の芝居を観ているが、かつてここの芝居を評した時に、「演劇界の良心」という言葉をあえて使った。道楽で芝居を創っているわけではないから、利益を上げなくては次の公演が打てないし、スタッフも生活できない。しかし、派手なキャスティングで目を引き、とにかくチケットを売り切ってしまうことを第一目的にしている芝居の創り手が多い中で、不器用なまでに「まずは作品ありき」の姿勢が好ましかったのだ。その軸がぶれなかったから、今まで続いたのだろう。
特別公演や朗読劇、実験劇場以外のいわゆる本公演を、今までに105回重ねて来た。この実績は大きい。単なる数の問題ではなく、日本の演劇シーンに記録すべき作品をいくつも生み出してきたのだ。
渡辺美佐子の一人芝居「化粧」、有馬稲子、松山政路の「はなれ瞽女おりん」、上月晃の「ピアフ−生命、燃えつきて」、高橋長英、原康義、嵐広也と主演を変えて演じ続けた「薮原検校」、こうしたものはみな地人会の仕事である。名作の再評価、きちんとした新作の上演、決してその場限りの芝居創りではなかった。
それだけに、今までの25年は楽な道のりではなかったはずである。東京の劇場だけではなく、各地方の演劇鑑賞団体の巡演をこまめに回り、日本全国で良質の芝居を安価で見せる仕事は、役者やスタッフにも過酷である。しかし、それを支える観客が地人会の情熱を感じたからこそ、歴史が積み重ねられたのだ。
テレビで人気のスターを並べて芝居を打つのも一つの興行形態である。しかし、あえてその方法に背を向け、コツコツと手作りで芝居を創ってきた人々。「体力が続かなくなった」という言葉が私には悲痛に聞こえ、胸が痛い。
当たればいい、受ければいいというだけの芝居創りではやがて行き詰まる。そうではなく、観客に見てもらいたい芝居を求め、地味な努力をしているところは他にもある。その中の貴重なともし火の一つである「地人会」の解散は寂しい。それは、派手なものばかりに目を奪われ、本質を見極めようとしないで浮かれ騒いでいる今の演劇界や、我々観客に対する命がけの警鐘であるような気がしてならない。
「誰が選んでくれたのでもない、自分で選んで歩き出した道ですもの…」。
杉村春子の代表作で、生涯に900回の上演を数えた「女の一生」の名ぜりふを淡島千景の口から聞いた時、全身が総毛だった。「芸の力」というものが、こんなに凄いものだとは思わなかった。
83歳にして先輩の当たり役に「朗読劇」という型式ではあれ、挑戦する淡島の姿勢はたいしたものだ。今までの自分の役を繰り返して演じていても忙しいだろうに、日本の演劇史に残っている作品に挑む。「朗読劇」とは言ってもただ座って台本を読むだけではなく、場面によって衣裳を変え、動きもある。休憩を挟んで2時間15分にカットしたものの、芝居の基本は何も変わっていない。大女優がたった3日間で6ステージ、しかも、主人公の布引けいを演じていない回は堤家の母・しずを演じている。もったいないとも贅沢の極みとも言うべき芝居だ。
そもそも、この話は先ごろ亡くなった文学座の北村和夫が淡島に「演出をするから朗読劇をしないか」という形で始まったものだ と言う 。それが、北村の急逝という哀しみを乗り越えて、今回の上演にこぎつけた。
しかし、淡島を囲む俳優陣のレベルの低さが気の毒だった。明治38年の日露戦争から第二次世界大戦後の昭和20年までの布引けいという「女の一生」を、10代から60代までにわたって演じる。淡島の布引けいが見事だったのは、年を追うごとに確実に老けて行ったことだ。当たり前の話だと思われるだろうが、幕を追うごとの時間の経過が、読み方や声に現われている。動きで表現できない分の芝居を、声でするのだ。70年近い芸歴を持つ彼女が、朗読劇は今回が初めてだ、と聞いた。舞台や映画、テレビなどの活躍が忙しく、そこまで幅を広げる暇がなかったのだろう。
初日の一ヶ月ほど前 の暑い夏、電話で少し話したが、いろいろな意味で「手作り」の芝居のために、初めてのことが多くて困る、と言っていた。しかし、この声音に困っている様子はなく、むしろ新しい分野に挑戦できる喜びに弾んでいるように私には聞こえた。
今までに 杉村の「女の一生」を幾度観たかわからない。 杉村 が演じる布引けいは、自分の人生に果敢に立ち向かっていく女性だった。しかし、淡島 の けいは、人生の荒波に翻弄されながら、必ずしも自分の本意ではない「一生」を歩んでしまった女性の哀しみが聞こえた。 特に終幕の焼け跡の場面など、秀逸である。
「あたしには芝居をするより他にないんですか ら」と明るく笑う淡島がいつまでも若々しい理由はこの意欲だろう。しかし、ただ挑戦するだけではなく 、それに対してこちらの予想以上の 結果を出すこの女優が、どんなに凄い芸の抽斗を持っているのか、全部を観たいという気がした。
残暑お見舞い申し上げます。御無沙汰しましたが、その後いかがですか。「役者になりたい」と私のところへ相談に見えた時は時間がなく、キチンとお話できませんでしたので、手紙にしました。
「人気者になりたい」というお話でしたよね。「有名になれる」「テレビに出られる」「カッコイイ」「いい生活ができる」などと思って役者を目指すのでしたら、即刻辞めた方がいいですよ。君が不幸になるだけです。
確かに華やかなスポット・ライトを浴び、多くの人の注目を集める仕事ですが、その裏には「仕事がいつもあるというわけではない精神的不安」や「ボーナスがない経済的不安」、「有給休暇がない」など、数え切れない過酷さが潜んでいるのですよ。
そうしたものに関係なく、自分の生活のすべてを投げ出してでもいいから「いい芝居がしたい」という抑え切れない熱情があるのなら、勉強をしてもいいでしょう。しかし、俗に「役者は親の死に目に会えない」と言います。大切な人が死の床にあろうと、芝居を抜けることはできません。そういう辛さや孤独を超えて、一人前の役者になるのですよ。
私を育ててくれた役者たち、前進座の名女形・五世河原崎国太郎が倒れた時に手にしていたのは「鶴屋南北全集」でした。十三世片岡仁左衛門は、不遇な時代に上方歌舞伎の復興を目指し、自分の住まいを売ろうとしてまで自主公演をしました。劇団NLTの賀原夏子は末期がんの激痛に舞台の袖で失神しながら旅公演を続けました。
こうした例は枚挙にいとまがありません。名優と呼ばれる人は、その生の終わる瞬間まで、芝居のことを考えています。煌びやかな世界であるからこそ、ストイックさが求められます。スターになればしたい放題ができる? いや、それは単なる勘違いですよ。
テレビや舞台で売れっ子の松村雄基さんをご存知ですよね。彼は、前の晩どんなに遅くても必ず早朝約1時間のランニングを欠かしませんし、去年明治座で上演された「女たちの忠臣蔵」では鼓を打つ場面があると知り、一年以上前から暇があれば鼓を打っていました。テープでごまかす役者も大勢います。しかし、過酷なまでに自分を追い込み、新しい芝居を生み出そうとする努力を怠りません。第一線で活躍している方はみなそういう想いで真面目に芝居に取り組んでいるのです。
その上で演技をひたすら追求し、ゴールのない道を目指す覚悟が必要なのです。何かのきっかけで少しテレビに出ても、蓄積と努力がなければ、すぐに視聴者にもテレビ局にも捨てられます。君は、役者になりたいのか、消耗品扱いのタレントになりたいのか、それをじっくり考えてください。
一度きりの人生です。好きな道を歩みたい想いは誰にでもあります。しかし、好きな道を選べば、苦労は三倍、四倍です。
厳しいことを書きましたが、また手紙を書きます。頑張ってくださいね。暑さに気をつけて。 怱々
「中日新聞掲載分では、松村雄基さんの出演した作品名を誤記してしまいま した。お詫びして訂正いたします」
歌舞伎の人気役者・市川海老蔵が今月の大阪松竹座の歌舞伎公演中に右足を十針以上縫う大怪我をした。ファンには残念な事態だが、それ以上に辛いのは本人だ。三本の演目を持ち、気を吐いていただけに残念だ。キレのいい芝居を期待していた浪花のファンはがっかりだろう。
ただ、見事だったのは海老蔵が演じていた役のすべてにすぐ代役が立ち、公演に穴を開けなかったことだ。これが他の芝居であれば、主役が大怪我をすればその日の舞台が休演になるケースもある。しかし、歌舞伎は即座に代役が立てられる。新作が少なく、演目数が限られているとは言っても、実に合理的なシステムだ。
これは、主役の役者ばかりではない。大きな役が一人でも抜ければ、新たに役者を投入するわけではなく、一座の中で役が順繰りに変わっていくのだから、誰もがいつでも代役ができるように心得ていなくてはならない。それが、歌舞伎役者のたしなみとして、昔から連綿と伝えられてきた伝統の良さである。
「鳴神」は片岡愛之助、「義経千本桜」の義経は坂東薪車、「女殺油地獄」は片岡仁左衛門がそれぞれ代役に立った。誰しも、他に自分の役があってのことだ。肉体的・精神的な負担も大きい。しかし、それを厭わずに仲間を助ける一種の互助システムでもある。仁左衛門などは、「女殺油地獄」の河内屋与兵衛は若き日からの当たり役とは言うものの、その前に「身替座禅」を演じており、わずか十五分の休憩を挟むだけだ。それを即座に替われたのは、役者としての蓄積の賜物だろう。
歌舞伎の代役の独自のシステムに、「三日ご定法」という決まりがある。代役を立てた場合、仮にもとの役者が翌日に出られるようになっても、三日間は代役をお願いすることになっている。急場のピンチを救ってくれた相手に対する礼儀である。場合によっては代役に立った役者のチャンスにもなる。
もっとも、ここで才能を認められるには日頃よほどの研鑽を積んでいなくてはなるまい。亡くなった河原崎権十郎は「代役の名手」と言われるほどに代役が回って来た。それも、歌舞伎ばかりではなく、尾上松緑が演じた「オセロー」を代わったこともある。こういうところでも役者の実力がわかる。
数年前、東京の明治座でも千秋楽を数日残して「女たちの鹿鳴館」という芝居で主役の若尾文子が体調を崩して休演した。その時も、同じ舞台に立っていた音無美紀子が代役に立ち、見事に急場を乗り切った。その時の一座の「チーム」としての結束力が物を言うのだ。
役者とて人間である。いつどこで何があるかわからない。何もないのが当たり前と思われているが、何か起きた時にどう対処するか、これは役者だけの問題ではなく、我々の日々とても同じことだ。
その点で今回の代役は実に見事に決まった。海老蔵は残念ながら今月は復帰不可能になってしまった。本人にしてみれば「痛恨」であろう。それをバネにできるかどうか、彼の役者としての性根が見たい。
先日、NHKで宮城まり子と「ねむの木学園」のドキュメンタリーを放映していた。東京では「ねむの木のこどもたちとまり子美術展」が開催され、多くの人々が純粋無垢な魂を持った子どもたちの絵に感銘を受けている。
静岡県掛川市にある肢体不自由児療護施設「ねむの木学園」が今年で創立40年を迎える。その間の宮城まり子の苦労たるや、筆舌に尽くしがたい。その代わりに、多くの子どもの母親としての喜びもひとしおだろう。
ふと考えると、彼女が「女優」として一世を風靡するほどの人気者だった時代を知っている人が少なくなり、今は「ねむの木学園の園長さん」としての顔を知る人の方が圧倒的に多い。彼女があの小さな身体で何度も倒れ、満身創痍でこの壮大な事業に取り組んできたからだ。
私にしても、昭和59年にフランスの娼婦を主人公にしたミュージカル「イルマ・ラ・ドゥース」を観たのが彼女の本格的な芝居の最後である。その時の愛らしく、可愛かったこと。高い声に魅力があり、小柄で丸っこい体型には愛嬌があった。これは彼女の役だ、と思った。女優・宮城まり子は、アメリカで大統領よりも有名と言われたルシル・ボールにも匹敵する類稀な「コメディエンヌ」なのである。そこを評価しないのは我々の責任だ。
もっとさかのぼれば、自らの恵まれない生い立ちを劇化した「まり子自叙伝」で観客の涙を絞り、「風と共に去りぬ」では帝国劇場を湧かせた。「雲の上団五郎一座」などの髷物コメディには欠かせないメンバーでもあった。また、「ガード下の靴磨き」などの大ヒット曲も持っている、立派な女優だ。
「ねむの木学園」の活動がある程度軌道に乗ってからは、子どもたちを主演にした映画を撮影したり、子どもたちとコンサートを開いたり、その旺盛な活動は決してマスコミから離れたわけではない。
腹が立つのは、大富豪でもない女優が私財を投げ打ち、挑んでいる事業に「文化国家」を標榜する政治家や官僚がなかなか重い腰を上げなかったことだ。多くの篤志家や一般市民の浄財などは集まったし、協力を惜しまない政治家もいた。しかし、「ねむの木学園」の知名度が高まり、福祉に目が向けられる時代になった時に、政治家が真っ先にしたことは、彼女を議員に立候補させようとしたことだった。呆れて物が言えない。
彼女は女優としての道よりも、多くの子どもたちの母親の道を選んだことを全く後悔はしていないだろう。そうでなければ、多くのスタッフの協力があったとは言え、40年も続けられはしない。「彼女がずっと女優でいてくれたら」と言うのはないものねだりだ。演劇界は彼女が「ねむの木学園」の園長になってからも続いている。しかし、彼女が園長を辞めていたら、今の「ねむの木」はなかっただろう。それに、今の彼女はとても「いい顔」をしている。
それは承知の上で、彼女の舞台女優としての素晴らしい才能を知っている最後の世代として、もう一度彼女の芝居が観たい。
G.Wの最終日に、文学座の北村和夫の訃報を聞いた。80歳だった。もうそんな年齢だったのかとも思ったが、考えてみれば30年以上も舞台を観ているのだ、おかしくはない。杉村春子に呼ばれたのだろうか、とも思った。
ほぼ予想していたことだが、彼の訃報を伝える多くの新聞記事やニュースの内容が「文学座の大黒柱」「杉村春子の長年の相手役」というスタンスで書かれていた。それは紛れもない事実である。しかし、役者・北村和夫について一番書くべきことだと私が思っていることを書いていない新聞が多かったのは残念だった。
北村和夫という役者が、杉村春子なくしては存在し得なかったことは誰にも否定のしようがない。それに異を唱えるつもりはないが、彼がそれだけの役者であったかのような論調で捉えることは間違いである。私自身が新聞に記事を書いていながら言えた義理ではないが、こうしたステレオタイプの報道しかしないマスコミの態度には大きな疑問を感じる。
私は彼の最も優れた舞台を一つ挙げよ、と質問されれば、何のためらいもなく「花咲くチェリー」と答えるだろう。この舞台には、杉村春子は出ていない。彼は杉村の相手役ではなく、「主役」なのだ。1965年に文学座の公演で主演し、2004年の地人会の公演まで、40年近くにわたって幾度も繰り返して演じた当たり役である。保険会社に勤めながら、何とか自分で林檎園を持ちたいという夢を持ち、その夢に破れる男の哀感を描いた芝居だ。今話題にされている団塊の世代であれば、グッと来るに違いない。
私も、この芝居を初めて観た時には、数少ない「男が共感できて、男が泣く芝居」だと評価し、彼の迫真の演技に涙した。畢生の名演、と言っても良い舞台だったと思う。もっと言えば、今までに彼が演じてきた役のいくつかは他の役者でもできただろうが、この芝居だけは北村和夫のものだと思った。そのことを書いてほしかったのだ。
どんな分野であれ、大きな仕事を成し遂げたり、名のある人の訃報記事はそれ自体が一つの作品だ、と私は思う。その人の歩んできた人生を知る最期の機会だからだ。しかし、それがどの新聞も提供された素材だけを頼りに同じようなことを書いていたのでは、面白くはないし「作品」たりえない。もちろん、「女の一生」の栄二も、「欲望という名の電車」のスタンレーも、彼なくしては成立しなかっただろう。しかし、それは杉村の相手役としての北村和夫の話である。
舞台人・北村和夫としての素晴らしい当たり役に触れる報道が少なかったのが、私は哀しい。と同時に、自分が他の役者をそういう眼で見ていないかどうか、反省をもしたい。突出した仕事だけ、目立ったことだけを評価する事は誰にでもできる。そうでない部分をも併せて評価してこそ、最期の作品ではないのだろうか。
私は「花咲くチェリー」の北村和夫を想って彼を偲ぶ。
食べ物ではなく、人間の方である。二月に、新宿のコマ劇場でコロッケの座長公演があった。「俺はお殿様」という喜劇に、恒例の物まねショーの二本立て公演だった。芝居の方は以前三木のり平が演じたもので、それを大胆にアレンジして舞台に乗せた。
初日が開く一週間ばかり前に、コロッケは稽古中に左手の肘を骨折した。しかし、座長である以上代役はきかない。左手を吊って、それでも元気いっぱいに舞台を駆け回り、いつもよりもパワーアップして観客を大笑いさせていた。「顔が大きいから転び方が下手で、左手を折っちゃってすみません」と、アクシデントさえも笑いにして。
その彼の姿に、芸人の魂を見た想いがした。「芸人」と言うと、テレビで馬鹿騒ぎをしている品のないお笑い芸人たちのおかげで、一段低いイメージを持たれるかも知れない。しかし、私の中では舞台の上に立つ人は、歌舞伎役者であろうが新劇女優であろうが、すべて「芸人」である。芸を見せる人、だからだ。これは芸を行う人々への私の尊称である。
一ヶ月単位の公演になると、故障を抱えて舞台に立つケースは少なくない。人間である以上、公演期間中完璧な体調を維持するのは至難の技だ。観客に見えない不調であればまだ隠しようもあるが、左腕を固定して、その上で出ずっぱり、早替わりの舞台を一ヶ月こなす不自由さは我々の想像を絶するだろう。
そうした中でコロッケの姿は真摯だった。もちろん、周りのサポートなくしてはありえない。ベテランの赤木春恵や相手役の熊谷真実など、共演者やスタッフの助けが大きかったのは事実だ。それでも、観た目のハンデを感じさせない大奮闘に拍手を贈りたい。自分がケガをしていても、座長としての目配りや心遣いを怠ることなく一座を率いていく、その優しさと強さが人気の秘密だろう。そして、観客の視線を常に意識している。芝居に没頭していない、という意味ではない。視線が観客と同じ高さなのだ。
彼は板の上に立つ怖さを知っているからだろう。だから勉強を怠らない。テレビへ出たはいいが、名前を覚える暇もなく消えていくお笑い芸人との違いはそこにある。まさに、揚げたてのコロッケのようにいつも熱いのだ。
視力を失いながら九十歳まで舞台を勤めた歌舞伎の十三世片岡仁左衛門。卵巣がんの痛みの余り舞台袖で失神しても、観客に気付かせずにコメディを演じた劇団NLTの賀原夏子。夫の死を看取ることよりも舞台を選んだ杉村春子。こうした名優たちと同じ匂いを彼は持っている。彼がその列に連なるかどうかはわからない。しかし、その根性は見事なものだ。
自分の出番が終わるとさっさと飲みに出かけてしまうような役者もいれば、人気を勘違いしてやりたい放題の役者もいる。しかし、めっきと純金の違いはやがてわかるものだ。
