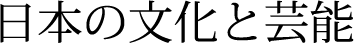
この11月、東京・明治座では先ごろ映画「ALWAYS 三丁目の夕日」で話題になったマンガ「三丁目の夕日」を舞台化して上演している。出演者は三田佳子、左とん平、篠田三郎、音無美紀子、金子昇などの面々だ。時代や場所はそのままに、映画とは全く違った新しいストーリーを作成し、古き良き昭和の一部分を舞台で再現しようという試みだ。
原作がある作品を劇化する場合、映像と舞台ではそれぞれに特徴がある。最新のデジタル技術を駆使できるのは映画だが、ライブの感覚は舞台だ。どちらが良いというものではなく、明らかに質の違いだ。
この芝居を観てふと感じたことがある。135年の歴史を持ち、1300席を超える規模の明治座は、以前は新派や新国劇のホームグラウンドだった。ならば、今の時代のスタンダードになる芝居を作るべきだ。その時、「三丁目の夕日」が候補作に成り得るだろう、と。
今回の公演が絶賛に値する、と言うつもりはない。工夫の余地は多いし、脚本の練り直しも必要だ。役者を揃えても持ち味を出し切れていない。ただ、「明治座と言えば誰」という役者がいるように、「あの芝居と言えば明治座」という芝居になる可能性を持つ原作だ。大劇場演劇として、多くの世代が楽しめるテーマを持っているからだ。
同じ内容の芝居を繰り返して上演するのではなく、キャストもストーリーも公演ごとに変えれば、「△×編」とか「◎▽の巻」など材料には事欠かない。ビッグコミックオリジナル(小学館)の西岸良平のマンガは1974年から30以上年連載を続け、50冊を超える単行本が出ている。人気作品の魅力は深い。
時代のスピードは異常なまでに速く、昭和30年代の芝居でも時代考証や科白のアクセント指導などが必要な時代である。いたずらに懐古趣味に走る必要はないが、我々がこの作品に「何か」を感じているのなら、それを色々な角度から眺め直すのも悪くはあるまい。
昭和三十年代後半生まれの私は、「三丁目の夕日」の世界には懐かしい温もりを感じる。この時代を知らずとも、雰囲気を感じられるのが、この作品の人気の秘訣だろう。
今回の舞台で左とん平が絶妙の間を見せる紙芝居屋も近所の公園にはいたし、大きな台風が来れば停電や雨漏りは当たり前だった。名建築や自然の世界遺産指定も結構だが、我々の心の中にポッと灯っている想い出とて、大切なものだ。それは、かつて新派の芝居が見せた人の情と何ら変わるものではない。
ある時代に軸を据え、スタンダードを創り上げる。こうした試行錯誤も、東京の伝統ある大劇場としての明治座の仕事の一つではないのだろうか。
奈良の平城遷都1300年記念のプレイベントとして、10月15日の夜、東大寺の大仏殿前で幸四郎が「勧進帳」を奉納し、1000回目の弁慶を演じた。東大寺式衆の「散華」に続き、5000人の観客を前にした特設舞台で市川染五郎の富樫での親子共演の舞台だ。
煌々と月明かりが射す中、花道を登場した幸四郎に観客がどよめく。舞台の後ろにはライトアップされた大仏殿があり、みほとけが静かな微笑みを浮かべている。秋の夜の野外劇としては絶好のシチュエーションだ。
「勧進帳」は兄・源頼朝に追われる義経一行を、安宅の関を守る富樫左衛門が武士の情で逃がす、という芝居だ。こういう「判官びいき」の感情は日本人が大好きなもので、歌舞伎十八番の一つでもあり、常に人気がある。芝居の中で、富樫と弁慶の問答になり、咄嗟の機転で弁慶が白紙の巻物を取り出し、我々は東大寺勧進のために諸国を歩いている山伏だ、と言う。この巻物が「勧進帳」なのだ。いわば、東大寺にゆかりの深い芝居である。
幸四郎は、16歳で弁慶を初めて演じ、ちょうど50年をかけて1000回目に到達した。もちろん、「勧進帳」の弁慶ばかりを演じていたわけではない。先日1100回を超えた「ラ・マンチャの男」や「アマデウス」のサリエリなど、歌舞伎以外の芝居も演じた上でのことだ。
役者が当たり役を持てるのは幸福だ。観客がその良さを認め、「また観たい」と思わなければ再演はできない。その一方、回を重ねるごとに前よりも良い芝居をしなければ前へは進めない苦しみも併せ持っている。1000回目の弁慶を、幸四郎はこうした役者の葛藤を感じさせずに、いつものように演じおおせた。これからも続く役者の道のりの一回として。どの芝居も役者と観客にとっては一期一会であり、「いつものように」が大切なのだ。
星が輝く夜空に科白が拡散していく。芝居の途中で8時になり、東大寺の鐘の音が想いもよらぬ効果音を添えた。秋の夜はしんしんと冷え込み、月はただ明るく中天を目指す。「芝居」というぐらいだから、芝の上で夜露を感じながら芝居を観るのも一興だ。これは野外劇ならでは味わいだろう。
花道を飛び六法で引っ込む弁慶の姿を、息子の染五郎が見詰めている。偉業を成し遂げた父の背中を、息子として後輩としてどんな想いを持ったのだろうか。芝居が終わり、満場は喝采に包まれた。その瞬間、幸四郎の「1001回への道」がまた新たに始まったのだ。
昭和31年に開場し、昭和の喜劇王と呼ばれた榎本健一をはじめ美空ひばり、喜劇の「雲の上団五郎一座」など、多くの舞台を提供してきた新宿コマ劇場が、年末に52年にわたる歴史の幕を閉じる。多くの役者や歌手が、この大きな舞台に上がることを夢見てきた名物が、また一つなくなり。寂しいことだ。
三重構造のまわり舞台がコマのように回ることから「コマ劇場」と名付けられ、現在までの観客動員数は延べ5000万人を超えるという。客席数が2000席を超える大劇場は、コンサートホールを除くとここ以外にはない。
歌舞伎町一帯の再開発に伴い劇場を閉館することになり、自主制作の公演は今月の「北島三郎特別公演」が最後になる。演歌界の大御所・北島三郎も今回が39回目の座長公演だ。相手役に星由里子を迎え、おなじみの白木みのるや龍虎、娘の水町レイコなどの顔ぶれで「国定忠治」にショー「北島三郎大いに唄う」の二本立て、コマ劇場の幕を降ろすにはふさわしいコマの「顔」だろう。早々に完売となって客席を埋め尽くした多くのファンたち。他県から観光バスを仕立て、団体で毎年この公演に通うのを楽しみにしている人々も多い。別れを惜しむ人びとで、さよなら公演は盛り上がっている。
私のメモを見ると、最初にコマ劇場で芝居を観たのは1975年6月の美空ひばりの「ご存じ弁天小僧」とある。ずいぶん古い話だ。近所の商店街の招待で出かけたものだった。以来、欠かさずではないが、多くの舞台を観た。森進一や小林幸子などの歌手の座長公演もあれば、山口百恵の「百恵ちゃんまつり」、ジャパン・アクション・クラブの千葉真一・真田広之・志穂美悦子のアクション・ミュージカルも観た。東京キッドブラザーズ時代の柴田恭兵の舞台もあり、そういう意味では、間口の広い「庶民の劇場」である。
新宿に大劇場がなくなるのは、ある意味では現代の芝居が置かれた状況をよく現わしているとも言えるだろう。特に大劇場の「商業演劇」と呼ばれる芝居をめぐる状況は大きく変わっている。映画がそうであるように、茶の間で寝転がっていれば何でも観られる時代に、生身の人間を劇場へ引っ張り出すのは大変な仕事だ。
少子高齢化と不況の波は、劇場という空間にも大きな影響を及ぼしている。若者だけに迎合する必要はないが、これからの観客層のニーズを絞り込み、その上で質を保つのがこれからの演劇界の課題だろう。劇場はなくなっても製作母体であるコマ・プロダクションは健在だ。この課題をどうクリアするか、それが52年にわたってこの劇場を愛してくれたお客様への恩返しにほかならない。
真夏に怪談を、というのは日本の芝居に限ったことではないようだ。現在、東京・渋谷のパルコ劇場で上演中の「ウーマン・イン・ブラック」(黒い服の女)。今回で5年ぶり6回目の上演を迎える秀作だ。斎藤晴彦と上川隆也の二人芝居で、東京公演終了後は作品の故郷、イギリス・ロンドンでも上演される。
何度観てもギクリとさせられる芝居だ。たった二人の科白劇であるにも関わらず、脚本の完成度が高いこと、演出家のロビン・ハーフォードの芝居の運びが巧みなのに加え、二人の役者のムードがほぼできあがっているからであろう。
中年の弁護士・キップスが過去に経験した恐怖の体験を、周囲に語ることを決意して若い俳優の助力を求める。そこで、俳優が若き日のキップスを演じ、弁護士が当時キップスに関わった人々を演じる、という入れ子のような二重構造の芝居だ。
今、日本に求められているのは、この作品のように繰り返し上演しても観客を満足させられる良質の「戯曲」なのだ。新作はポンポン飛び出すが、再演されるケースは少ない。日本の芝居において、肝心な戯曲がいかに脆弱で、良質の作品が不足しているかが良くわかる。海外の戯曲がすべて良質で、日本のそれがすべて脆弱だと言うのではない。しかし、「戯曲」というものが、時として役者と同等以上に重要なものであることを制作サイドが認識しているかどうか、の問題なのだ。
私は、日本の作家の戯曲を応援したい。そのために、あえて劇評で「練り上げての再演を期待する」というエールを贈ることがあるが、滅多に練り上げて再演されることはない。これでは、新作ばかりを書かされる作家が気の毒であり、役者も挽回の機会がないままに終わってしまう。なぜ、日本の演劇関係者は戯曲を大切にしないのであろうか。
今回の舞台で特筆すべきは演出家のロビン・ハーフォードである。外国の演出家を珍しく取り上げる時代ではないが、この芝居は彼でなくては演出できなかったであろう。怪談、としての仕組みやトラップもさることながら、一番優れていたのは「空気」である。我々には想像もつかないイギリスの湿地帯のねっとりした空気と身体にまとわりつくような湿気の質感、これを見事に演出した。「空気感覚」などという言葉はないが、その質感を演出し、観客に体感させたのが大きな効果となったことは間違いない。
この成功は、「戯曲の力」を演出家が引き出したことによる。もちろん、斎藤・上川の好演あってのことだが、「いかにいい作品を選ぶか」、「作品の力を引き出すか」が必要なのだ。そういう眼で日本の作家を育ててほしい。
「景気が悪い時にはコメディが流行る」とは昔から言われてきたことだ。今もご他聞に漏れずコメディは多いが、その質の善し悪しを判別するのは難しい。テレビでもやたらにお笑いが溢れているが、その質については言うまでもないだろう。
先日、東京・下北沢の本多劇場で伊東四朗一座「喜劇 俺たちに品格はない」を観た。共演者が三宅裕司、小倉久寛、ラサール石井、戸田恵子などの豪華さもあり、チケットは即日完売。当日券を求める行列も凄かった。
登場人物は政治家で、現在の政治を大いに風刺した内容だったが、客席の笑い方が凄かった。喜劇だから面白いのだが、それ以上に観客が「笑いたがっている」のを感じた。
世間のニュースは明るい話題がほとんどない。生活も厳しくなっている中で、芝居を観ている時ぐらいは大笑いしたい、という観客の欲望が舞台に伝わり、舞台をヒートアップさせていた。そこで愚かな政治家たちが醜態をさらすのだから、我々庶民にとっては痛快な話だ。
どの分野に限らず、回り道を嫌う人は多い。スピードが求められる時代に回り道をしている暇はないのかも知れない。しかし、結局、王道に近道はないのだ。特に、芸の道には確かにそれが言える。揺るぎない座を保っている今でも、伊東四朗は努力を怠らない。先の「俺たちに品格はない」にしても、見事に円周率を100桁暗唱して見せた。そういうバカバカしいとも言えるような挑戦が、笑いを創っているのだ。
嬉しいことに、三宅裕司がいいコンビで、彼の芸風を違った形で継承してくれそうな気がする。世代が違うから、形は変わっても、その精神が変わらなければいいのだ。こういう時代だからこそ、「きちんとした喜劇」が観たい。それに応えられる役者を大切にしたい。
「独立行政法人 日本芸術文化振興会」。ご大層な名前だが、何のことだかお分かりだろうか。平たく言えば「国立劇場」である。東京・千代田区の皇居を臨む一等地の、校倉造りの大きな劇場だ。敷地内には大劇場、小劇場と演芸場がある。また、新宿にはオペラや現代演劇などを上演する新国立劇場、千駄ヶ谷には国立能楽堂、他にも大阪文楽劇場、国立劇場おきなわ、などを有している。
お堀端という静かな環境のせいか「国立」だからなのか、世の中の劇場が生き残りを賭けてしのぎを削っているのに、何とも浮世離れしている。つい先日も、東京の新宿コマ劇場が経営不振で52年の歴史にピリオドを打つというニュースが発表され、芝居好きには大きなショックを与えたばかりなのに。
国立劇場が担っている伝統芸能の保存・振興・育成という仕事の中の、歌舞伎役者や人形浄瑠璃の研修生の育成事業は評価しよう。しかし、歌舞伎や人形浄瑠璃は、保存しなければ滅びるような、ひ弱な芸能ではない。江戸時代から体制の弾圧を受け、時には日和ながら、四百年の命脈を保って来たしたたかな芸能だ。保護してもらわなくては潰れるようなら潰れればいいだけの話だ。仮に、どこかの劇団が赤字続きだからと言って、誰が守ってくれるのか。「伝統」があり、「保存に値する」とお役所や学者先生のお墨付きが出れば、金を出すのか。食うや食わずで芝居をしている人に気の毒だ。
「面白い芝居を観てもらおう」という、劇場が第一に考えるべき精神が欠落したまま泰然自若としているところが恐ろしい。タダなら我慢もしよう。しかし、相場より安いとは言え、料金を取って見せるのだ。それも、「二百何十年ぶりに復活」だの「完全通し上演」だの、芝居の楽しみは置き去りのまま、人を四時間も椅子に縛り付ける拷問のような真似をして平然としている。その上、肝心の歌舞伎公演は年間に半年で、残りの半年は貸し劇場である。これが天下の「国立劇場」の姿であろうか。これでは都心に巨大な倉庫が建てられているようなものではないか。
かつて、昭和の名優たちが最後の光芒を放った「仮名手本忠臣蔵」の通し上演などの名舞台は、「国立」だからこそ出来たことだろう。しかし、開場42年を迎えた今、時代の流れも観客の意向も関係なく、ひたすら「守る」だけで、激変の嵐が吹き荒れている演劇界に貢献できるのか。古典芸能の劇場だからと、制作者の感覚が古典化し、硬直してどうする。観客のことを考えた芝居創りが劇場の最優先課題であることはわかっているはずだ。
先月この舞台を観た時に、料金設定が実に細かいのに気づいた。席数907の「四季劇場・秋」で、実に6段階の席種・料金が設定されている。S席の9450円を筆頭にA席7350円、B席5250円、C席3150円、バルコニー席4200円、バルコニー学生席2100円。
眠れる巨象よ、太平の眠りから覚め、「さすが、国立劇場!」と言われる芝居を創れ。
劇団四季がミュージカル「李香蘭」を上演中である。実在の人物を劇化した芝居は多いが、「現存の」という点では稀なケースである。
今の若い世代は知らないだろうが、「李香蘭」は戦前にすでに大スターであり、そのコンサートを聴きたい群集が、当時有楽町にあった日本劇場を七回り半取り囲み、警察が出動したというほどだ。戦争の中、国策によって中国では「歌う中国人女優」として人気を博した。しかし、敗戦後はスパイとして、中国で裁かれた。死刑判決が下る寸前に、日本人であることが立証された、というドラマ顔負けの半生である。
その後は本名の山口淑子に戻り、テレビの司会などを経て参議院議員として国際交流を中心に活躍してきた。最近は昔のCDが復刻されており、往年の名曲が簡単に聴ける。「蘇州夜曲」や「支那の夜」などのヒット曲は美しい。現在表立っての活動はしていないが、往年の美貌を残した、歴史に残る女優だ。
こうした事実をもとに劇団四季が1991年に東京・青山劇場で初演、今年で17年になった。初演の折には歴史劇のような感覚だったが、回を重ね、劇場を変えることで芝居の密度が濃くなった。そして、単なる歴史劇を超え、時代を生きた一人の女性の姿が活写されるようになり、上演回数も800回を超えた。
こういう芝居を、戦争を知らない世代や若者に観てもらいたい。
先月この舞台を観た時に、料金設定が実に細かいのに気づいた。席数907の「四季劇場・秋」で、実に6段階の席種・料金が設定されている。S席の9450円を筆頭にA席7350円、B席5250円、C席3150円、バルコニー席4200円、バルコニー学生席2100円。
いくら芝居が観たくても、チケットが10000円を超えると、気軽には出かけられない。しかし、観る席に応じてこれだけ細かい料金の設定がしてあれば、その時の状況に応じてチョイスすることができる。劇団四季の「ビジネス」としての巧さ、である。
もっとも、これが本来の姿なのだ。大劇場で2段階ぐらいの設定しかなく、一階の一番前も二階の後ろの隅も同じ一等席、という乱暴な料金設定をしている劇場が多い。中には全席同一料金という劇場もある。観客の目ではなく、「数字」でしか芝居を見ていない証拠だ。
本当に芝居を観てもらいたければ、次の世代の観客になる今の若者に、いかに芝居に親しんでもらうかを考えるだろう。劇場が自分で敷居を高くしていては、芝居の発展や観客の若返りなどあるわけがない。
「李香蘭」の半生は単なる波乱万丈ではなく、「国」が介在していた。その意味は重い。だからこそ、若者に見せたいのだ。
昨年京都の南座で上演し、今月中日劇場で幕を開けた前進座の芝居である。中村梅之助が法然を演じ、嵐圭史がその弟子・親鸞を演じている。劇団の二枚看板が、歴史に残る宗教家を演じる芝居で、今後は大阪や東京などの大都市をはじめ、日本各地を巡演して、再来年まで続ける四年がかりの大きなプロジェクトだと言う。
ある意味で、宗教家を扱った芝居は興行的には非常に難しい。特定の宗派の祖を描き、その功績などを喧伝すると、それが反発や誤解を招く恐れがある。もっとも、芝居に思想や宗教を持ち込むのは今に始まった話ではなく、宗教はともかくも何らかの「想い」がなくては芝居にはなるまい。
今回の芝居を観てまず感じたのは、これは宗教劇ではなく「人間讃歌」なのだ、ということだ。歴史の教科書に出てくる「偉い人のお話」を見せるのではなく、そういう人々がいかに人間臭かったか、我々と同じような迷いや苦しみにとらわれて生きていたのか、を描いたものなのだ。
浄土真宗の祖である親鸞は恋に悩む自分の心のありように悩み苦しみ、法然に相談をする。極端な言い方をすれば、現代の若いサラリーマンが、酒場で気のおけない先輩に恋の悩みを告白しているようなものだ。こんなことを書くと、「宗教に対する理解が浅い」とお叱りを受けそうだが、この芝居は、最終的には「人間なんてそんなものだよ」と語りかけているように思えてならない。
ある意味で興味深かったのは、七十七年の歴史を持つ老舗の劇団が、興行的には決して派手とは言えない仕事に四年の歳月を費やそうとする姿勢だ。さすがにブロードウェイ・ミュージカルは上演しないまでも、歌舞伎から現代劇、和製ミュージカルまで幅広いレパートリーを持つ劇団が、こういう仕事をコツコツする。その姿勢がいかにも前進座という劇団らしいのだ。
話題を集め、チケットを売るために、人気スターをゲストに迎え、何とかその場を乗り切って次を考えよう、というケースが多い中、前進座は不器用な道を選択しているように思えてならない。「役者はそろばん勘定をしない」という時代ではないが、それでもなお、「儲けたいけどいい芝居を…」というギリギリのせめぎ合いの中で苦しんでいる。何とも微笑ましい役者馬鹿の集団である。
この芝居の中で「若き日の法然」を演じている劇団の二枚目・嵐広也が終演後にこう言った。「僕の芝居、どうですか?」。「まずまずじゃないかな」と答えた私に、「いや、悪いところが聴きたいんです」と。ああ、ここにも愛すべき役者馬鹿がいた。
明治二十一年に「壮士芝居」として従来の歌舞伎に対する「新しい劇」として新派が誕生し、今年で百二十周年を迎える。東京や京都で記念公演が予定されているようで、歌舞伎に次ぐ歴史を誇る日本の伝統演劇だ。
しかし、新派の長期低落傾向は甚だしく、一向にそれを脱することができない。かつて、昭和の劇壇を彩った初代水谷八重子や花柳章太郎、大矢市次郎や市川翠扇などの先達が残した財産演目は数え切れないほどだ。それを初代の愛娘である二代目水谷八重子や波乃久里子が受け継ぎ、命脈を保ってきた。
新派の芝居には日本人の求めてやまない「人情」がある。「情愛」がある。こうした感情は、時代を経ようとも古びるものではないし、川口松太郎や北條秀司らの劇作家が新派に遺した作品には、情が溢れている。川口の「遊女夕霧」にしても北條の「太夫さん」にしても、今の世の中に薬にしたいような情感がたっぷりだ。遊女でありながら客に惚れてしまい、一緒になれないことがわかっているのに、男が犯した詐欺の尻ぬぐいに謝って歩く女の姿。「そんな馬鹿な」という話だが、そこが芝居、名優の手にかかれば見事に泣かされるのだ。こういう芝居はいくらもある。
しかし、今度の記念公演が「婦系図」の通しと「鹿鳴館」だと聞いて、あまりの工夫のなさにがっかりした。どちらも作品としては素晴らしいものだが、せっかくの新派百二十年のお祝いだ、もう少し新しい試みがあっても良いだろう。別れ話と夫婦のもつれから来る悲劇では興もそがれるというものだ。初代の水谷八重子を知らずとも、新派の芝居に憧れて入門する若い役者はいるのだ。日本人の根源的な感情を見せる新派の芝居が、今、獅子奮迅の努力をしなくては、百五十年のお祝いはできないかも知れないのだ。
芝居は観客が入ってからの評価だ。観客が観たい芝居は何なのか、この時代に何が求められているのか。それをきちんとリサーチしないで、先人の財産だけに頼っていたのでは、血と涙で築き上げた新派の歴史から輝きが失われてしまう。日本の芝居の大損失だ。今こそ、「新派ここにあり」という底力を見せてほしい。芸者姿の似合う女優がたくさんいて、粋な科白を知っている役者が大勢いる。こんな劇団が他にあろうか。
新派よ、今こそ甦れ!百年記念を前に亡くなったある老優の言葉を思い出した。見舞いに訪れた時、ベッドの上で私の手を握り、「百年記念の口上には出られるように、と思ってますから」と涙をこぼしたのだ。そういう先輩の想いを無駄にするな!
年明け4日に東京の「ルテアトル銀座」で幕を開けた平岳大主演の「ジンギスカン」にベテランの若林豪が出演している。ちょっとした場面でも「さすが」と思わせる腕はたいしたものだ。稽古の後などで交わす雑談の中に、師匠である島田正吾の話が出た。
島田正吾。言わずと知れた名優で、辰巳柳太郎との名コンビで新国劇の黄金時代を築き、辰巳亡き後は一人芝居に精力を傾け、96歳まで舞台に立ち続けた役者である。
若林豪は、島田の直弟子に当たる。昭和45年に新国劇の財産演目である「人生劇場」で大抜擢され、島田の吉良常を相手に飛車角を演じた。その苦労たるや並大抵のものではなかっただろう。しかし、それが実り、人気者になって新国劇を退団後は、活躍の場をテレビや舞台に広げることになる。若き日の彼に役者としての性根を叩き込んだのは島田である。
私との雑話の中で、若林は今でも島田のことを「オヤジがね」と懐かしそうに呼ぶ。失礼ながら、70歳に手が届こうという大ベテランが、今でも亡き師匠を慕い続け、まるで恋人の話をするようにエピソードを語る。
無論、楽しい想い出ばかりではなかっただろう。叱られて悔し涙に暮れた日々も、大失敗もあったはずだ。しかし、そうしたものも含めたすべてが師匠と自分の想い出になり、芸の肥やしになってきたのだ。
若林が新国劇を退団する時に、島田がラグビーボールの形をした革のトランクをくれたそうだ。中に入っていた手紙には、「困った時には、このトランクの匂いをかげ。ここには俺の芝居が詰まっている」と書いてあったそうだ。まるで一幕の芝居のような名科白であり、その話を嬉しそうに語る若林の顔を見て、鼻の奥がきな臭くなった。
厳しいながらも、絶対的な信頼に結ばれた師弟関係。今の演劇界にはなかなか見られない光景だ。「人を育てる」ことは、どの世界でも時間がかかる。しかし、自分の思うように育つ保障はない。それでもなお、芝居を志す若い人々のために、厳しくも暖かい眼で後進を育てようとする「師匠」、その大きさに圧倒されながらも必死の想いで、一歩でも師匠に近づこうとする弟子。厳しくも羨ましい姿だ。
今の時代、ちょっとうるさいことを言えば「じゃあ辞めます」と簡単に言われる世の中だ。また、人の面倒を見る余裕もない。しかし、師匠と弟子の間に横たわる「情」は、時代の流れや金銭で変わるほど柔(ルビ:やわ)なものではない。
折から「芝居の神様 島田正吾・新国劇一代」という評伝が吉川潮の手で新潮社から発刊になった。この本にも、師弟のエピソードがたくさんある。演劇界で活躍しているベテランの多くは、こういう師匠を持っていたのだ。今必要なのは、役者、スタッフ、評論家を含め、うるさいことを言って叱ってくれる「お師匠番」なのだ。うるさいことなど、愛情のない人には言えないのだから。
若林豪の師への追慕は、一生物の財産である。
