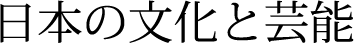
�@�����l�̌|�����ꂱ��ƌ���Ă��Ă��d�����Ȃ��̂ŁA���܂ɂ͎����̎ŋ��Ɋւ���l������邱�Ƃɂ��悤�B�ӂƂ������Ƃ���ŋ��̐��E�Ɋւ��������A�C���t������O�\�N�ȏ������ʂ������Ă���B���̊Ԃɉ����E�͑傫���ϖe���A�������芪�����Ԃ��ς�����B�����č��A�Ƃ��Ƃ��ߗ��ɂȂ��X�͊��ɓ˓������B�����̎ŋ��̎��̒ቺ�͖ڂɗ]����̂�����A���̂܂܂̏�Ԃ������A����ɂ͊ՌÒ������A���҂̎d���͂Ȃ��Ȃ�A�ŋ��̐�������B�ϋq�́A�����u�ʔ����ŋ��v���`���C�X����]�n���Ȃ��Ȃ�B�ꌩ����Ɗ�����悵�Ă��邩�̂悤�����鉉���E�����A�����ɂ���Ă͂܂��Ɂu�R���Ղ��v�ɂ���̂��B���̒���́A���낢��ȂƂ���Ɍ����Ă���B��������čs�����B
�@�^�C�g���ʂ�A����ŋ��́A�ق��Ă��Ă��`�P�b�g�̒D�������ɂȂ�B�u���v�͂Ƃ������A�����B�e���r�Ŗ��̔��ꂽ�X�^�[���W�߁A�m���x�̍�����i���A�����ȉ��o�Ƃł̊ŔŌ�����B���������ŋ��́A������B�ϋq���A�ŋ����̂��̂����u���̒N�X�v�̎p���ςɍs���������炾�B�����悤�Ȃ��Ƃ����Ă��Ă��A������ꍇ������B���̍��͔��ɔ����ŁA����̏ꏊ���Ԃ�̈�l�������肷��B����Ȃ��ŋ��́A������L���l����ׂĂ�����Ȃ��B�����ɂ́A�v���f���[�T�[�̃Z���X�̖�肪���邩�炾�B
�@�������N�A���̓�ɕ��������Ɍ������Ȃ����B�ŋ��������ł���ȏ�A�ׂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����O����B����͋��s��Ђ̊�Ƙ_���Ƃ��Ă������R�̘b���B�������A���̈���ŁA�u����̕����v��n��d���ł����邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̃o�����X����������Ԃ����������߂ɁA�����E���X�͊��ɓ˓������̂��B�u���v�����u���v�v��Nj����邱�Ƃɂ������S�������߂ɁA�ϋq���x����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B
�@�ŋ��͌�y�Ƃ��Ă͔����ґ�ȗV�т��B1��10000�~����`�P�b�g�͂���ɂ���B�����o�X�c�A�[�Ȃ牷��ɂ��s������z���B�ŋ����ςɍs�����߂ɁA����Ȃ����͉�Ђ��猀��֑����^�сA�ǂ����̃^�C�~���O�ň�x�͐H�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ԓI�ɂ����K�I�ɂ���ςȗV�т��B10000�~�̃`�P�b�g�́A����1000�~�̃A���o�C�g10���ԕ��̒������B����Ƃ�����Ƃ̃A���o�C�g�オ�ŋ���{�Ŕ��ł����B���ꂪ�A12000�~�����Ă��ǂ������A�Ǝv������̂ł���܂������A�u�����10000�~�I?�v�Ƃ����ŋ��������ď��Ȃ��͂Ȃ��B��������{�̏���҂����ƂȂ����Ă��A����ł͌���֑����^�Ԑl�����Ȃ��Ȃ�̂����R���B���g�̐l�Ԃ�����ֈ�������o���͕̂����̎d���ł͂Ȃ��B
�@�u�ϋq������ŋ��v���u�ǂ��ŋ��v�ł��邩�ǂ����Ƃ����ƁA���̌����͕K���������藧���Ȃ��B������ϋq�������Ă��A�u����́H�v�Ǝv�����̂����邵�A�K���K���ł������ŋ��͂���B�����̌��ɂ߂�����̂͊ϋq�ł����]�ƂȂ̂����A���̐����������͂��Ă���̂��ǂ����A�͂Ȃ͂��^�킵�����̂�����B
�@�|���̂́A�ϋq�����������Ƃɂ���āA���̎ŋ��̕]�����������̂��Ɗ��Ⴂ�����鋻�s�T�C�h�ł���B�܂��A�₩�Ȋ�Ԃ��b��Ɋ��D���āA���`�P�b�g�ɌQ����ϋq�̐S���ł���B���̓C���^�[�l�b�g�̐�s�\��Ȃǂ̃V�X�e����������O�ɂȂ��Ă���A�ŋ��̓��e���낭�ɂ킩��Ȃ������Ƀ`�P�b�g���P�[�X�����ɑ����B�V��̏ꍇ�Ȃǂ́A���̓`�P�b�g���������ꂽ���_�ł܂��r�{���o���Ă��Ȃ��A�ȂǂƂ����̂͂���ɂ���B���ꂪ�v���̂���d���ƌ�����̂��낤���B�����Ƃ��A����Ȃ��Ƃ܂ł͈�ʂ̊ϋq�ɂ͂킩��Ȃ��B������������ƂɁA�����������Ȃ��܂���ʂ��Ă���̂ł���B
�@�G���^�e�C�������g�Ƃ̂��Ă̎��͂Ƃ��������A�ϋq��������ꂪ���тɂȂ�A���������傫���Ȃ�B����͂����̐��E�ł��������Ƃ��B�������A���ꂪ���z�������Ă���̂��B
�@���A�H�i�Ɋւ��ďܖ������Ȃǂ̖�肪�ߕq�Ȃ܂łɂ₩�܂�������ł���B�̂͂���Ȃ��̂͏���҂̖��o�Ŕ��f���������̂��B����͂Ƃ��������A��X���ߏ��̃X�[�p�[�œ��������Ƃ��悤�B������ƂɎ����A��A�J���������Ɍ��ȓ����������肨�����Ȗ�������A�X�[�p�[�֕ԕi����������߂�͓̂��R�̍s�ׂ��B�������A���������ōl�������ɁA�ς��ŋ����܂�Ȃ��Ă��A�N���u����Ԃ��v�Ƃ͌���Ȃ��B�O���Ɏn�܂�A���{�l�̂��ƂȂ����ɂ͂�����Ԃ�قǂ����A����ł͊��S�ɂȂ߂��Ă���ƌ����Ă��d��������܂��B�����Ȃ�Έ꒚100�~���x�����A�ŋ��͐�ɏ������悤��10000�~��������̂͂���ɂ���B��������Ԃ������Ċςɏo�����A���ʂ��ʔ����Ȃ��Ƃ��A�������킸�ɖق��ċA���Ă���B����ł����̂��낤���H�@�{���̂Ƃ���������A��X�]�_�Ƃ����������A���ʂ̉����t�@�����u�܂�Ȃ��v�Ƒ吺���グ�Ă��ꂽ�����A�ꍇ�ɂ���Ă͌��ʂ�������̂Ȃ̂��B
�@����A吐�K�Y���o�́u����A�킪���e���ʕP�v���ς��B���R�I�V�������̏��`�ɕ����邱�Ƃł��b����W�߂����A���̃��X���[�E�`���������������E���ǂ����ǂ������炠��Ȏŋ��ɂȂ��Ă��܂��̂��A�܂������킩��Ȃ������B���͂�A�u�V����吐�K�Y�v�ɑ��Đ^�������畨��������l�����E�ɂ͂��Ȃ��̂��낤�B�����ȑO�����V���ɏ��������������َE���ꂽ�����������B����͂Ƃ��������A�ĉ��̍�i�łȂ�����́A�ϋq�͎ŋ��̓��e��o���s�o����m�炸�Ƀ`�P�b�g�����ƂɂȂ�B���̐ӔC�́A��̒N�����̂��낤���B
�@���{�̎ŋ��́A�A�����J�Ȃǂƈ���Ă�����]���������Ă��A�����N���[�Y�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B���߂�ꂽ���s���Ԃ͕K���㉉����B��H�y�߂��ɑݐ�c�̂������Ă��邱�Ƃ�����̂��낤���A���̓I�ɋ��s�T�C�h�ɃV�r�A����������̂ł���B���s�͂���Ӗ��ł́u���Łv�ł���A�����J���Ă݂�܂ł͊ϋq�����邩�ǂ����͂����܂ł��u�\�z�v�͈̔͂ł���B�O����ł͔���Ă��Ȃ������ŋ����A�������J���Ă݂�ƈӊO�ɕ]�����ǂ��A�ϋq�̌��R�~�łǂ�ǂ�`�P�b�g������Ċ����ɂȂ���A�Ƃ����P�[�X�����Ȃ��͂Ȃ��B�[�����s���Ȃ��̂́A��L�̂悤�ȗ��R������ɂ��Ă��A���߂�ꂽ���ԉ��X�Ǝŋ��𑱂��Ă��邱�Ƃł���B�ȒP�Ɍ����A�����ɂ́A���s�t�̗ǐS���Ȃ����炾�B�u�����������\����Ă���ŋ��ł����A�����J���܂������̂́A���q�l���炨���Ղ��Ă���������悤�Ȃ��̂ł͂������܂���v�ƌ�����E�C�̂��鋻�s�t�͂��܂��B�܂��A���G�ɗ��ݍ��������̉����E�̃V�X�e�����A�ǐS�����������s�t���E���悤�ɏo���Ă���B���ɁA�̘b�����A�����̎��q�������ł��������s�ׂ�������v���f���[�T�[�������Ƃ��悤�B���̎��ɁA�u���������������v�Ɣ��Ȃ���̂Ȃ�Ƃ��������A�u�ꃖ���̃X�P�W���[�������̂ɂ���Ȃ��ƂɂȂ�A�ǂ����Ă����B�����̃^�����g�̕]����������ł͂Ȃ����B���������o���v�ƌ������˂Ȃ�������������̂��B����ł́A�S�̒��ł��q�l�Ɏӂ���ŋ��𑱂��邵������܂��B
�@�u���O�͂ǂ��Ȃv�ƌ���ꂩ�˂Ȃ����A�܂����������ŋ����}�X�R�~���ٌ삷��B�V���̌��]���܂Ƃ��Ȍ��]�Ƒ����邩�ǂ����͂Ƃ��������A���������Ȑ�`�L���������A�����ł��ϋq�����ɋ��͂����鏑���肪����B�u�������ΐO�����v�Ƃ͂��̂��Ƃ��B
�@�����ɂ́A�L���p�V�e�B��30�l���x�̌��ꂩ��A2000�l����R�}����̂悤�ȑ匀��܂ŁA�u����v�ƌĂ���Ԃ������̂����m�ɂ͂킩��Ȃ��قǂ��B�ꉞ�A������A������A�匀��ƕX�I�ȋ敪�͂����Ă��A���m�Ȓ�`������킯�ł͂Ȃ��B�����Ƃ��A������⒆����ƌĂ��Ƃ���̑����݂͑�����Ƃ��Ă̌����������A���܂茀��ł̎��吧��͂��Ȃ��B���Ƃ��A�̕������V��������ƌ��������|�n�̑匀���A�鍑����A������ˌ���Ȃǂ̓���n�̑匀��A�Ɨ��̖������Ȃǂ����吧������ŋ��s���s���B�������A���������匀�ꂪ�u�����v��Ԃ��͂Ȃ͂������B����Ƃ��Ắu�R���Z�v�g�v�������Ȃ��A�ꓖ����I�ɂ��̌������̂����Ƃ��ł������ł悵�A�Ƃ����X�^�C���ɂ��������Ȃ��̂ł���B
�@���Ƃ��Β鍑����B�N��12�����̌����̂����A���{�̎ŋ���������̂͂�������2�����ł���B��̓W���j�[�Y�����������ւ݂̑������ƁA�����ς��ʓ���~���[�W�J���̃����O�����������B�ʂɍl���Ă����A�ǂ̌����ɂ�����Ȃ�̗����͂����A�]���ł�����̂�����B�������A�N�Ԃ̃��C���A�b�v��ʂ��Ă݂����ɁA�u���ꂪ�V���̒鍑���ꂩ�v�ƊS�Q�������Ȃ�悤�ȓ��e�ł���B�����f���炵�����Ƃ��ƐS�̒ꂩ�瓌�l���Ă���A�ϋq�����̋^����Ȃ��̂ł���A���̍l�������������A�Ƃ������ƂɂȂ�B�������A�u�ׂ��肳������Ή��ł������v����́A�����I����Ă��邱�ƂɁA���s��Ђ��C�Â��A�݂𐳂��Ă��̖��ɐ^���ʂ����������Ȃ�����A�����̒[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B���̓���ɂƂ��ẮA�u�m���ɋq�������ł���v�Ώۂ��~���[�W�J���ł���A�Ƃ��������ɉ߂����A�ϋq�����̌J��Ԃ��ɖO�������ɂǂ�����Ηǂ��̂��A�܂��A���̎ŋ����ǂ��u��ĂĂ����̂��v�Ƃ����r�W����������悤�ɂ͌����Ȃ��B�������ł����Ă��������ŏ������̂����A���s��Ђɂ́u��Ă�v�`��������̂��B�ŋ���ł��Ėׂ��邾���ł͂Ȃ��B����Ɠ����ɁA�ϋq���A���҂��A�X�^�b�t���A�ŋ�����Ă�`��������B����́A����̑n���҂ł��鏬�ш�O�����|�̑n�Ǝ҂ł����J�|���Y�A���䏼���Y���A���V�̕������n�����������O���A�������̃I�[�i�[�������O�c���g���A���s�t�Ƃ��Ė��𐬂����l���݂͂Ȃ����Ă������Ƃ��B�u���͎��オ�Ⴄ�v�Ƃ͌��킹�Ȃ��B���������傫�ȗ���̂��ƂɁA���{�̉����Ƃ����y�낪�琬����Ă����B����́A��ʂ̊ϋq�Ɍ��ʂƂ��Ă��̐ӔC���y�Ԉȏ�A���s��Ђɉۂ��ꂽ�d�v�ȐӖ��Ȃ̂��B�ǂ����A�����Y��Ċ�̑O�̋��s�����Ɋ�������点�Ă��邩��A��������̂��B
�@���č����I�̎肾�����O�g�t�v�́A�u���q�l�͐_�l�ł��v�ƃX�e�[�W�ŏ�Ɍ����Ă����B���̌��t���A�����̏ے��̂悤�Ɏg���l�����邪�A����͂����������ł���B�������đ����^��ł���邨�q�l�̂������ŁA�X�^�[�����݂��邱�Ƃ��ł���̂��B���́A�v���f���[�T�[�ɐ_�l��������A���o�Ƃ��_�l��������A���҂��_�l�ɂȂ����肵�Ă������ŁA�̐S�̂��q�l�͂����u���Ă��ڂ��H����Ă���悤�ȏ��B����ł́A����ɊՌÒ������̂������͂���܂��B�������������珵���Ă���̂͌��ꎩ�g�Ȃ̂��B����T�C�h���A���M��������12000�~�̐��D�����邱�Ƃ��ł��A�g�K����Ăł��ς����Ǝv���ŋ�������Ă��邩�ǂ����A���͂����ɂ���̂��B
�@�������Ă���͉̂����������ł͂Ȃ��B���|�Ƃē������Ƃ��B�̕����V�h�́u�`���|�\�v�����ɕ����Ă��鏼�|�̖��͂܂��ʂ̖ʂŏ����[���B
�@�������܂ŁA�u�ŋ��v�ƌ����Ή̕��ꂵ���Ȃ������B�����ɁA�V�����o�ꂵ�A�ꐢ���r�����̂��V�h���B�����ʼn����j�̕����������͂Ȃ��̂ł����܂łɂ��Ă������A�ȗ��A�����̊ϋq�𒆐S�ɐl�C���W�߁A���N�őn��120�N���}���闧�h�ȌÓT�|�\�ł���B�Ǝ��̏��`�|�Ŋ쑽���ΘY��Ԗ��͑��Y�Ȃǂ̖��D�ق��A���㐅�J���d�q���V�h�ɂ����鏗�D�̌|���m�����A���ꂪ���݂̓��ڐ��J���d�q��g�T�v���q�Ɏp����Ă���B�ƌ����Ε������͂������A�f���炵�����{�l�̏��L���Ɏ����Ă���ŋ��Ȃ̂ɁA���̒����ᗎ�X���͈���Ɏ��~�߂������炸�A120�N�L�O�ʼn��U�A�ƕ����Ă������E�ŋ����l�͂��Ȃ����낤�B
�@���̗��R�́A�ȑO�����V���ɂ����������A���������悤�Ȏŋ�����������A�̑�Ȃ��l�����̒z������Y��H���ׂ��Ă������ŁA�����H�v���Ȃ����炾�B�̕���̋������ɑ��A�����Ŕj���ĐV�����ŋ���n�낤�A�ƎY�����グ���͂��̐V�h���A���܂�̕���������ԈˑR�Ƃ����̂̂܂܁A�]����ԂɂȂ��Ă���B�̕���͂��Ƃ��Ƃ��u���̐��v�̌|�\�ƌ����Ă��悭�A��@��q���Ɏ@�m���A���̌��͂̈�����Ȃ���l�S�N�������Ă��邵�������Ȍ|�\�ł���B�ᔻ���悤�����ł��낤���A��ɕЕ��̊�ł́u����v���ӎ����A�ϋq�Ƌ��ɕ������Ƃ����p��������B�������A�̕���Ƃđ����̖�������Ă���B�ꌩ�������Ɍ�������҂̑w���A�̕���̋��s�����������߂Ɏ蔖�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�e���̕���A���ڂ̑I���`���v�̐��ނȂǁA���͑����B�������A�܂����������ӎ��������Ă��邾���~��������B
����̐V�h�́A���������Ӗ��ł͗��ڂ��ׂ�Ă���ɓ������B������A�l����ς���A�Ƌ���ł�����ɉ��߂�C�z���Ȃ��Ƃ��������ƁA���͂⎨���������Ȃ��̂����m��Ȃ��B�V�h�̎ŋ��ň���������A����Ȍ��e�������˂Ȃ�Ȃ��̂͒ɐȑz���ł���B�������A�|�҂��O�\�l����ɂ����ƈꎅ���ꂸ�ɕ���ɕ��ׂ邱�Ƃ̂ł��錀�c�����ɂ��낤���B���ꂾ���̓`���Ɨ͂������Ȃ���A����ӂ��Ă���������������A�{����ЂƂ����Ȃ̂��B���Ă̐V�����̂悤�ɁA�U�X���s����������A���܂�A��s���Ă̔s��ł���܂�����̗܂����ڂ����B�������A������͓��y���q���e�̈�Y���g���ʂ����Ĕj�Y���O�ɂȂ��Ă���悤�Ȃ��̂��B���̃c�P�́A�����܂ł����玩�������Ŏ�邵������܂��B���ꂪ�A���ɗ�̂Ȃ��L���Ȉ�̕����̓����������Ƃ��A�Ƃ����傫�ȍ߈����Ƌ��ɁA���̗܂𗬂����Ƃ��B
��U��̂��A�S����V�h�̖��҂������u�l�I�V�h�v�ł��u�j���[�V�h�v�ł����Ηǂ��̂��B���X���A�V�h�̗��j�Ƃė����W�U�̌J��Ԃ����B�����������Ĉ������R�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B���ꂪ�ł��Ȃ��̂́A��l����D���ȁu�������v�v�Ƃ������ׂ��`���̏�ɂ�����������Ă��邩��ł���B�V�h�̍�Ƃł��������v�ۓc�����Y�̍�i�̖��͂ɖ������A�N�Ɉ��W�������������҂������W�܂��ăR�c�R�c�Ǝ�ł��̂悤�Ȏŋ��𑱂��Ă����u�݂��v�����̓w�͂ɑ��ė��h�ȏ܂����B������ςāA�V�h�̃v���f���[�T�[����҂͉����������̂��낤���B����A����͋��ł������B�����������Ă���A�s���Ɉڂ��̂�����ȍs�ׂł���B���������Ă��Ȃ��̂��낤�B�����f�����Ă�����͌����܂��B
��l�����ʌ����̖��l�ł��邱�Ƃ͎�����������܂ł��Ȃ��A�����̃j���[�X�Ō��ƌ����قǕ������Ă�����Ă���B���c�改���B�c���̂܂�O�A�s�S�ł��ꓙ�n�ł���B�����b�Șb�����A������قǂł��낤���B3000���~�Ƃ��āA��X���ꐶ�܂ɓ����Ƃ����悤�ȑz���ł����߂āA����ƈ�̓y�n�������邩�ǂ����A�ł���B����ȏꏊ�ɁA����ȑq�ɂ�����̂����������낤���B���̖����u��������v�Ƃ����B�����ɂ͑匀��A������A���|��ƎO�̌���Ȃ����̓z�[��������B�����h�ӂ����߂Ă��̋���Ȍ�����u�q�Ɂv�ƌĂ̂́A���h�Ȗ��O���t���Ă���ɂ��ւ�炸�A����������N�Ԏ������A��͗x��̌����Ȃǂ݂̑�����ɂȂ��Ă��邩�炾�B�������̉̕�������̂����̓��́A��Ɋw����ΏۂƂ����u�̕���ӏ܋����v�ŁA�̕���̕��y�ɓw�߂Ă���B�܂��A�̕�����҂╶�y�Z�|���Ȃǂ̈琬���Ƃ�����ɍs���Ă���A�������ƂłȂ��Ă͂ł��Ȃ��d�v�Ȏ��Ƃ͕]�����Ă悢�B�������A�̐S�̌���������K���K���Ȃ̂͑傫�Ȗ�肾�B��������͍����s�́u�Ɨ��s���@�l�v�ŁA���a41�N11���ɊJ�ꂵ���B�����͉̕���́u�ʂ�������v��v�����㉉����Ȃ��u���������v�̏㉉����ȖړI�ɂ��Ă������A�����͂����������̂���ł��Ȃ��B�̕���̎O�喼��ƌ�����u������{���b���v��u�����`����K�Ӂv��u�`�o��{�N�v�����ꂼ��O���������Ēʂ��ď㉉����ȂǁA����I�Ȑ��ʂ��c���Ă���B
�@���̈���ŁA��S���\�N�Ԃ�̕����I��ȂǂƖ��ł��ĎU�X���ɂ����Ȃ��ŋ����㉉���Ă����B����Ȃɒ����ԏ㉉����Ȃ��̂́A����Ȃ�̗��R������킯�ŁA�ʔ���������Ԃ�u�����ɌJ��Ԃ��㉉����邱�Ƃ͒N�ł��킩��B�������A�������u��������v���鏊�ȂŁA�ʔ����낤���܂�Ȃ��낤���A�u�����㉉����v���ƂɈӖ�������̂ł����āA�u���������v�Ƃ������������c���A�ϋq���Q�Ă��悤�����ł��낤���W�͂Ȃ��B�����Ԃ\�Șb�����������̂��B
�@������̉̕���̊ϋq����Ă邽�߂́u�̕���ӏ܋����v�������Ԃ����ƍs���Ă���A���ɂ킽���Ċe�n���璆�w�E���Z�����W�܂�B�e�Ȃ̂́A�ŏ���30���قǁA���̉̕�����҂��u�̕���̊ϕ��v�̂悤�Șb�����낢��ȍH�v�Řb���A������B���̌�A��������͂Ȃ��̕�����㉉����̂����A�ˑR�̕���������Ɂu�����A�s�v���ꂽ���k�����̂��܂т������͑�ςȂ��̂��B�������A������̕��ꂪ�n�܂��ē�\�������Ȃ������ɁA���̌����ɐÂ��ɂȂ�B�݂ȋC�����悳�����ɖ����Ă���B���J���O�Ɂu�����ȁI�v�Ǝ����Ă����搶���A�r�g�݂����A������J���ĐS�n�悳�����ɓ�����̔�������Ă��镗�i�Ȃǂ͔��܂�������������B���̉̕���ɔ�ׂė����͗y���Ɉ������A����łقƂ�ǂ̐l�Ԃ��������Ă���悤�Ȍ����ɉ����^��������Ȃ��̂��낤���B�u�ӏ܋����v�������Ƃ�������͂Ȃ��B����u����Ȃ�A�V�������@��͍����Ă͂ǂ����A�Ƃ����A�h�o�C�X�ł���B����ł͖��҂����C���Ȃ������낤�ɁB
�@�������āA���̔��Ȃ��Ȃ��܂܂Ɂi�����̔��Ȃ͂��������m��Ȃ����A���P�͂Ȃ��j�A���N�̂悤�ɓ�����Ԃ������Ă���B�̕�����͘A������ꂪ�����Ă��Ă��A��������ł���Ȍ����͂܂��ɐ�����قǂ����Ȃ��B��A��������ɓ���̗]�n������Ƃ���A�̕�����҂̂قƂ�ǂ̐Ђ����|�ɂ���A���|������҂��u��Ă���v����ɂ��邱�Ƃ��B�������A���ꂪ�o����40�N�ȏ���o���A���C���o�g�̖��҂��疼��i�����j�o�D�܂ŏo���Ă�����т������Ă���̂�����A�ɒ[�Șb�������������Ŏ��O�̉̕�����҂������Ă��Ă������͂���܂��B���������A�O�Ɍ�����w�͂����Ď��s�����̂Ȃ�܂����������邪�A�c���O�̈ꓙ�n�Ō���ɊՌÒ��̑�������Ă���悤�ł́A�u�q�Ɂv�ƌ����Ă��d��������܂��B�������̓X�P�W���[�������܂��Ă��Ă��A�݂�����ɂ��邽�߂ɍ����̌����������͂��͂Ȃ��̂�����B
�@�匀�ꉉ������������Ă��Ă����̎ŋ��̊ϋq�ɐ\����Ȃ��̂ŁA�������ς��ď�����̘b�����悤�B��̂����̏����c������̂��A���m�Ȑ����͒N�ɂ��킩��Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B����͂���ł����B������c�����邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��B���Ȃ̂́A�ʐ����̒��Łu�v�����|�I�ɑ��������߂ɁA�ꕔ�Łu������̓_���v�Ƃ����A�_���ɂȂ�Ȃ��ᔻ���N���邱�Ƃ��B���́A�u�ǂ�������ŋ��v�̌��������������Ȃ�̔��f��Ō��Ă���B�܂��A�T�[�N�����o�̌��c�ł͂Ȃ����ƁB����������Č����Ă��Ă��A�����������c�͔��ɑ����B���ꂪ�A������̎ŋ��̔��W�ɐ�����������ɂ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���B�ǂ�������ŋ��́A������Ƃ������[�_�[���A����������������Ă���A��������c�������������̂ł͂Ȃ��[�����Ă��邱�Ƃ��B���������Ƃ���́A���������������ɁA�傫�ȕ���֖��o��`�����X�������Ă���Ǝ��͍l����B�����Ƃ��A���̂��ׂĂ��������A�ƌ����킯�ł͂Ȃ��B�r���𗁂т�̂͂��̒��̐����Ƃ����������낤�B
�@���Ƃ����[�_�[�����Ă��A���c�̕�������u�����ς��A���c��������N�����A�܂��V���Ȍ��c���A�Ƃ��������������̂�������ŋ��̓����ł���B���́A������u��ڂ̒��ʼnQ������M�v�Ɗ����A�ނ���m��I�ł���B���{�̋ߑ㌀�A������u�V���v�̌��c�Ƃė����W�U�̌J��Ԃ����o�Ă���ɂ��܂ŗ����̂��B������ŋ����\�����Ă���Ⴂ�l�X�������A�����ȂƂ���Ŕ[�܂肫���Ă��܂��悤�ł͂ނ��덢��B�����Ŗ��C���N�����A�������A�R���邱�Ƃ͑傢�Ɍ��\���B�������A���ꂪ���W�ɂȂ���̂ł���A�Ƃ������ߕt���ł͂��邪�B���ɂ͏�����ŋ��̂܂܌ł܂��Ă��܂��A�s���l���Ă��܂��Ƃ���������B�ŋ��ɑ����M�̌͊��Ɖ䖝�̌��E�A�ł��낤���B
�@���݁A�����E�ő傫�Ȑl�C���ւ�A���ڂ��W�߂Ă�����҂ɂ�������ŋ��o�g�҂͑����B���������l�X���A���̈炿�������Ă������҂����Ƃ͕ʂɑ��݂��A��������̂͑傢�Ɍ��\�Ȃ��Ƃ��B
�@�����A��ԍ���̂́A������ŋ��Ƀv���ӎ������@���Ă���P�[�X�����ɑ������Ƃ��B���c�𗧂��グ������̍��͗F�l�m�l���ĂяW�߁A�ŋ��������邩��d��������܂��B�������A����ƂĂ����炩�̓��ꗿ���ė��Ă����̂��B���̈ӎ����x���Ŏ~�܂��Ă��܂��ƁA���������̐����͂Ȃ��B���Ƃ�1000�~�ł��낤�����ꗿ�����ȏ�A1200�~���x�̎ŋ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂͗L�������A����̑召���킸�A���҂𖼏����̂̐ӔC���B���ꂪ�A�g����F�l�Ɉ͂܂�āu�ǂ�������v�u������Ăˁv�ƌ����Ă����C�����ɂȂ��Ă��邾���ł́A����ŏI��肾�B�����ɁA������ŋ��̃A�L���X�F������B
�@�����Ƃ��A�v���ӎ��Ƃ����_�Ō����A�匀�ꉉ���Ƃčŋ߂͂��̌��@������������Ȃ����ł���B���ɃV���v���Ȑ}���Ō����A�u���D�v�ƌĂ��l�X�͂������ƂȂ����D�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��A�l�̌����Ȃ��Ƃ���œw�͂��d�ˁA�������A�O��I�Ȏ��ȊǗ����s�������ʂȂ̂��B�D�ꂽ�v���X�|�[�c�I��Ɠ��������ł���B�ŋ��Ƃ������̂��A�����̓��̂ŕ\��������̂ł���ȏ�A���̓��̂Ɛ��_�������ɍ������`�x�[�V�����ɒu���Ă����邩�A���ꂪ�v���ӎ����B�匀��̎ŋ��ŁA�������J���ĉ������o�̂ɂ܂��Ȕ��������Ɋo����ꂸ�Ƀv�����v�^�[�ɗ����Ă�����҂�����B���o�Ƃ͖�����ŁA�m�Ï�ɂ낭�Ɋ���������ɂقƂ�ǂ����o��⏕��ɔC���Ă��܂��l������B������ŋ��ɂ́u�M�Ӂv�����邾���ǂ��̂����m��ʂ��A���ꂪ���肷��Ǝ��Ȗ����ŏI���B���̕ӂ�̂��߂�����������̂��B
�@��܂��ɂ��̐E���𗝉����Ă͂��Ă��A�{����`�Â�����v���f���[�T�[�̖����͂Ȃ��Ȃ��������ɂ������̂�����B�{���ł���A�㉉���ڂ̑I��Ɏn�܂�A�r�{�Ƃ��K�v�ł�����̑I�C�A�L���X�e�B���O�A���o�Ƃ̈˗��ȂǂȂǁA�싅�Ō����Α��ēł���B���̑�g�����߂Č�͐�`���Ƃ������S���Ɏd����U�蕪����B�������A���̋��s�̑S�ӔC���ׂ�����̓v���f���[�T�[�ł���B������Ȃ��g�����f�B�h���}�ɏo�Ă���悤�ȃ`�����`���������l�Ԃɋ܂�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���҂̉䂪�܂܂ɐU��ꂽ�肹���ɁA�S�����������Ă���v���f���[�T�[�̑��݂͕K�v���B�������A���̃v���f���[�T�[�Ƃ����l�X�A���Ȃ��Ȃ���Ԃɂ���l�������̂��m���Ȃ̂��B
�@��Ԗ��Ȃ̂́A�u�������Ă��Ȃ��v���Ƃ��B�u�Z�����̂Łv�ȂǂƂ�������������͎����Ȃ��B�Z�����̂����ŁA�ŋ��ɖZ�E���ꂽ���Ȃ���Ύ��߂���������̂��Ƃ��B�v���f���[�T�[�̕��Ƃ́A�ꌾ�Ō����u�ŋ���m��v���Ƃ��B�����āA���̏�ɗ����āA�ڐ�̃v���X�}�C�i�X�����ɂƂ����̂ł͂Ȃ��A���{�̍���̉����̂������~�����čl������悤�Ȑl�ނ����A�ꗬ�̃v���f���[�T�[�ł��낤�B�o�Ԃ��������Ȃ��́A�Ɏn�܂�A���Ԃ������Ă���悤�Ȗ��҂⎖�����A���o�����Ă�������Ă��Ȃ����킩��Ȃ��悤�ȉ��o�Ƃɑ��A�͂����蕨�������ɂ́A���ꂾ���ŋ��̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�啨�ɑ��āu����͈Ⴂ�܂��v�ƌ����邾���̌��������邩�ǂ����A���B���ꂪ�Ȃ�����A���ׂāu���C�����܂��v�Ƃ�����ԂɂȂ�B���C�����ꂽ���͎��������₷���悤�ɂ��Ɍ��܂��Ă���B���̎��_�ŁA�u�ϋq�v�Ƃ������t��ӎ��̓v���f���[�T�[�̓��̒�����͌������Ă���B�u�����A���ߎ��Ɋ������܂ꂸ�ɂ��v�Ƃ������x�����m��Ȃ��B
����Ӗ��ł́A��Ƃ̌��e�̍ŏ��̓ǎ҂��ҏW�҂ł���悤�ɁA�ϋq���\�����u��v�������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��B���̏�ŁA���s�Ƃ��Đ��藧���ǂ����̔��f�͂����߂���B�ǂ���̑��Ɍ}�����Ă������Ȃ��̂��B�u������Y�펖�������Ă��v�ƌ����邾�낤���A�������Y�펖�ł͂Ȃ��B���̋��Ԃɗ����āA�������͂���A���Ƃ��ǂ����������ɂ͒m��������ΐM�p���K�v�Ȃ̂��B���̒��ŁA�͂ɂȂт��������Ԃ���Ȃ��u�����v�������Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ȑ�ςȎd���͂Ȃ��B�m�����̊Ŕɂ��܂���Ă͂����Ȃ��B
�@�����̕�����ςĂ���ƁA�u������́v���]��ɂ������B���悪����̂��́A����̖ڐ��ς������́A�����z���̉₩���ł��܂������Ƃ��Ă���P�[�X�����X������B�������̕��@�ł���A���������ɂ���̂������Ƃ͌���Ȃ��B���Ĉꐢ���r�����u�x���T�C���̂�v�͖��悪����ł���A���ɂ��]�����ׂ�����͂���B�������A�����������łɕ]���̓���ꂽ���̂����ɗ����Ă��܂��A�V���ȍ�Ƃ̈琬��r�{��ǂޓw�͂����Ȃ��v���f���[�T�[�������̂������Ȃ̂��B�l����Ă邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B����͏��m�̏ゾ�B�������A��������Ă����Ȃ��ẮA���W�͂Ȃ��̂��B������A�u�D�L���v�d�����A�ƌ����̂��B���̓D�L���������͂����ē�������̂Ȃ����Ƃ�������Ă���ƁA�����̙\�͂����������ł͂Ȃ��A�ϋq�̊ӏ܊��ቺ�����錴���ɂ��Ȃ�B�Ⴂ���x���̂��̂Ŋϋq���������Ă��܂��A���҂͂���ȏ�̓w�͂͂��Ȃ��B���S�ȕ��̘A���������ŏo���オ��B���ꂪ��ԕ|���̂��B
�@���s�̋K�͂ɂ���邪�A���P�ʂ̂����������������s�̐��ۂ����߂�̂̓v���f���[�T�[�̌����ł���B���̘͐̂b�ɂȂ邪�A�ϋq�������Ďŋ����ς�ȏ�́A���������I�҂������B���āA���͉̕�����̎O�K�Ȃ���A������҂Ɂu�卪�I�v�Ƃ����������������̂������Ƃ�����B���A�����������Ƃ�������q�Ȃ���܂ݏo�����̂��A�q�Ȃ����炯��̂��͂킩��Ȃ����A�ϋq�����҂���āA���҂��ϋq����Ă�悤�Ȏŋ���n��̂��v���f���[�T�[�̖�ڂł�����B�u��y�Ŏŋ����ςɏo������̂ɁA���������܂ł̑z���͂��Ȃ��Ă������v�u���܂ɂ̂��Ƃ�����A�y���������ł����̂��v�Ƃ����ӌ��������Ƃ����B�������A���̃��x�������炩�ɉ������Ă��邱�Ƃ͔ے�̂��悤���Ȃ��̂��B
�����Ƃ��A����ɂ͂������̗v�f�����ݍ����Ă���A����I�Ƀv���f���[�T�[�����f�߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ǂ��ł������悤�ȁA���Ԓׂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ԑg�����X�ƕ������A���̓łɔ]����N����Ă��܂����ϋq�͋C�̓łȂ��̂��B�����Ƃ��A�����Ńe���r�_��_���Ă���ɂ͂Ȃ����A���͂��̔C�ł͂Ȃ����A�e���r�̑��͒N���������Ȃ��炸�����Ă��邱�Ƃ��낤�B�ǂ������Ό�y�̑��l���A���������Α��l���ɂ��X�̎��̒ቺ�������I�ɗ��ݍ����āA����̎��̒ቺ�ɂȂ����Ă���̂��B�����ň�ԁA�������Ŏŋ��̐��E�𗧂Ē������Ƃ����v���f���[�T�[���ق������̂��B
�@�ǂ������u�{�v�A���������u����Ă��鎞�����̎g���̂āv�����͂�|�\�E�̏펯�ɂȂ����B�ŏ����炻���[�����Ă���܂������A��u�ׂ̖��̂��߂ɂ�����J��Ԃ��Ă��邩��A�l�ނ��炽�Ȃ��B�N�ł������䂩�疼�����ł��Ȃ��̂Ɠ������ƂŁA����ō����]���āA������������̃I�t�@�[���r��Ȃ��悤�Ȗ��҂ɂȂ�ɂ͑����̎��ԂƓw�͂��K�v�Ȃ̂��B�������A��]�҂����͂�����ł����邩��A�Ƃ������z�ŁA���g���Ă݂ă_���Ȃ�I���B�܂��A�g���̂Ăɂ��ꂽ�����u�Ȃɂ����A���̎������́v�Ƃ����e�C�Ȃǂ��炳��Ȃ�����A�o���G�e�B�ł����ł��Ƃ肠������炵�Ă���������A�Ƃ����b�ɂȂ�B�܂��A���̋t������ŁA�e���r�ŏ������ꂽ���玟�͕���i�o�A�ȂǂƋC�y�ɕ���֏オ���ė���B����Ȃ�̊o�傪����\��Ȃ����A������Ȃ߂Ă͕���l�Ɏ��炾���A�ϋq�͋C�̓ł��B���A�����̊Ԃ܂Ńe���r�ő����ł�����҂�����ɏo�邩��ƌ����āA����ɑ喇���͂����Č���֑����^�ԂقNJϋq�͗D�����͂Ȃ��B
�@��قǁA�v���f���[�T�[�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����������A�����l�Ȃ����͂���ȏ�ɖ��҂������Ȃ��B�匀��̎ŋ��ł́A�����̏o�Ԃ��I���Ǝŋ����Ō�܂Ŋς邱�Ƃ������ɁA�������ƈ��݂ɍs���Ă��܂��y������B����ɂ��鎞�Ԃ������Ă��c�Ƒオ���Ȃ��A�ƍl���Ăł�����̂��낤���B���������ɕς��ŋ��S�̂�c������w�͂����Ȃ��ŁA�����̏�ʂ����ł���������Ă��āA�ŋ����I���Ȃ�킯���Ȃ��B����ł悵�Ǝv���Ă���{�l���A����������Ă��鎖�����ɂ��v���Ƃ��Ăْ̋��������@���Ă���̂��B�펯������A�u��y�����̕�������̋@��ɂ݂���������āA���̋@��ɔ�����v�Ƃ����}�l�[�W���[�����Ă����͂����B���Ɏd���̃X�P�W���[���������Ă���̂Ȃ�Ƃ������A�܂������܂�Ȃ������Ɍ������ɂ���ȂǁA���ꓹ�f���r�������B
�@�����ǂ�Ȃɔ��B���悤���A���D�����Ȃł͏o���オ��Ȃ����Ƃ����͕ۏႷ��B�l�����Ă��Ȃ��Ƃ���Ō����Ɍ����Ȃ���J�����A�����ŋ������܂��Ȃ邱�Ƃ�ړI�Ɉ���������ė����u���Ҕn���v�̎ŋ������炱���A�ϋq�̋������ł̂��B����ȒP���Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��A���̉��Ƒ������Ƃ��B���������l�͕���ɏo��K�v�͂Ȃ��B�����Ƃ��A���ґS�������D�ɂȂ��Ă�����͂܂�����킯�ŁA�卪���҂����邩�炱�����D�̍I�����ۗ��̂ł���B�������A�ŋ߂͑卪�܂Ő������Ȃ������ɂ��낵�Ă��܂�����g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�B����̃T�C�N���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ͒N�ɂ��ے�̂��悤���Ȃ��b�ŁA���̒��ō��܂ł̎O���̈�̃X�s�[�h�Ŏŋ������܂��Ȃ肽����A�l�̎O�{��������������̂��ƂȂ̂��B�������ăV���v���Ȑ}���ł���B
�@�����������Ƃ���ɂȂ炸�ɂł���l�A����Γ��̔z�������ʂ̐l�Ƃ͏�������Ă���l���������D�̏����������Ă���̂��B�N�ł�����Ȃ��͍I�������ǂ��Ɍ��܂��Ă���B���炩���ߌ��ʂ�\�����Ă��܂��A�w�͂��������̂͗_�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B�������A�������ǂ��܂Ŏŋ��ɂ̂߂肱�ނ��Ƃ��ł��邩���A��x�q�ϓI�ɒ��߂Ă݂�K�v�͂��邾�낤�B���ꂳ�����o�����ɕ���ɗ����Ă���l�X�̉��Ƒ������Ƃ�B����͂���Ӗ��ł͈��������Ƃł�����̂��B����������Ă����l�����Ȃ��B�C�Â������Ȃ��B���̂܂܃_���_���ƍ�������čs�������Ȃ��̂��B�C�̓łƌ����C�̓łł͂���B
�@�ꌩ�₩�ȃX�|�b�g���C�g�𗁂сA�l�C�̒��S�ɂ���悤�Ɍ�������҂Ƃ��������́A�E�ƂƂ��čl�����������̍������̂ł͂Ȃ��A�Ǝ��͎v���B�{���ł���A��ЂƂ̍�i�ŋꂵ�݁A�Y�݁A�����Ǝ����̒��̒��l�𑝂₵�Ă����A��Ԃ̂�����C�̉����Ȃ�悤�Ȏd���Ȃ̂��B�����ɋC�������ǂ����A�C�����Ă����H�ł��邩�ǂ����A�����ɖ��D�ɂȂ�邩�ǂ����̊�H������B
�@�ꎞ���s�����{�̃^�C�g���ł͂Ȃ��B���̃`�P�b�g�̗��ʃV�X�e�������ɕ֗��ɂȂ�������ŁA���s�T�C�h�͐�s�\�̉����̂Ə̂��āA�O����Ő��肽�āA�Ƃɂ����`�P�b�g����Ă��܂����Ƃ���B���̃T�C�N�����̂��������Ȃ����B���s�T�C�h�ɂ���A���O�ɔ���o���������A�ꃖ���ԗl�q�����āA����s���������������CM��łȂǂ̂Ă���������鎞�Ԃ̗]�T�����邩�炾�B�����ɁA�������ɂ��Ă݂Ă��A�u��s�\��v�u�D��\��v�ŁA�����l�i�ŏ����ł������Ȃ���ɓ���̂ł���A�Ƃ����S���ŁA�u��������v�����Ă��܂��P�[�X�����X����B����قǍs�������킯�ł��Ȃ�����ǁc�Ƃ�����Ԃł��A��������Đ�����A�Q�Ă�̂͐l�Ԃ̐S�����B�������x����āu�����Ă͂����Ȃ��v�̂��B���Ⴀ�A�����������B�����J���A�m�荇���̊��z�ł������āA�������ς����A�Ǝv�������Ɋς�悢�̂��B���̎��ɂ̓`�P�b�g���Ȃ��悤�Ȑl�C�����ł���A�߂������Ƀe���r�ŕ������邾�낤�B�ŋ��Ɋւ��d�������Ă���̂ł���Ƃ������A�ŋ���{���������Ƃ���Ől�����傫���ς��킯���Ȃ��B��������A�����Ȃ���ÂȊ��o�������Ƃ��A�Љ���ł͂�قǏd�v���B
�@���̕i�X�ƈ���āA�ŋ��̃`�P�b�g�͈�ԕԋ��ɉ����Ȃ��O���[�v�ɓ����Ă���ƌ����Ă��ǂ��B�o���҂��ύX�ɂȂ낤���V�Ђ��N���悤���A��قǂ̂��ƂłȂ���Εԕi�ɂ͉����Ȃ��B�̔����Ƃ��Ă���قǂ܂łɍ��p���ȏ��i�͑��ɗނ����Ȃ����낤�B�`�P�b�g�����Łu�������Ă��܂��ƁA�L�����Z���E�ύX�͂ł��܂���̂Łv�Ǝ����̂悤�ɌJ��Ԃ���錾�t���Ă���ƁA�����s����~�����Ă��邱�Ƃ�����B�����������Ɍ����āA�\���͓I������B���낵�����Ƃ��B
�@���ꂩ����{�̌o�ς͂���ɔ敾���邾�낤�B����Ȍ����������̒��A�������������J�肵�A�S�̃I�A�V�X�����߂Č���֒ʂ��̂ɁA�����܂�Ȃ���A�ł͖����ւ̊��͂���C�Ɏ����Ă��܂��B���͂����ł͂Ȃ��A�`�P�b�g����ƌ�ʔ�A�ꍇ�ɂ���Ă͐H����܂Ŏ����Ă���̂��B����ł͖ڂ����Ă��Ȃ��B�ϋq������ȑz�������Ă��Ă��A���R�Ƃ�����Ȃ��ŋ��𑱂���l�X������A���̐l�̃M�������e�B�͕ۏႳ��Ă���̂��B����͂������Șb�ł͂Ȃ����B���͋��s�t�ł͂Ȃ����A�ŋ��̃M�������o�������ɂ���A�݂�Ȃ������ɂ����ŋ��ɂ��悤�Ƃ��邾�낤�B�ꃖ���̌������I����Ă��܂��A���g�݂����U���A����ł��ׂĂ����Z�b�g����Ă��܂��d�g�݂ɂ���肪����̂��B���s�����ꍇ�ɂ��̌��������A���ւ̔��ȂƂ���̂͂ǂ�Ȏd���ł�������O�̂��Ƃ��B��������Ȃ��Ă�������Ă��܂������邱�Ƃ͂����Ȃ��B
�@���̈���ŁA�����s�́u�i���v�Ō����A�ꏊ�����ɃR�c�R�c�ƒn���ȓw�͂��d�˂Ă��Ă����ꂸ�A���̓�����Ȃ��l���吨����̂���肾�B�֎q���Q�[���̈֎q�̐��������Ă��邩��A��U�֎q����ɂ����l�͉��������Ă������Ȃ��B�������ɂ��邾���̗͗ʂ������Ă���l�������Ă��镪�ɂ͍\��Ȃ����A�����ł͂Ȃ��l����������B�������A�ϋq�s�݂Ȃ̂��B
�@��x�ł������A�ϋq���{���ɃV�r�A�Ȋ�Œ��߁A�ʔ����Ȃ��ŋ��́u�s���^���v������悢�B�K���K���ȋq�Ȃ���ɂ����v���f���[�T�[����҂����ɂ́A���ꂪ��Ԍ����ڂ̂����ɂȂ邾�낤�B�̂̋��s�t�͂��������ڂɑ����ė����B���łƂ����ƌꊴ�������Ȃ邪�A���s�͐����ł���B���s����Γ��R�呹������킯�ŁA�N�����̕ۏ�͂��Ă͂���Ȃ��B�����Ȃ�Ȃ����߂ɁA��������������S�߂ȑz�������Ɋ������A�K���ōl�����̂��B���́A�ǂ�����������Ƒ̂Ƃ��Ă̕ۏႪ���邽�߁A���������v���f���[�T�[���u�T�����[�}���v�ɉ߂��Ȃ��B�{�[�i�X�̍���ɑ����̉e�����o�邮�炢�ŁA�����̐����������Ɋ낤���Ȃ�A�Ƃ������Ƃ��Ȃ���A�ŋ���ł��߂Ɏ؋�������K�v���Ȃ��B����Ȓ��A��C�T�Ŏ������u�����v�Ǝv���ŋ���ł��߂����Ɏ��������\���A�����Ńv���f���[�X�����Ďŋ���ł��Ă���v���f���[�T�[������B�������A�����猾���Έ��|�I�ɏ��Ȃ����낤�B���s��Ђ́A�ϋq���������Ă��A�������������Ȃ��d�g�݂͂�����Ƃł��Ă���̂��B���̃c�P�́A�ϋq�������Ă���B���̌������ƂƓ����d�g�݂��B
�@���̐Ԏ��`�[����Ȃ����߂ɂ��A�u�s���^���v�����Ă��ǂ��̂��B�����̕������ŁA��������ł����������10�~�オ���Ă��呛���ɂȂ邵�A���̐ςݏd�˂͉�������B����Ȃ̂ɁA12000�~�̃`�P�b�g�ɑ��ĕ���̈������Ȃ��̂́A�]��ɂ���g�ɉ߂��͂��Ȃ����낤���B
�@�����̕ϓ����l���Ă��A���͂����ƈ����l�i�ł����Ɨǎ��̎ŋ�����������ςĂ����B������A���̉����E�������䂭�Ďd�����Ȃ��B�݂�ȁA����Ăł��Ȃ��킯�͂Ȃ��̂��B��炸�ɂ���A��炸�ɂ��܂��Ă��邾���Ȃ̂��B������A�����҂��n��������B����́A���̎�����������Ƃ����m��Ȃ����A�D���������Əꍇ�ɂ����̂��B
�@�u�����ŋ����v�Ɣn���̈�o���̂悤�ɋ���ł��Ă��A���Ⴀ��̓I�ɂ͂ǂ��������̂��u�����ŋ��v�Ȃ̂��B���ۓI�Ȃ��Ƃ���������Ă��Ă��M�p�͂���܂��B
�@�����l����u�����ŋ��v�Ƃ́A�P�Ɂu�����v�Ƃ������t�ɂƂǂ܂邾���ł͂Ȃ��A�u�l�̐S�����ŋ��v�u�i������̂ɉߕs���̂Ȃ��ŋ��v���B�ŋ߂́A�e�[�}���Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���ŋ��������B�ʏ�A�ŋ��́u�l���������сv���́u�푈�͂����Ȃ��v���́A�����ɂȂ�ׂ��e�[�}������A��������ɓ��t�����Ȃ����B�������A�u�������������̂��������ς�킩��ʁv�܂܂Ɏŋ����i�s���A����ŏI�����̂�A�����������Ƃ��U�X������ꕷ�����ꂽ��ŁA���X�Ƒ������̂�����B�u�ߕs���v�Ƃ͂��̂��Ƃ��B
�@�S�����������c�{�͊ϋq�ɂ��Ⴄ���낤�B����͓��R�ł���B�Q�l�܂łɁA�������N9���̏��{�܂łɊς��ŋ��̒��ŁA�u�����v���邢�́u�����Ȃ��v�Ǝv�������̂��ȉ��ɋ����Ă����B
�@�E�u�t�������q�v�i�E�̕�����j
�@�E�u���錋���̕��i�v�i�O���E�x�j�T���E�s�b�g�j
�@�E�u����v�i�O���E�����|�p����j
�@�E�u�����l�v�i�O���E�̕��꒬FACE�j
�@�E�u�V�菼�ł�����v�i�l���E�A�g���G�t�H���e�[�k�j
�@�E�u��17�ߗ����e���v�i�܌��E�����O���[�u���j
�@�E�u�����h�E�~�[�E�A�E�e�i�[�v�i�Z���E�{������j
�@�E�u���̕����v�i�����E�X�e�[�W�~�j
�@�E�u�E�[�}���E�C���E�u���b�N�v�i�����E�p���R����j
�@�E�u�l�`�̉Ɓv�i�㌎�E�V�A�^�[�R�N�[���j�B1000�l����K�͂̌��ꂩ��A100�l�����̌��������B�������ŋ����A���ꂼ�ꂪ�u�����v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������A�ǂ����Ɂu�S���������́v���������B����͍�i�{�̂ł�������A���o�̎�@�ł�������A���҂̉��Z�ł�������A���܂��܂��B�ǂ�Ȏ��ۂɂ����Ă��A100���Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤����A���ꂼ������r���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B�����Ȃ镑������߂����C�����͂��邪�A���g�̐l�Ԃ������A���g�̐l�Ԃ��ς�̂��B���̎��_�ŁA100���͂Ȃ����낤�B����ł��A�����ɖ����������ŋ��͎��̒��ł́u���i�_�v��������ŋ����B
�@��{���̓��e�����ׂ��ɐ������Ă���]�T�͂Ȃ����A������̎ŋ��������~�肽���A���邢�͌��ꂩ��̋A�蓹�ɁA���ς��ŋ��ɑz�������������Ƃ����������̂��B�Ƃ͌����A����͂��Ȃ�u�Â߁v�̕]���ł���B�u���������v�u�������v�ƍׂ��Ȃ��Ƃ������炦�A���͂����ƌ���B��]�Ƃ̐E���́A�u�ق߂�v�u���Ȃ��v�����ł͂Ȃ��B�N�I���e�B���グ�邽�߂ɂ͉����K�v�Ȃ̂��A������q�ϓI�Ȋ�ŕ]�����A���邱�ƂȂ̂��B���̎��_�ɂ����āA�����Ɍ����Ȏ�����ۂ��Ƃ��ł���̂��B���ꂪ�A�ł������]�Ƃ̐S�\���ł���B
�@�u�i���Љ�v�Ƃ������t�����s��ɂȂ��Ă���B�����čD�܂������t�ł͂Ȃ��B�������A�ŋ��̃`�P�b�g��ɂ��傫�ȁu�i���v�����݂��Ă���B���ꂪ�A�N�I���e�B�ɂ������i���ł���܂����ɂ��Ȃ�Ȃ��̂����A�u����Ł��������~�I�v�Ƃ������e�̎ŋ��������͎̂������B
�@�f�p�ȋ^��ł���B�u�Ȃ��A�ŋ��̃`�P�b�g�͍����̂��낤���H�v
�@�Ə��������Ă�����A���c�l�G�����̕s���̐܂Ƀ`�P�b�g�����������A�Ƃ����j���[�X���������Ă����B�u����͂����ȒP�ɑ����^�ׂ���z�ł͂Ȃ��B�����炱�����̌����������ɒl���������āA�C�y�ɑ����^��ł������������v�Ƃ�����|�̂��̂ł���B�l�����z�̍��v�͑S���ꗿ�̂T�������̋��z�ɂȂ�ƌ����B���c�l�G�̏ꍇ�A�Ȃ̃N���X���ו�������Ă��邽�߂ɁA�l�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ����邪�A����ŕ������ł��l���������͎̂ŋ��t�@���ɂƂ��Ă͊������b���B
�c���̎l�G�̉^�c���@�Ɋւ��Ă͎^�ۗ��_������B�������A�o�c�҂̊�ō���̌��f���o�����̂́A�������������̏��Ŕ��f�������u�p�f�v���ƌ����Ă悢���낤�B���R�A���̂T���̂�������c�l�G�ɏ������Ă���X�^�b�t�ɒ��˕Ԃ�ł��낤���A���̕��̉c�Ɠw�͂��K�v�ɂȂ�B�������A�u�ׂ���Ƃ���ׂ͖��Ă����āA�Ԏ����o�Ă���肽���ŋ��A���ׂ��ŋ��͂��v�Ƃ����A���s�t�Ƃ��Ă̎p���͂���������B����̂Ȃ��悤�ɐ\���グ�邪�A�ǂ̎ŋ��������łǂ̎ŋ����Ԏ��������͒m��Ȃ��B�������������̂́A�{���̋��s�t�̎p���͏�ɏq�ׂ��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B
�ŏ�����Ԏ����o�����ƍl���Ďŋ�������l�͂��Ȃ��B�ƂȂ�A�r�W�l�X�ł���B�r�W�l�X�ł���ȏ�A���̃N�I���e�B�ƃv���C�X����v���Ă͂��߂Čڋq�̖�������B�`�̂���i���ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͕ԕi���������A�ŋ��̏ꍇ�͊ςĂ��܂�����Ɂu�܂�Ȃ������̂ł�����Ԃ��v�Ƃ����b�ɂ͂Ȃ�ɂ����B���������Ӗ��ł́A�ǂ̎ŋ����ꔭ�����ł���A�����J���Ă݂Ȃ��Ă͂킩��Ȃ��̂��B�����炢���ŋ��ł�����Ȃ����͓̂���Ȃ����A�u�Ȃ����̎ŋ����c�v�Ǝv���悤�Ȃ��̂Ɋϋq���E�������������B
���͑O����A�����匀�ꉉ���͕�����A���̕a���Ȃ�d���Ƃ������Ƃ�܂��邲�Ƃɏ����Ă������A����̌��c�l�G�́u�p�f�v�ɂ��A�����̌��ꂪ�e�����邾�낤�B����ŗǂ��̂��B���̉e���ɂ��A����̌o�c�҂�v���f���[�T�[���{�C�ɂȂ�A�����̌���̎ŋ��̃`�P�b�g������K�����i�ł��邩�ǂ������q�ϓI�ɔ��f��������B���̌i�C����̎���������̂ɁA�u���i�v�����čl����킯�ɂ͂����܂��B
�ɒ[�Șb������A���ꂪ�ׂ�Ă��A�����ׂ͒�Ȃ��B�����ƂȂ�A�]�˂̐̂ɖ߂��đ哹�Ō|���I����Ηǂ������̂��Ƃ��B�����܂ł̊o�傪�����E�S�̂ɂ��邩�ǂ����B���ꂪ�ׂ�Ă��܂��A��]�ƂȂǂ���Ȃ��B�����������܂ł��������āA�݂�Ȃ����𐘂��鎞�������̉����E�Ȃ̂��B�����1000�l���錀���80�l�̌���ł͌o�c���j���Ⴆ�A���̌����ň������z�������Ⴄ�B�����������̂��������傭���ɂ��đ哯�c������A�Ƃ܂ł͌���Ȃ����A���̊�@�����邽�߂ɁA�u�l����v�Ƃ������Ƃ͕K�v���B�v�����d�˂Ȃ��ẮA�V�������͎̂Y�܂�Ă͗��Ȃ��B���l�C�̂���l�ɗ����Ă�����A���̏ꂵ�̂��ŋ��s�𑱂��Ă��邾���ł́A�����c��Ȃ�����Ȃ̂��B�`�P�b�g����̒��ɂ͑����̗v�f���܂܂�Ă���B���̒��g���ēx�ᖡ���A���̎���̉������l����ɂ́A���̕s�i�C�͂���Ӗ��ł̓`�����X�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@2009�N�̂P���ŁA���c�썶����u�x�j�T���E�s�b�g�v��������A�Ƃ����j���[�X������A�����t�@�������������B����̉Ǝ�ł����释�g�O�̖�肩��[���Ă���̂����A���܂�ɂ��ˑR�̂��ƂŁA�o�����[�����A���ӂ�����ł̕��ł͂Ȃ��B���͂ǂ��̌�����s�U�ɂ������ł��鎞�ゾ����A����̕��͂�ނȂ����������邪�A���̏ꍇ�͂��������������Ă���B�����������A��ƂƓX�q�̌������Ⴄ���Ƃɖ�肪����B�����E�̖��Ō����A������100�ȏ゠�錀��̒��̈�������邾�����A�Ƃ������������낤���A���Ƃ͂����P���ł͂Ȃ��B
�u�x�j�T���E�s�b�g�v�����_�ɐ��슈���𑱂��Ă���T.P.T���A�����ȗ������E�ɗ^�����e���͑傫���B����������킯�ɂ͍s���Ȃ��̂��B���ł����A�f���B�b�h�E�����H�[�̖��͉����t�@���ɂ͐Z�����Ă��邪�A�ނ��ŏ��ɓ��{�̋��_�Ƃ����̂͂��̌���ł���B�����ŁA���낢��Ȏ��݂��s�������Ƃ�������A�����]�������Ƃ͑����̐l���m���Ă���B�ꎞ�́A���҂̊ԂŁu�����H�[�̉��o�̎ŋ��Ȃ�A�ʍs�l�ł��o���������v�Ƃ����قǂɎh����^�������o�ƂȂ̂��B�����������Ƃ́A���т̑傫�Ȍ���ł͐�ɂł��Ȃ��B�u�����I�����v�Ƃ������t���g���ƁA�����킯�̂킩��Ȃ��ŋ������Ă���悤�Ō�����������������A�V�������݁A���Ƃ����Ă̖���̐�����V���߂ȂǂŁA�����Ԃ��̘b�����ł���B�b��ɂȂ��������ł͂Ȃ��A�ǎ��̕���݂����Ă����̂��������B
��������́u�x�j�T���E�s�b�g�v�̕��̖��ɂ��ĕq���ɔ���������̂́A��N�A��������W�c�́u�n�l��v���������~�������Ƃ��傫���W���Ă���B�u�n�l��v�͎����̌���������Ȃ�����W�c�ŁA�V�h�̋I�ɍ����z�[����T�U���V�A�^�[�A�n���̉����ӏ܉�Ȃǂ𒆐S�Ɋ����𑱂��Ă����B��ɂ̖ؑ�����͕��w���o�g�̉��o�Ƃł���A��͂���{�̌��㉉���ɂ��낢��ȉe����^������l�ł���B�����H�[�Ƃ͊���ė��v�z�͈Ⴄ�����m��Ȃ����A�u������i���㉉�������v�Ƃ������{�͕ς��Ȃ��B���ꂪ�A�u�����E�̗ǐS�v���A�Ǝ��͎v���B���̓��̈�ł������u�n�l��v���������~���A���܂�T.P.T�����O�̓��̏�Ԃɂ��炳��Ă���B�厑�{�ł͂Ȃ������ɁA���K�ʂł̖��͑傫���B�������A���ꂾ���ł��ޘb�ł��Ȃ����낤�B
���́A�����ꂾ�������Ƃ����ۛ��ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B���������匀��Ə�����ł͂��̖������Ⴄ�̂��B�u�x�j�T���E�s�b�g�v�Ŗk���O�Y�̌������ł��Ȃ�����ɁA�������Ń����H�[�����o����u�����߁v��u�o���̘h�v�͏㉉�ł��Ȃ��B�������������̖��Ȃ̂ł���B������A���{��`�ɂ����铑���Ȃ̂��A�ƌ������Ă��܂��Θb�͊ȒP�����A���ꂾ���œ��{�̕����̓��������Ă������Ƃ�������Ă��܂��Ă悢���̂��낤���B����́A���܂�ɂ����\�Șb���B
�n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ắu����v�������邱�Ƃ��������Ȃ̂ł͂Ȃ��B����ɂ���āA�����ɂ������u�����v�̈�������Ă��܂����Ƃ����Ȃ̂��B�i�n�ɑ��Y�͌������B�u�}�W�����e�B�ɂ͕��������Ȃ��B�}�C�m���e�B�ɂ͂т����蕶�����l�܂��Ă���v�ƁB���{�̕����́u�I�^�N�v�ɂ���Č`������Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���ꂾ���A�������ו������i��ł���̂��B�����ŁA�}�C�m���e�B������ƌ����āA�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������킩���Ăق����̂��B
�@���낢��ȋǖʂŎŋ��̐���҂ɉ�ƁA�u�����r�{�͂Ȃ��ł����˂��v�Ƃ����b���B�����E�ł͂����A�r�{��T���Ă���B�ŋ߂̌X���Ƃ��ẮA�Â��r�{��|��A���邢�͉��o���Ȃ����ď㉉����P�[�X�������B�{��肦�ƒ�^�ꂪ�������u�l�`�̉Ɓv��130�N���O�̃m���E�F�[�̍�ƁE�C�v�Z���̋r�{�ł���A�V�A�^�[�N���G�ŏ㉉���Ă����u�������v��70�N���O�̋r�{���B��������A�ĉ�����鉿�l�̂��閼��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�ߋ��̍�i�̒��ŗ��j�̒J�Ԃɂ�������Ă��܂������ȍ�i������Ă��̉��l�𐢂ɖ₤���Ƃ͕K�v�ȍs�ׂ��B
�@���̈���ŁA20�N�ȏ���O����u�V��̕���v�����ɂ���Ă���B�����Ɍ����A�u�ĉ��ɑς�����V��v���B�V��͂�������o�邪�A������̏㉉�ŏI���ɂ���Ă��܂��P�[�X���ŋ߂͈��|�I�ɑ����B���̌����͂��������邪�A���ꂪ���G�ɗ��ݍ����Ă��邱�Ƃɖ�肪����B
�@��ԑ傫�Ȗ��́A����Ƃ��E�ƂƂ��Đ������ɂ����A�����b���u�H���Ȃ��v�Ƃ�����肾�B��{�̋r�{�������ɂ́A�����̘J�͂�v����B�r�{��{�ɑ��Ăǂꂾ���̑Ή����x�����Ă���̂��A�ڍׂ͒m��Ȃ������Ȃ��Ƃ������āu�����v�Ƃ����b�͕����Ȃ��B�܂��A�Y�Ȃ�{�ɂ��ďo�ł��Ă��A����Ȃ��B�Y�Ȃ�ǂށA�Ƃ����K�����A���̓Ǐ��l�ɂ͏��Ȃ��Ȃ������炾�B���������̂����_�炩���{����ǂ�ł��邩��A�ǂ����Ă��Y�Ȃ�ǂ�œ��̒��ł̃C�}�W�l�[�V�������ʓ|�ɂȂ�B����Ƃ̎������r�{�ɂ��̑啔�����߂�ƂȂ�ƁA�ĉ����d�˂Ă����Ȃ��Ɛ����ł��Ȃ��B�������́A�������Ɉ�{�̃y�[�X�ŐV��������čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̎��_�ŁA����Ƃ͏��Ղ��Ă��܂��B
�@�܂��A���̉����l�������r�{�ɏd����u���Ȃ��Ȃ����Ƃ�������̗��ꂪ����B30�N�O�܂ł́A�����̏������r�{�̉Ȕ����ꌾ�ς��������ł��㉉�͂����Ȃ��A���̂��炢�̃v���C�h�Ǝ��M�������ċr�{�������Ă����B���ꂾ�����ꂪ���������̂ł���B�������A���̌���Ƃɂ͂���͌����Ȃ��B�X�^�[�V�X�e���̒��ŁA������A���邢�͐���T�C�h���u�����Ăق����v�ƌ����ꍇ�ɁA����������ς�f��Ȃ��ɂȂ��Ă���B�ŋ���ǂ����邽�߂̉��ǂł���Α��k�ɂ���낤���A�P�Ȃ�d����̖��ŋr�{��������ꂽ�̂ł́A����Ƃ̑��݈Ӌ`�͋ɒ[�ɉ��l��������B
�@�����Ȃ��������́A���܂łɈ��̌����������Ă���ł����A�Ƃ��������̒��Ō���Ƃ������U�炵�Ă������ʂ�����B�̂̂悤�ɗI���Ȏ���ł͂Ȃ�����A�N�ɓ�{�̋r�{�������A���ꂪ���������ōĉ�����ĕ�点�鎞��ł͂Ȃ��B������Ԃ��A�l�^���d�����Ԃ��Ȃ��A�����玟�ւƋr�{���������ƂɂȂ�B����Ȃ��Ƃ��N�����Ă���A���������̃p�^�[�����甲���o���Ȃ��Ȃ�A���̂܂g���̂ĂɂȂ�B
�@�����������̃X�p�C�����������A���E���������̂悤�ȏŋr�{�����ꂵ�Ă���̂��B���{�l�̈������K���̈���Ǝ��͍l���Ă��邪�A�ڂɌ����Ȃ��m���ɑ��āA�h�ӂ͕������̂́A�����͕��������Ȃ��A�Ƃ������o������B�܂��A���m�ȍ����Ȃ��ɁA�Y�Ȃ������������Ɍ�����X��������B���������P���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B���̏ꍇ�͕]�_�Ƃ����A�����ɂ��Ĕ��\����A���̔}�̂ɂ���ċK��̌��e�����x������B�������A�������e��d�b�Ŏ�ނ����Ɓu�ǂ������肪�Ƃ��������܂����v�ŏI���B�����ɂ��A�ے��I�Șb�ł͂Ȃ����낤���B
�@���������ẴC�P�����u�[���ł���B�l�ԁA�����̐l�X�͉������̂������������̂��D�ނ̂͂������R�̊���ł���A���ꂪ�j���ł���ς��͂Ȃ��B���Ȃǂ̔N��ɂȂ�ƁA���O���o�����Ȃ�������A�����悤�Ȋ�Ɍ����Ă��܂��č��邱�Ƃ����X���邪�A����͘V���̈��ł���ƍl���邱�Ƃɂ���B
�@���āA���̃C�P�����u�[�������A�ނ�̐l�C�ɂ���ĎႢ����������ɋl�߂����A�ŋ���������悷��̂͗ǂ����Ƃ��B�]�˂̐̂̉̕��ꂾ���āA�ږ��҂Ɏx�����A�M�����Ȃ��b�����A���҂����������C�̓�������o���ꂽ�ƌ����B������A���́A�C�P�����u�[����ے肷�����͂Ȃ��B�������A�u�[���͂����ɏI��肪����B�ϋq�͔��ɃV�r�A�Ȃ��̂��B�����ꕔ�̃t�@���́A�ΏۂƂ�����҂Ƌ��ɔN���d�˂Ă����y���݂����o�����A����͑S�̂̊������猾���Ώ��Ȃ����̂ŁA�����̊ϋq�͎���ƂƂ��Ɉڂ낤���̂ł���B���̑O����������蓥�܂��Ă���̂ł���Ή�������Ȃ����A�����ł��Ȃ������ȂƂ���ɖ�肪����B
�@�C�P�����̖��҂ƂĔN�͎��B���̈���ŁA�r�͂Ƃ��������������Ⴍ�ăJ�b�R�C�C���҂́A���X�Ɠo�ꂷ��B���̐V��ӂ̒��ŁA�����Ă��܂�Ȃ��悤�Ɂu�r�v���Ă����Ȃ��ƁA�C�P�����Ƃ����ǂ������Ƃ����ԂɎ̂Ă��鎞��Ȃ̂��B�ɒ[�Ȍ�����������A�|�\�E�ɂ����Ė��҂́u���Օi�v�ł���B�������A���Օi�ł��A���̕i���ɂȂ����͂���ł�����A�������Ɏc�邱�Ƃ��ł���B����Ă��鎞���͖Z�����A�{�l�����Ⴂ�������������A���̎����Ɏ����Ȃ�̃v���X�A���t�@��T���w�͂����邩�ǂ����������c������E����̂��B
�@�u�C�P�����v�Ƃ������_�ɂ����āA���̖��҂������łɕ��킪������B�u�����̓J�b�R�C�C����v�Ƒ卪���҂ł�������鎞��ł͂Ȃ��B�����Ƃ��A�卪�ɂȂ�܂łɏ����Ă��܂����҂������̂��������B���̐l�����L���ȗ���ɂ��镪�A��̐킢���L�����ƌ����A����͋t���B���̕��A���̓G�͋����B�o���N���ł�������A���قȃL�����N�^�[�ł�������A�̂̍I���ł������肷��B��������������������l�����ɁA�炾���ŏ��������Ă��Ă��A�������������͖̂����ł���B
�@���҂���Ă�̂͊ϋq�ł���A���s�҂ł��邪�A����ȑO�ɖ��Ҏ��g�����������ł��O�ɐi�����Ƃ����C�������Ȃ���A��肪�����牞�����Ă����̓˂�����ɂ��Ȃ�Ȃ��B���A�C�P�����Ƃ��Ă͂₳��Ă���l�X�₻�̎��͂��A���̌������������ǂ�قǔF�����A�^�ʖڂɗ������������Ƃ���̂��B��̏o���͂Ƃ������A�����|�l�͎��炪�u�ꔭ���v�Ƃ������݉��l�ł����Ȃ����Ƃ�ǂ����������������Ă���B�����ʂŌ����h���C�����A���������Ό���S���Ȃ��B�O����ꂽ��u����ł������v�Ƃ������x�̌|�l�������B�������A�C�P�����̃v���C�h�i����ł͂Ȃ����낤���j�A���̌������炵�Ă��A���������킯�ɂ͍s���Ȃ��B
�@�C�P�������������q�ϓI�ɑ����A�����̕�������^���ɍl���邱�Ƃ����Ȃ��ƁA����������Ƃ��ꂩ��̉����E�̋N���܂ɂȂ邩���m��Ȃ��v�f���s���̂܂܂ɏI���A���Ղ̃T�C�N���̒��ɓ����Ă��܂������ɂȂ�B�}�X�R�~���ُ�ɃC�P���������Ă͂₷�ӔC�̑傫�������邪�A�����Ŏ������ǂꂾ���q�ώ����A�����̖��҂Ƃ��Ă̕��������l���邱�Ƃ��ł���̂��B���ꂪ�A���̃C�P�����̑傫�ȁA���ً}�̉ۑ�ł���B���茸�炳��A�u���̐l�͍��H�v�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��B�u�[���͕|���B�Ⴆ�͓K�ł͂Ȃ������m��Ȃ����A���g�̂悤�Ȃ��̂ł���B���̑傫�Ȕg�����������ɁA�C�݂əz�R�Ɨ����Ă��邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����B���ꂪ�C�P�����̍���̍s�������Î����Ă���̂��B
�@�u�h���S���N�G�X�g�v�Ȃǂ�RPG�i���[���E�v���C���O�E�Q�[���j�ł́A�Q�[���̎�l���̌o���l������̃Q�[���̓W�J�ɑ傫���e����^����̂́A�V�o���̂�����ł���킩�邾�낤�B�G��|�����ƂɎ����̌o���l���オ��A��苭���G��|�����Ƃ��ł���B�������A�o���l�����߂�ɂ́A�����Ă������̏����ł͂Ȃ��B�����������J��Ԃ��Ȃ���A����Ɍo���l���オ���čs���A�����̓G��|�����Ƃ��ł���̂��B�܂��A�����������Ȃ��ăQ�[����i�߂čs�������قǁA�����Ă��鑊��������B�����|���Đi�߂邱�ƂɁA���������Q�[���̑�햡�̈������̂��낤�B
�@���̍\�}�́A�ŋ��̐��E�Ɏ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�ǂ�ȑ�X�^�[���A�ŏ��͌o���l�u�[���v����̃X�^�[�g�ł���B�s���Ƌ��|�ł����ς��A���̒��͐^�����ɂȂ�Ȃ���A������ށB�Ȕ����Ƃ�������A��y�Ɏ���ꂽ�肵�Ȃ���A�����̌o���l�����߂Ă�����Ƃ��B�u�G�v�Ƃ����������͓K�ł͂Ȃ����A���̓s�x����������������Ⴆ��i���Ⴄ�B�����������ŝ��܂�A�ꂵ���z�������āA�o����ςނ��ƂŎ����̘r���グ�čs���������@�͂Ȃ��̂��B
�@�Q�[���ł���ΉB��A�C�e�����̋ߓ��Ȃǂ����邾�낤���A�ŋ��̐��E�͂����͍s���Ȃ��B���ɖJ�߂��A���̑����̏ꍇ�͂��Ȃ���Ȃ���A�����œw�͂��Ă��������Ȃ��B���ɂ́A�����̂��������Ŕ���I�Ɍo���l���L�т�P�[�X�����邪�A����͂����H�Șb�ł����Ȃ��A������Ă���̂ł���A���ł������������܂��܂��ƌ������̂��B
�@�����A���̌o���l�Ƃ������́A�l�����ɂ���Ă͋Ȏ҂ł�����B������������ɏo�Ă������Ōo���l���オ��A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�������o�Ă��镑��ʼn����邩�A���ꂪ�����̐g�ɂ��Ă����̌o���l�Ȃ̂ł���B���������H�y�܂Ŗ��R�Ǝŋ������Ă����̂ł́A����ɏo�Ă��o�Ȃ��Ă��������Ƃ��B�u������薾���v�A�u������薾����v�̕���ɉ����̈Ӗ������߂Ȃ��̂ł���A�i����������Ȃ��B�܂����ꂪ�A�������̂Ȃ����̂����ɖ��҂͐h���B�������A���������z�����d�˂Ă��邤���ɁA�m�炸�m�炸�̂����Ɍo���l���オ���Ă䂭���̂��B
�@����͊ϋq�ɂƂ��Ă������邱�ƂŁA�ŋ����ς�Ίς�قǁA�ڂ��삦�ė���B�ŋ����ώn�߂����͉��̋^����������ɖ������A�������Ă������̂ɁA���������̕�����Ȃ����o���Ă���B�����Ƃ��낢��ȃe���g���[�̎ŋ���`���Ă݂����Ȃ�B�������Ċϋq������Ă����ȏ�A���҂������Ƃ��Ă���킯�ɂ͍s���Ȃ��B�������A�ϋq�͂������Č���֗���B���҂͌���Ŏŋ������Ă��������炤�̂��B���̊u����͌���Ȃ��傫���B
�@���҂ɂƂ��Čo���l���グ�邱�Ƃ́A����̐��𑽂����邱�Ƃ����ł͂Ȃ��B���̎ŋ����ς邱�Ƃ�A�W�������ɊW�Ȃ��{��ǂ�A���邢�͉f����ς��艹�y������A�u���҂̋��{�v�����߂邱�Ƃɂ��Ȃ���B���㌀�ɏo�āA���������̓��̒u�������킩��Ȃ��悤�ł͖��҂̋��{���Ȃ��A�ƌ����Ă��d��������܂��B�ǂ�Ȏd���ł����������A��y�͂��C�̂����y�ɑ��āu����������v�Ƃ������Ƃ�ɂ��܂Ȃ��B�������A�u�g�̂Ŋo����v�u����Ŋo����v�Ƃ�����y�����邪�A����ƂāA�w�K���@�������Ă���Ă���̂��B���̕����{�l�̂��߂ɂȂ邱�Ƃ��A�u�o���v�Œm���Ă��邩�炾�B
�@�ǂ��������@�����ɂ���A�o���l���グ�Ă����đ��͂Ȃ��B�������A�ȒP�ɂ͍s���Ȃ����Ƃ�m��ׂ����B
�@�ɂԂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��u�����v���u�[���̂������A�u�|�l�v�ɂȂ肽���A�Ƃ��������B�ǂ��łǂ��ԈႦ���̂��A�����|�l���|�l�ł���ƍl���Ă���l�������悤�ȋC������������B����Ȕn���Șb�͂Ȃ��B����ł́A�킴�킴���Ɂu�����v�Ƃ���Ӗ����Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@�ł́A�|�l�Ƃ͉����H�@�������ǂ���`���Ă��邩�͒m��Ȃ����A���͌|�\�Ɍg���A���炩�̌|���I���ċ��K�Ȃ蕨�i�Ă���l�͂��ׂČ|�l�ł���ƍl����B���̈Ӗ��Ō����A���҂͂��Ƃ��A����Ƃ���Ԃ��A���o�Ƃ��|�҂��݂Ȍ|�l���B�����A�ǂ����ŕ��͂������A���e�������������Ό|�l���B������u���ɏo���������A��`�������Ă��ꂽ��҂��A���̎p�����Ă����������B�u�z�[���֗��Ă���ׂ��ċ������炤����A�|�l�݂����ł��ˁv�ƁB�ނ̓��̒��ɂ͗���Ƃ̃C���[�W�ł��������̂����m��Ȃ��B���́A�ŋ��̘b�����ču�����������������B����ƂɎ����邩���m��Ȃ����A����́A�[�I�ȕ\�����Ǝ��͎v���B
�@�������̊��o�����m��Ȃ����A�u�|�p�Ɓv�ƌ����Ɖ������h�Ȏd��������悤�����u�|�l�v�ƌ����ƈ�i�Ⴍ����ꂪ���ȃC���[�W������B���e���r�ɏo�Ă��邨���|�l�̑����́A�ƂĂ��|�l�ȂǂƂ͂������܂����A������ŁA���̂悤�Ȃւ��Ȃ���͌|�p�Ƃ����|�l���D�����B���A�E�l�����Ă͂₳��Ă��邪�A�E�l�Ƃē������ƂŁA��H�����z�ƂƂ͖���肽���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B��H�͑�H�A�����͍����ƁA���̐E�������܂��Ă���B���̒��ł����ɂ����d�������邩���|�l��E�l�̃v���C�h���Ǝv���B
�@�u��|�ɏG�ł�v�Ƃ�����������B�����͈Ղ��s���͓�ŁA�����ȒP�ɏG�ł邱�Ƃ��ł�����̂ł͂Ȃ��B��������ꂸ�Ɍ����A��l�Ƃ̋��E���ݏo���Ă��܂��قǂɂ̂߂肱���łȂ��ẮA��|�ɏG�ł邱�ƂȂǂȂ����낤�B�ǂ�Ȍ|�ł��A���̓����ɂ߂�͖̂������ł���B�ꐶ�̑唼��R�Ă��s�����Ă��A�ɂ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂��B�����炱���A�����̎҂��������Ƃ��Ă���B�ȒP�Ɂu�|�l�ɂȂ肽���v�Ƃ����l�X�́A���̌��t�̖{���̈Ӗ������Ⴆ�Ă���P�[�X�����|�I�ɑ����B�����ʔ������Ƃł������ăe���r�ɏo����ꂪ�|�l���A�Ɖ��߂��Ă���̂��낤�B����͊��S�Ƀe���r�̐ӔC���B�u�u�Ԍ|�v���́u�ꔭ�|�v���̂𗐔����Ă��邪�A�����������̂́A�ɘ_������Ό|�̂����ł͂Ȃ��B�{���̌|�l�ɑ��Ď���ł���B�O���Ŏ��鎑�i�ɂ͎O�����x�̌��\�����Ȃ��̂Ɠ����悤�Ȃ��̂ŁA���Ǝ��i�̂Ȃ��|�l�����炱������̂��B��̂��A�|�l�Ƃ������͖̂{���̌|�̋��낵����m���Ă��邩��|�ɑ��Ă͔��Ɍ����ł���A���炪�u���͌|�l�ł��v�ȂǂƖ���邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�̂̐l�͂��܂����Ƃ����������̂��B�u�|�͐g�������v�ƁB�G�ł�܂łɂ͂Ȃ炸�Ƃ��A�����̌|��g�ɕt���Ă���A�Ƃ肠�����H���ɂ͍���Ȃ�����̘b���B�����Ƃ��A���̌��̎���w�i�ɂ���|�́A���S����Ȃǂ̉��Ȃł��邱�Ƃ������B���邢�͏������w�₩�B������ɂ��Ă��A�l�l���炨�������������ċ�����̂ł���A�����Ȃ��Ƃł͂ł��Ȃ��B���y�Ŏn�߂������ł��A���ꂪ�u�|�v�ɂȂ�܂łɂ͑�ςȂ����Ǝ��Ԃ�v������̂Ȃ̂��B�Q�]�����Ă��Đg�ɕt���̂͗]�v�Ȏ��b���炢�̂��̂��B
���̉�͌��������o�Ă��邪�A�Ō�ɂƂǂ߂̈ꔭ�B�u�|���g��������قǂ̐�܂����v�B���́A�����������t�ɂ��������K�v�Ȏ���ɂȂ��Ă��܂����B�N������������̂��B
�@��́A�S���ɂǂ�قǂ̐��̌��ꂪ����̂��낤���B�傫�Ȃ��̂�2000�l������̂���A�����Ȃ��̂�50�l�Ŗ����Ƃ������̂�����B���̑傫����ݔ��͂��낢�낾���A����Ƃ����ꏊ���A�u�������������ԁv�ł���A�Ђ��Ă͂��ꂪ�����̋�Ԃł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�����ŁA���S�Ȃ������̌����邽�߂ɁA�ϋq�͌���֑����^�Ԃ̂��B���̉�X�̊��o�̒��ɂ́u�n���v���u�P�v���Ȃ����A����͖��炩�Ɂu�n���v�̋�Ԃł���B�]�ˎ���̗�������܂ł��Ȃ��A���a�̒����܂ł͉̕���������������̏ꏊ�̈�Ƃ��Đ��ԂɔF������Ă������Ƃ́A���Ɏ����I���B
�@���݁A�����̐l��������O�̂悤�Ɍ���֒ʂ��悤�ɂȂ�A�u�n���v��u�P�v�̈ӎ��͔��ꂽ�B����͎���̈ڂ낢�Ƌ��ɕς��䂭���̂ł���A�ے肷�����͂Ȃ��B�������A����ł��Ȃ��A����Ƃ�����Ԃ��A�u�����v�ł��邱�Ƃ͕ς��Ȃ��B���ꂪ�P�Ȃ����̉����ɂȂ��Ă��܂��ẮA���������Ɍ���̈Ӗ��͂Ȃ��Ȃ�B
�@40�N�߂��ςĂ���ƁA���낢��ȈӖ��Ŏŋ��̌���������Ă���B�߂Ɍ����艡���猩���藠���猩���肵�Ă���ԂɁA���҂̔\�͂̈�Ƃ��āA�u��Ԕc���̔\�́v�Ƃ������̂��傫�ȗv�f�ł��邱�Ƃ��������B80�l�̋�ԂŎŋ������Ă������҂������Ȃ�1000�l�̌���֏o�Ă��A���̖c��ȋ�Ԃ�c�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O�K�Ȃ̌��܂Ŏ����̐���ŋ���͂����邱�Ƃ͎���̋Z�ł���B���l�ɁA�傫�Ȍ���Ŏŋ������Ă������҂��A�����Ȃ菬����ŏo�����ɂ́A���|�I�ȃ{�����[���Ɋϋq�����ꂵ���Ȃ�P�[�X������B
�@�������A�ʔ������̂ŁA���낢��ȕ�����o�����Ă��邤���ɁA�����̎ŋ��̐��@���A����̃T�C�Y�ɍ��킹�Ăł���悤�ɂȂ���̂��B����ƂĂ��A���҂̘r�̈�ł���B���̊ȒP�ȗ��_�Ƃ������Ȃ��@����m��ʂ܂܂ɁA������̖��҂��傫�ȕ���ɏオ��ƁA���䒆�Ɍ��ԕ��������Ƃ����ߌ����N����B���������o�����d�˂āA����������Ɍ����Ԃɍ��킹���ŋ����ł���悤�ɂȂ�̂����҂̏C�s���B�c�O�Ȃ���A�����܂ōl���Ďŋ������Ă���Ⴂ���҂����Ȃ��B�����̋Z�ʂ������đ傫�Ȍ���֏o��̂�����A����̂܂܂̎p���u�����Ȃ�v�Ɍ�����悢�̂��A�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��ẮA�ŋ��̐��@�͐L�тȂ��B
�@�����̐����ǂ��܂œ͂��̂��A�����̎ŋ����ǂ��܂œ͂��̂��A�����������Ƃ��A���������̌���֎ŋ����ςɍs�������ɁA�ŋ������ł͂Ȃ��u�����ԁv�Ƃ������̂Ɉӎ����y�ڂ����Ƃ͔��ɏd�v�Ȃ̂��B���҂͐E�Ƃ����炻����V�r�A�ɍl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�ŋ��������ꂽ�ϋq�́A���ӎ��̂����ɂ���������̒��ő̊����Ă���B����́A�l���悤�ɂ���Ă͕|�����Ƃ��B���������q�ϓI�Ɍ��Ă���l���吨����Ƃ������Ƃ��B���̌��ʁA�u���̖��҂͏�����ł͋P���Ă����̂ɁA�匀��֏o���疣�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v�Ƃ������ƂɂȂ�B����́A�ϋq�͉s�q�Ȋ��o�������Ă���؋��Ȃ̂��B
�@���҂́A�������ǂ̒��x�̋�Ԕc���\�͂������Ă��āA�ǂ̒��x�̋K�͂̌��ꂪ�����ɓK������ԂȂ̂����A�畆���o�Œm��K�v������B���̏�ŁA�ǂ�������Ԃ𐧔e���悤�Ɠw�͂���̂��B�����ŏ㉉�����ŋ��ʼn���������̂��B�̂̉̕���ȂǂŁu���҂��傫���v�Ƃ����\�����悭���Ă������A����͑̊i�̂��Ƃł͂Ȃ��A�u��Ԕc���\�́v�Ȃ̂��B��\�N�ȏ�O�ɁA����̊Ԍ�����\���[�g���ȏ゠��̕�����̊Ԍ����A�������O�l�̖��҂ŔZ���ȋ�ԂɂȂ����B�����������Ƃ��A���D�̑傫�ȗv�f�Ȃ̂��B
�@�u�l���v���́u���l�v���̂̑�D���Ȏ���ɁA�u���w�v�ȂǂƂ������t���g�������̂Ȃ�l����������R�c�����邾�낤���A���\�Ȍ�����������A�����������Ƃɐ𗧂Ă�l�X�����w�Ȃ̂��B��100�N�قǑO�܂ŁA���w�ȂǓ�����O�̂��ƂŁA�p���ׂ����Ƃł����ł��Ȃ��B�u���m�̒m�v�̈Ӗ����킩��Ȃ��l�Ԃ����A���w�҂��B
�@�]�ˎ���́A���������|�I�Ɏ��������Ⴉ�������Ƃ͊F������悭�m��Ƃ��낾�낤�B����Ɠ����ɁA�V�Ï��X�ȂǂȂ�����A�{�Ƃ������̂̉��l�����ɍ��������B������A�ݖ{���Ƃ����E�Ƃ����X�Ɛ������Ă����̂ł���B�������āA�����̐S���̂�����͎̂ʖ{�����A�܂������N�����ʖ{������B���̌J��Ԃ��̊ԂɁA��L��玩���̈ӌ����������Ă����B�������A����͂����ꕔ�̐l�X�̍s�ׂł����āA���̓�������炷�̂��������ς��̐l�X�ɂƂ��ẮA����ȗI���Ȃ��Ƃ����Ă���ɂ͂Ȃ��B����Ȓ��ŁA�ŋ������ɍs�����Ƃ́A�܂��Ɂu���w�̑��w��i���w��Ƃ���������������j�v�������̂��B
�@���j�I�Ȏ�����A����̃j���[�X��X�L�����_���ɑ�������悤�Ȏ��ۂ��A�킩��₷���ŋ��Ō����Ă����B������d�˂Ă��邤���ɁA����ɗ��j��̑傫�Ȏ������A�^���ł͂Ȃ��܂ł����̍��i���킩���Ă���B�܂��ɁA���h�Ȋw��ł���B���ꂪ�A������҂̈���I�Ȍ�y���o�Ɋ�Â����̂ł������ɂ���A�]�ˎ���̐l�X�ɂƂ��Ă͉����̏�̈�ł������̂��B
�@����́A���e���r�̑O�ɍ����Ă��Ă���ɂł��Ȃ��s�ׂł���B�����͕����Ă��A���������Ŏŋ����y���݁A���̏�ł��낢��Ȓm������A��Γł���B�����Ƃ��A�ŋ߂͂�����������ɂ܂�Ȃ��ŋ����������Ă��������ɂȂ�P�[�X���r�������B���ߑ��̍��A�킴�킴�ŋ��ʼn������w�ڂ��Ƃ����l�͂��������͂Ȃ����낤���A�ӂƂ����Ȕ��ɐS��ł��ꂽ��A�C���������ꂽ�肷��悤�Ȃ��Ƃ͂���B����ƂĂ��A�m���ł͂Ȃ����A�S�̊w��ł���B
�@�n���͂��̂����������ŋ����Ȃ�A���̂��Ƃ肪�ُ�Ƃ��v����ʂ̒��Ő��E�������Ă���B�u���ۉ��v������ċv�������A�O����̃e�X�g�ō����_�āA�O����Ɋ��\�ȍ˔\�͗��h�ɕ]���ł�����̂̈�ł��낤�B���̈���ŁA���{�̕����Ɋւ��鋻���͂Ȃ��A�u���b���v�̑e���킩��Ȃ���A�u��������v�����ł����̂��m��Ȃ��l�������͎̂������B���l�������獂���낤�ƁA�����̕����ɋ����������A�ւ������Ă��Ȃ��l�X���A����ł́u���w�ҁv�ł���B�ÓT�ɐ��ʂ���A�Ɖ����������͂Ȃ��B�������A���{�̖L���ȕ����������N���������Ĕ|���Ă������t�̔������⊴���̖L�����Ɍ������������A�u�ÏL���v�u����Ă킩��ɂ����v�ƈ�R���Ă��܂��l�X�����A����́u���w�ҁv�ɓ������B
�@���Ⴂ���Ȃ��ł������������̂́A���{�̌Â����������t�������킯�ł͂Ȃ��B���̐V�������{�̎ŋ����������̐l�Ԃ̂���悤�╨�̍l������m�邱�Ƃ͏[���ɂł���̂��B�����������ɖڂ����ꂸ�ɁA�����������{�̊O�������Ă��邾���ł́A���{�l�Ƃ��č��ۉ��ɍv�����邱�ƂȂǂł��Ȃ��̂��A�ƌ��������̂��B�u�����ÏL�����Ƃ��v�Ƃ����������邾�낤�B����͓��R�̂��Ƃ��B�������A���{�l�Ƃ��Ă̌����g�̂ɗ���Ă���ȏ�A���{�Ɋւ���m�������܂�ɂ����Ȃ��̂ł́A�]�ˎ���̖��w�҂������Ƃ͂ł��Ȃ����A�ꍇ�ɂ���ẮA�O�����Y��ł����g�͋���ۂȌ���l�ƌ���ꌓ�˂Ȃ��B�u�ŋ��͖��w�̑��w��v�Ƃ������t�́A�����Ĕn���ɂ͂ł��Ȃ��̂��B
�@�l�̂��Ƃ��肠���ł��Ȃ������ł��Ȃ��Ƃ����A�u�����]�_�Ɓv�͈�̂ǂ��Ȃ̂��H�@���������₢�ɂ������œ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B���a�������獡���܂ł̊ԂɁA�u���]�v�Ƃ������̂͑傫���ϖe�𐋂����B�����Ɍ����A�u�͂��������v�̂��B���̗��R�͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ����A���̑��݉��l���ቺ�����͎̂����ł���B�V���̌��]�Ɋ������X�y�[�X�͔N�X�������Ȃ����ŁA��`������]�����킩��Ȃ����̂������B������A���͎����������������Ƃ��������߂ɁA�������ɔ����Ȃ����߂Ɏ�����HP�𗧂��グ�Ă���B
�@�q�ϓI�Ɍ��āA�ŋ��Ɍ��炸�������u��]�v���邽�߂ɂ́A���̕���Ɋւ���c��Ȓm���Ɖs�������������Ȃ��Ă͋܂�Ȃ��B�����̔�]��������Ɨ��t�����A�ǎ҂�������邢�͔[���������邾���̂��̂��K�v�Ȃ̂��B�������u���z�v�Ƃ͑傫���Ⴄ�Ƃ��낾�B
�@21���I�̍��A�C���^�[�l�b�g��M���ɂ��ꂾ���̏���ӂ�Ă��钆�ŁA�u�����]�_�Ɓv�̕K�R���A���邢�͑��݈Ӌ`��q�˂�ꂽ���A�c�O�Ȃ���u�ϋq�̑����͂����K�v�Ƃ��Ȃ��v�Ɠ�������Ȃ����낤�B�������A�㐢�̊ϋq�i���������l�X�����Ă���邱�Ƃ�ߒɂȂ܂łɖ]��ł���j�̂��߂ɁA�u�����̋L�^�v�Ƃ��Ă̔�]�Ƃ̑��݂͕K�v�ł���B���̂��߂ɂ��c����]�͌����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝ��͍l����B�����̎d���̑��݈Ӌ`���A�S�ʓI�ɂł͂Ȃ��ɂ���u�ے�v����͔̂��ɐh���A�������B�������A�u�]�_�Ɓv�𖼏��̂ł�������A���q�ϓI�Ȋ�Ŏ����̎d�������āA��]���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��B���̗����ȁA���������̒ɂ݂�����F���͏�̒ʂ�ł���B
�@���̏ꍇ�Ō����A�̕�����͂��߂Ƃ����ÓT�|�\�A�V�h�A�X�g���[�g�E�v���C�A�l�`��ڗ��A�~���[�W�J���A������A�匀�ꉉ���Ȃǂ���]�̑ΏۂƂȂ�B�����Ă���͕̂�˂��炢�ł��낤���B�����̎ŋ��ׂ̍��ȕ����ɂ܂Ŗڂ�z��A���҂̉��Z����r�{�̏o���A���o�Ƃ̎p���Ȃǂ𑍍��I�ɔ�]���邱�Ƃ�S�����Ă���B�������A�s���ȕ����〈����������������A100���̔�]�͂��Ȃ�Ȃ��B���������Ȃ�100���ɋ߂Â��邽�߂ɁA�ŋ����ρA���e�������A���������A�ߋ��̉f�����Q�l�ɂ�����Ƃ������͓��X�����Ă���B
�@�ŋ߂̉����ɂ܂��}�̂�ǂ�ł���ƁA�u�������C�^�[�v�Ƃ��������̕��X���������B��]����ł͂Ȃ��A���̋L���������I�ɏ����A�Ƃ������Ƃ��B�����A��]�ȊO�̌��e�������B����́A�N��E����Ԃ̊��o�̈Ⴂ�ŁA�E���Ƃ��Ă͂������Ȃ��Ǝ��͍l���Ă���B�������A�u�����]�_�Ɓv�Ɩ����l�X�̒��ł́A�����炭40��㔼�̎����Ō�̐���ł͂Ȃ����낤���B�����ɋM�d�������߂�킯�ł͂Ȃ��A���̎���������̏ے��Ȃ̂��A�Ǝ��͊����Ă���B�����������A���錀��ɓd�b�������܂ɁA�u���]�Ɓv�Ɩ��������u����Ƃł����H�v�ƕ����ꂽ���Ƃ��������B������������A���ꂪ�����ł���B�����ے肵�悤�Ƃ���̂ł���A�����̔�]�ɂ��Ă̂悤�ȉ��l���������A�����̊ϋq��W�҂��u�����œI����]���v�Ɣ[������悤�Ȕ�]�����������Ȃ��B�ߋ��̌��]�Ƃ͗ǂ������ƒQ���Ă݂��Ƃ���ŁA�������܂�͂��Ȃ��B
�@��葽���̐l���[���ł���悤�Ȍ��]���������߂ɁA�������i��ōs���������@�͂Ȃ��̂��B���̌��e�̒��Łu���D�͈���ɂ��ĂȂ炸�v�Ə��������A����͔�]�ƂƂē������Ƃ��B�����g���A30�N�ȏ�ŋ��̕������Ă��Ȃ���u����Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ������̂��v�Ƌ����A����邱�Ƃ͂�������B���̌J��Ԃ��ŏ������ςݏグ�A�����ł��ǂ����e���������ƁA���ꂪ���܂Ŏ��������������ŋ��ւ̉��Ԃ��ł���ƍl���Ă���B
�@�ŋ��́u����|�p�v�ł���B���̈���ŁA�u�r�W�l�X�v�ł�����B�ϋq�Ɋ������т�^���A�ϋq�����҂��X�^�b�t�������A�����ăr�W�l�X�Ƃ��Đ�������̂����z�I�Ȍ`���B�������A���ꂪ�����ɓ�����Ƃ́A���܂łɑ����̐l�X�������̐l����q���ďؖ����Ă���B�ł͕s�\�Ȃ̂��A�ƌ����A�ȒP�ɂ����Ƃ͌�����Ȃ��Ƃ���ɂ݂�Ȃ����ݓ���閂�͂�����̂��낤�B
�@���c�ɂ��悻���łȂ��ɂ���A�ŋ���ł����A�����������M��v�z��|�p�I�X��������I�Ɋϋq�ɉ����t������₢�������肵�Ă��A�����̊ϋq�̎x���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̋t���܂�������ł���B
�@�]�ˎ���̏�ڗ���҂ł���ߏ��卶�q��́A�u�����疌�_�v�̒��ŁA�u�{���̌|�́A�R�Ɛ^�̊Ԃɂ��邲��������̂悤�Ȃ��̂��v�Ɛ����Ă���B�ߏ��̖���m��Ȃ������l�͂��Ȃ����낤���A�ނ̂��̗D�ꂽ�_�l�𗝉����Ă���l�́A�w�҂͂Ƃ���������̐l�Ԃł͏��Ȃ������m��Ȃ��B
�@����͂܂��Ƃɐ����Ă��āA���̎ŋ��̗l�X�ȃV�[�������̌��t�Ő������邱�Ƃ��\�ł���B�ϋq�ɂƂ��Ă����҂ɂƂ��Ă����z�I�Ȃ̂́A�|�p�ƃr�W�l�X�̂����킸���Ȍ��Ԃɔ����\���Ă����Ȃ̂ł���B�����A�����ȒP�ɋC�Â����̂ł͂Ȃ��A�\���ł�����̂ł��Ȃ�����A�������ǂ������邩�A���邢�͊y���ނ��̎��s���낪���S�N�������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@���̌��t�Ō����u���Ƃ��ǂ���v�Ȃ̂����A����̑��l���ŁA���ꂪ�S�������Ȃ��ł���B������A�e���r�ł�����Ɣ��ꂽ���҂�ɋN�p���Ă݂���A�ߋ��̍�i��������x����ɏ悹���肷��B���̎��݂̂��ꂼ��ɂ͗��������낤����A���ׂĂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�v�͂��̖��ɂ������ƋC�Â��A������T�����ƂȂ̂��B�ꏊ�����T�����Ƃ���ŁA�����Ɍ�������̂ł͂Ȃ��B������ƌ����āA�r�W�l�X����ɑ����Ă��肢�ẮA���̊ϋq���x����Ȃ��B
�@���̋͂��Ȍ��Ԃ�T�����Ƃ������ɏd�v�ł��邩�A���̂������ăV���v���Ȑ}���ɋC�����A���s���悤�Ƃ���u�p�f�v�����v���f���[�T�[�����Ȃ��͎̂������B�����������ɓ���ꂵ��ł���l�������B������A���̂悤�Ȏ҂̂Ƃ���ɂ܂Łu���̎���ɂ͂ǂ�ȍ�i���K���v�Ƃ������₪����̂ł���B
�@���_���猾���A���̓���������������A�����n�̖ڂ����̒��̂��Ƃ��A�N�����Ƃ����ɂ���Ă��邾�낤�B�u�����ł��Ȃ��v�u����͑ʖڂ��v�̌J��Ԃ��Ȃ̂ł���B���������̕X�͊��̊ϋq�́A���̌��ʂ�҂��Ă���]�T�͂Ȃ��B����͋��s�T�C�h�Ƃē������Ƃł���B���̏ł肪�A���̃X�p�C�����Ƃ������ׂ����s�ɂȂ����Ă���̂����̉����E�̌���̈�ʂ��B
�@�ߋ��̖����l�C�o�D�ŏ㉉����B�ꌩ����A�m���Ɍ|�p�ƃr�W�l�X�́u�ԁv���Ƃ炦�Ă���悤�Ɍ�����B�������A����ł͒P�ɓ�́u������́v���������������ɉ߂��Ȃ��B����Řb�����߂ΊȒP���B�����ŁA�j�����Ƃ�������悤�ȁu�����v���N�������ɁA����Ɗϋq���M������̂��B���́u���Γ_�v���A�ߏ��������Ƃ���̔������Ȃ̂ł͂���܂����B
�@�����Ŏ����q�ׂĂ�����́A��Ɏŋ���n�鑤�̘b�ł���B�������A�ϋq�ƂāA���̖���m���Ă��đ��ɂ͂Ȃ�܂��B�����������Ƃ́A�w�Z�ł͋����Ȃ��B�������ӂ��āA�����ς���ɂ����Ȃ��ŋ����ς���łȂ��ẮA�����̊��o�ɂ͂Ȃ�Ȃ����̂��B�����l�\�N�߂��ŋ����ςė��āA����ƍ��ɂȂ��Ă���Ȃ��Ƃ������Ă��鎟�悾�B������A���炩�̌`�ŁA����HP�ɂ��t���������������Ă���ǎ҂ɊҌ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�ŋ��̐�����������B���ĂȂ��������B����ꂽ���ԂƎ����̒��ŁA��̉����ς�Ηǂ��̂��A��������߂�͍̂����̒��ňꗱ�̃_�C����T���ɓ�����������B
�@���̎Ⴂ�ϋq�ɂ͐M�����Ȃ��b���낤���A�����w���̍��́A�ό��̗\�肪����܂Ō��܂��Ă��邱�ƂȂǂȂ������B�ɒ[�Șb������A���̓��Ɏv�������ďo�������Ƃ���ŁA��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����͐ؕ������������̂��B���͗ǂ����������C���^�[�l�b�g�̔��B�ŁA����s�\������ʗ\�ƁA�����������Ă��邩�ǂ������킩��ʐ�̓����̎ŋ��̐S�z�܂ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ����̂́A�ŋ������������ƂɌ����ɔ�Ⴕ�Ă���B
�@�ŋ��̐��������A�Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���ŋ��ɖ��͂������Ă���l���������ƁA�܂��ŋ��̑��l���E�ו������傫�Ȍ������낤�B���̌��ʎŋ��������A�����ŋ��Ŋϋq�������ł�����̂��肪����ł���Ηǂ����A��ԍ���̂́u���݂��lj݂��쒀����v���Ƃł���B���A���łɂ�����������ɂȂ����B�����u�X�͊����v�Ƌ��ԑ傫�ȗ��R�̈�͂��̖��ɂ�����B
�@���ׂĂ������𒆐S�Ƃ����֓����Ɉ�ɏW������̂́A�ŋ������̘b�ł͂Ȃ��B��O���Y�Ƃ̑����͂��̌X�������ǂ��Ă���B�n���ł���Ȃ�̃l�[���o�����[�������Ċ撣���Ă��錀�c�����邪�A�����̉������x���������邽�߂ɁA����]�n���Ȃ��̂�����ł���B���ꂪ�����O�a��ԂɒB���A����Ƃ����n�[�h�E�F�A�̃X�N���b�v���r���h���n�܂����B�匀��E��������킸�ɁA�ł���B���ꂾ�����ꂪ������ƁA���R�̂��ƂȂ���\�t�g�E�F�A������Ȃ��Ȃ�B�e���r���f�W�^���������n�߁A���̌��ʂƂ��ă\�t�g������Ȃ��ĉE���������Ă���̂Ɠ������Ƃ�����ŋN���Ă���̂��B
�@����ɂ͒��̊Ԃł͎�y�ɖ��키���Ƃ̂ł��Ȃ��u���C�u���o�v������A���ꂪ�����B���̊y�����𖡂키���߂ɁA�ϋq�͖c��ȃG�l���M�[������Č���֑����^�ԁB���邢�́A�^�т����Ǝv���Ă���B�������A���̑I���������܂�ɂ��������߂ɁA�����ςɍs���ėǂ����̂������Ă��邤���ɁA�`�P�b�g�������ɂȂ�A�������n�܂�B���邢�́A�`�P�b�g�������Ă��܂��B����ł́A�ϋq�̂�����͍L����Ȃ��̂��B
�@�u�����ς邩�v�Ƃ����I�����́A��Ɋϋq�̎�ɂ���B�����Y��Ȃ����Ƃ��B�Y��Ă��Ȃ��Ƃ��A�u�ςȂ��Ă͂����Ȃ��v�悤�ȋC�ɂ������Ă��܂����Ƃ����X�ɂ��Ă���B����͐�`�̏����ŁA���̋C�ɂ������Ė�������Ηǂ����A���Ȃ��ꍇ������B�S���S���ł��������ŋ�������ςĂ��邱�Ƃ͕s�\�����A���Ȃ����A����������ÂȊ�ŕ����I�ԕK�v������B����́A�ϋq�̐ӔC�ł���B
�@�N�����Ȃ��ŋ����A���ɏ㉉���錀��͂Ȃ��B���ꂪ���R�����Ƃ������̂��B�V��ӂ�������A���̃X�p�C�����ɓ��邾���Ȃ̂ł���B���̐V��ӂ𑣂��̂́A��X�ϋq�ł���B�����̕���̒��ʼn����ς���ǂ��̂����������ɁA���m�ȏ������̂��A�����]�_�Ƃ̖�ڂł���B�����������A�u�����l���鐳�m�ȏ��v���B�����Ԏŋ����ςĂ���A���̌o���Ƃ��������̒m���𗊂�ɂ��āA���Ǝ��̕��ʎ��j�Łu���̕����ł���v�Ǝw���������Ƃ��ł���Ηǂ��̂��B������������Ȃ����́A�ǎ҂̔��f���邱�ƂŁA�����������͂��炳��Ȃ��B
�@�����A���̎ŋ����܂��ɖ��\�L�̍�����Ԃɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�푈����ł����̂悤�ȍ����͂Ȃ������͂����B�e�ς͓����܂܂Ŏ��ʂ�������A����͓̂��R�̂��Ƃ��B���������邽�߂ɂ́A��X�ϋq���T�d�ȁu��v�������Ƃ���̕��낤�B
�@�f��o�D�̃`���b�v�������A�u���Ȃ��ɂƂ��Ă̍ō���́H�v�Ƃ̖₢�ɑ��āu�l�N�X�g�E�����v�Ɠ������Ƃ����G�s�\�[�h�͗L���Șb�B��Ɏ��Ɋ��҂���A�Ƃ����v���C�h�������������̂ŁA���ꂾ���̂��̂������Ă������M�ɗ��ł����ꂽ���t�ł���A�����������~悂��܂܂�Ă���̂��낤�B
�@��X�ϋq�ɂƂ��Ă��A�u�l�N�X�g�E�����v�͕ʂ̈Ӗ��ő���B�u�����̎ŋ��͖ʔ��������B�܂��A�������������ŋ����ς����v�ƁA�ϋq�̑������v����悤�ȏA���ꂪ�ϋq�ɂƂ��Ắu�l�N�X�g�E�����v���B���������玟�ւƂ����ŋ����肠��킯�ł͂Ȃ��B�v���싅�̑I�肾���āA�ŗ��O�����L�[�v����̂������ɓ�����Ƃ��B���҂≉�o�Ƃ����ɂP�O�O�������߂�͍̂��Șb�ł���A�ϋq���ڂ��삦��Δ삦��قǂɃn�[�h���͍����Ȃ��Ă䂭�B�u�O�͖ʔ��������̂Ɂc�v�̈ꌾ�œ�������Ă��܂��̂��B
�@���ǂ̂Ƃ���A��X�̐l���ɂ����āA�P�O�O���Ƃ����͕̂s�\�Ȗ�肾�B�����A��������Ȃ��߂Â����߂̓w�́A���ꂪ�K�v�Ȃ̂��B����͎ŋ��̐��E�����Ɍ��������ł͂Ȃ��B�Ƃ͌����A�s�f�̓w�͂𑱂��邱�Ƃɂ������l������B�w�͂Ƃ������̂́A���������ƂɕK���������̂ł͂Ȃ��B������w�͂����Ă��P�O�O�����Ȃ���A���̓w�͂������Ɍ�������ۏ��Ȃ��B
�@�������A���ƌ|�\�Ɋւ��Č����A�����������E�����炱���A�`�������W���鉿�l������̂��������B�u�����̎ŋ��͑����I�ɉ��_�ł��v�Ƃ������f�ȂǁA�N�ɂ���������̂ł͂Ȃ��B�ɒ[�Șb������A�{�l���u�l���ōō��̎ŋ����ς��v�Ɗ������Ă���ׂ̐ȂŁA�u�����̎ŋ��͍ň��������v�ƒQ���Ă���l�����Ă����������͂Ȃ��B���Ƃقǂ��悤�ɁA�ς�l�ɂ���ĕ��������Ⴄ�ŋ����A��葽���̐l�Ɋ��ł��炦��悤�Ȃ��̂�n��̂������l�̖�ڂ��B
�@��]�Ƃē������ƂŁA���ʼn������悤�Ȕ�]����������Ă��Ă͈Ӗ����Ȃ��B���\�N���ŋ����ςĂ��āA����C�������Ƃ�����B�u���܂łɉ��x�����̎ŋ����ςĂ��Ȃ���A�Ȃ��C�t���Ȃ������̂��낤�v�Ǝ��������߂Ȃ���ƘH�ɒ������Ƃ͏��Ȃ��͂Ȃ��B�������������ɂƂ��Ă̎��n���A���̔�]�ɔ��f�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���A��]�������Ă���Ӗ��͂Ȃ����낤�B�l�Ԃ́A�Ƃ����p�^�[���ɂ͂܂�₷���B�܂��A��x�p�^�[����n���Ă��܂��A�����Ɉ��Z���Ă�������y�Ȃ̂͌����܂ł��Ȃ��B�������A�u�l�N�X�g�E�����v�̂��߂ɂ́A���Ƃ��Ď����Ŏ����̊k��ł��j��悤�Ȍ������s�ׂ��K�v�ɂȂ�̂��B
�@�u�����͈Ղ��s���͓�v�B�Â̐l�͂��܂����Ƃ��������̂��B���̎����ɂ��ꂪ�ł��A�ڂ̊o�߂�悤�Ȕ�]���������M������̂��A�Ɩ����A�u�����������Ԃ����������v�Ƙl�т邵���Ȃ��B�������A���̓����A��]�������Ă��邱�Ƃ̈Ӗ������̂��Ɩ��炩�ɂȂ�悤�ȁA���ꂪ�����E�ɖ𗧂悤�Ȕ�]�������悤�ɁA�����Ђ�����ɕ������邵���Ȃ��B
�@�ŋ߁A�u�ł���v���Ƃ̑���A���悤�₭�킩�肩���ė����悤�ȋC������B�����ł́A�܂��x���͂Ȃ��A�Ǝv���Ă���B�����̔�]�̂��߂ɁB���̎ŋ��̂��߂ɁB
�@���̍e�Ɍ��炸�A���͂悭�u������v�Ƃ��������A�u��������v�Ǝ����Ɍ����������Ă���B�ł́A�ŋ��̐��E�ɐ�����l�ԂɂƂ��āA���Ƃ͋�̓I�ɉ��������̂��낤���B
�@�ɘ_������A�����Ă��邱�Ƃ����Ȃ킿�������A�N�w�I�Șb�����Ă��d�����Ȃ��B�ŋ��Ɋւ����̂ł���ȏ�́A�u�ŋ���m�邱�Ɓv�����Ȃ킿�����낤�B�ŋ����ς�͓̂��R�̂��ƂȂ���A�Y�Ȃ�ǂށA�M�y�ł��m�y�ł��m�Î�������A�g�̂̈ێ��̂��߂̃g���[�j���O���s���A�f����ς�A�{��ǂށA�Ɛ����グ��ΐ肪�Ȃ��B
�@��]�Ƃ͂ǂ�ȕ�������̂��B���̎���͂����܂ł��l���̂ŎQ�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���A��]�Ƃ����������ɔ�]������̂��A��m��藧�Ăɂ͂Ȃ邩���m��Ȃ��B
�@�������܂��ς����Ƃ̂Ȃ��ŋ��ŁA�r�{������������Ă�����̂́A�ɗ͎��O�Ɋ��ʂ��B�ŋ��̂��炷���̒��ɒ@������ł����B���̎ŋ��̌������e�[�}���ǂ��ɂ���̂��A�����炩���ߒm���Ă������߂��B��{���Ȃ����̂́A�k��ŏo������B
�@���x���ςĂ��镑���ʂ̖��҂Ŋς�ꍇ�́A�����̊ό��������Ђ�����Ԃ��āA�ߋ��̕��䂪�ǂ��ł���������z���o���B�ǂ��������������̒��ɔ�r�Ώۂ̎������B�����Ƃ��A������]�ɏ������ǂ����͂܂������ʂ̘b�ŁA�O�\�N���O�̕���Ɣ�ׂĂ��Ӗ����Ȃ��Ȃ��ꍇ�������B
�@��́A�{��ǂނ��Ƃ��낤���B�Ⴆ�Ή̕���̏ꍇ�A�̕���̂��Ƃ����ׁA���̒��ɓ���Ă����悢�A�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���{�̌��z����p�A�����⒃���A���x�A���y�A�������������I�Ȕw�i���o�b�N�{�[���Ƃ��Ď����̒��Ɏ����Ă����B
�@�C�O�̎ŋ����������Ƃ��B�u�}�C�E�t�F�A�E���f�B�v���ς�̂ł���A����ɓ�����o�[�i�[�h��V���[�́u�s�O�}���I���v����n�܂�A�����̉p���̐����╶�����ς�B�p���Ɍ��R�ƋM�������݂��A�u�K���v�Ƃ������̂��͂����肵�Ă��邩�炱�����̎ŋ������藧�̂��A�Ƃ����w�i�������̒��Ɏ����ĕ�����ς邱�ƂɂȂ�B
�@�u�ŋ��v�Ƃ�����̊j�𒆐S�ɂ��āA�l�������֖����Ɏ}�����������悤�Ȃ��ƂɂȂ�B���̎}��������ǂꂾ���L���邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����u�D��S�v�Ɓu�~�v�������Ƃ��A���Ȃ킿���ł͂Ȃ����낤���B
�@����A��͌���Ŏs�����e�́u���̐l�v���ς��B����̓��{�����ł͔��ɕ]���̍�����i���B�����A�ߋ��̑��̕�������������B�Y�Ȃ�������x�ǂݒ������B��������ƁA�S�b�z���g�̂��Ƃׂ����Ȃ����B���l�ɁA�o��l���ł���S�[�M������[�g���b�N�̂��Ƃ��m�肽���B�܂��A�S�b�z���������u�W���|�j�Y���v�̎���ɂ��������킭�B����ŁA�O�D�\�Y�Ƃ�������Ƃ��A�Ȃ��S�b�z���������Ƃ����̂��A������C�ɂȂ�B�O�D�\�Y�W�̖{��ǂ�ł��邤���ɁA���̍�i���ǂ�ł݂����Ȃ�B���̍�Ƃ��J��Ԃ��Ă���ƁA�i���ɔ�]�ȂǏ����Ȃ��Ȃ�̂ŁA���������v����Đ�グ��B
�@�����������Ƃ̐ςݏd�˂ŁA�K�v�E�s�v�Ȓm�����A���y�̊k�ɂ��S�~�̂悤�ɂ܂Ƃ����ė���B���x�́A��������̂܂܂ɂ��Ȃ��ŁA�u�l����v���Ƃ��B�u���̍�Ƃ͂Ȃ��A���̎ŋ����������̂��v�ł��A�u���̎ŋ��̃e�[�}�͉����v�ł��A�u���̖��҂ɂ��̖��͓K�Ȃ̂��v�ł��A�e�[�}�͉��ł��悢�B�����������m�������̂܂ܕ���o���Ă����ƁA�����Ōł܂��Ă��܂��B���̒m�������������߂ɁA���o�Ԃ����Ă������悤�ɁA������ɏ_��ɂ��������B�Ƃ������z�������āA��������B
�@���낻�뎩���́u����v�Ƃ������̂��ǂ��l���Ă��邩�A����m�ɂ��鎞���ł͂Ȃ����Ǝv���B���āu�ꉭ���]�_�Ǝ���v�Ƃ������t�����������A���ꂾ�����̑������̒��A�����̓��ӂȕ��삪����A�u�]�_�Ɓv�Ɩ���邱�Ƃɂ͉��̏�Q���Ȃ��B���́A���Ԃ������F�m���邩�ǂ����̖��ł��낤�B�������������A�u�����]�_�Ɓv�Ɩ�����Ă͂�����̂́A�����̎��i������킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł��u���́v�ł���B
�@�Ƃ͌����A�v���̂��Ă���d���ɑ��ĉ������������Ƃ����̂ł��邩��A���ꑊ���ȏ�̊o�傪�Ȃ���Δ�]���������Ƃ͂ł��Ȃ��̂��������B�����ȍ~�A�u�����]�_�Ɓv�Ƃ������̂̈ʒu�t�����傫���ς��A�͂����茾���Ă��܂����̌��Ђ͎��Ă������ł���B���Ђ�U�肩��������Ȃǖѓ��Ȃ����A��������ς���u�M�p�v�̃��x�����������ė����A�Ƃ������Ƃ��B����ɂ͎��Ԃ̌o�߂ɔ��������̕��G�ȗv�f�����ݍ����Ă���A���̃R�����ň���ɏq�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����A���炭�O�Ɍ��݂̕]�_�Ƃ��u����Ă��闧�����������悤�ȏے��I�ȏo�������������B�V���̘A�ڋL���ł��Ȃ茵�����ӌ����������܂̂��Ƃ��B���m��ʓǎ҂̕�����u�]�_�Ƃ͖J�߂�̂������Ȃ̂ɁA����ȂɌ��������Ƃ������Ă��܂��āA��̎d���ɍ����x���Ȃ��̂ł��傤���v�Ƃ����|�̃��b�Z�[�W�������Ƃ�����B�ǂ����������A���ꂪ�q�ϓI�ɑ������Ă���u�����]�_�Ɓv�̃C���[�W�Ȃ̂��A�Ƃ������ƂɎ��̓V���b�N�����B����Ɠ����ɁA���̃��b�Z�[�W���A�݂𐳂��z���œǂB
�@�m���ɁA�V���Ȃǂ̌��]�͂킸���ȃX�y�[�X�i�̂̎O���̈���Ȃ��قǂ��j�ɁA��ȏo���ҁA�ŋ��̑e�A������̖��҂Ɋւ���킸���Ȕ�]�������Ă�����̂������B����ł́A�u�J�߂�̂������v�ƌ����Ă����_�̗]�n���Ȃ��B���̎Ⴂ�����t�@���ɂ́A������]�Ƃ������̂��A���Ă͏�ł���Ɠ����Ɉ�̂�����Ƃ����ǂݕ��ł���������Ȃǂ͑z�������Ȃ����낤�B���ꂪ�A����̗���Ŗ������ω����A���̂悤�ȏɂȂ��Ă���̂��B
�@��������Ă������������Ȃ��̂́A�u�J�߂鏤���v�ł��Ȃ���u���Ȃ������v�ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B�V���v���ɁA�u�ǂ����͗ǂ��v�A�u�������͈����v�ƁA��O�҂̋q�ϓI�Ȋ�ŁA�ŋ����ςāA�����̒m����ߋ��̊ό��o���̒������r������̂��������Ηǂ��A�Ȃ�����Ȃ��Ƃ��ǂ��B���̃V���v���ȃK���X�̂悤�ȍ\�������������܂��Ă��邱�Ƃ͔ے�̂��悤���Ȃ��B
�@���A�����]�_�Ƃɋ��߂��Ă���̂́A����قǑ����ŋ��̒��ŁA�����ł������̎ŋ��̏��M���A�ϋq�ɂƂ��ẴA�h�o�C�U���[�̖�ڂ��ʂ������Ƃ��낤�B���̃��b�Z�[�W��M�p���邩���Ȃ����́A���ǎ҂̖��ł���B
�@�����]�_�Ƃɋ��߂���̂́A����̑召���킸�A��{�ł������̎ŋ����ς邱�Ƃ��낤�B���̎ŋ��ɑ��A�K�Ȕ�]���q�ׂ邱�Ƃ͍Œ�̏����ł���B���̏�ŁA���̉����E�̒����Ŋ����Ȃ���A�ܔN��A�\�N��̉����E�̂���悤���l���邱�Ƃ��B���̏�ŁA�ߋ��̊ό��̒~�ς����ɂ��Ȃ���A����̉����E�̓��������ɂ߁A���ꂼ��̍l���M���邱�ƂȂ̂��A�Ǝv���B
�@���́A�ŋ��̐����������āA�ƂĂ��̂��Ƃɂ��ׂĂ��ςĕ������Ƃ͕s�\�ł���B���̒��ŁA�����̊�Ɗ����Ŋς�ŋ����`���C�X���A����������ɂ��Ċϋq�ɓ`���邩�B�ϋq�̒��ł��܂����t�ɂł��Ȃ�������A�����Ƃ����}�̂ŊF����ɓ`���邱�Ƃ��낤�B���ꂪ�[���ɂł��Ȃ��͑��X����B���̒��ŁA�����ł��ǂ��ŋ������o�����Ƃ��A�����ł������A�����̎ŋ����ςĂ���l�Ԃɉۂ���ꂽ�u�`���v�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@���̗��҂��҂���ƈ�v����P�[�X�͑����ɋH�Ȃ��Ƃ��낤�B���s�T�C�h�ɂ͂���Ȃ�̎v�f������A����Ɋϋq���������������ǂ����A�����b�����łł���B������K�������A�\�z���͂���Ă�����ŋ�������B���s�̗��j�ȂǁA���̌J��Ԃ����ƌ����̂͗��\�����m��Ȃ����A�����͂��ꂽ�b�ł��Ȃ����낤�B
�@����قǂ̏���钆�ł́A�ϋq�Ɂu�ς����ŋ��͉��ł����H�v�Ɩ₢�|���Ă��A�����ɓ����邱�Ƃ͓�����A���̓������獷���ʂœ��v�̂Ƃ�悤���Ȃ����낤�B�ǂ�ȂɁu�ǂ��ŋ��v���Ǝv���ď㉉���Ă��A�̐S�v�̊ϋq������ɑ����^��ł���Ȃ��Ă͉����Ӗ����Ȃ��B����ŁA�ϋq�̍D�݂����D�悵�āA���������ɑ����Ă������Ƃ��������̎��͌��サ�Ȃ��B
�@��������҂����͂��̂͂��܂ŋꂵ��ł���A���s������J��Ԃ��Ă���B�Ƃ͌����A�����Ĉ������ꗿ�ł͂Ȃ��B�܂��āA���̕s�i�C�ł���B��x�̎��s���v���I�ȑŌ��ɂȂ邱�Ƃ����X�ɂ��Ă���̂��B���̏̒��ŁA�u���������ŋ��v�Ɓu�ς����ŋ��v�������Ɉ�v�������ɁA�݂�Ȃ������ł���悤�ȕ��䂪�����J����̂��B
�@�u�����͈Ղ��s���͓�v�B�ŋ��̐��쌻������������Ă��āA�����̃X�^�b�t����҂�����ꂽ���Ԃ̒��ŋꂵ�݁A���̌��ʁA�݂�Ȃ������̂䂭���䂪�ł������Ȃɂ��ꂵ�����Ƃ͂Ȃ��B�������A���������`�����X�ɏ��荇���邱�Ƃ͎c�O�Ȃ�����ɏ��Ȃ��B�����������A�Ƃ������̂͂Ȃ��B����͂킩���Ă��Ă��A�����ł��N�I���e�B���グ�����A�Ƃ����̂͐l��ł���B
�@���̔��B��������爫�����ŁA�C���^�[�l�b�g�̂������ŏu���Ƀ`�P�b�g����ɓ���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������̂́A�ŋ��̏������J���ĕ]�����܂ł��Ȃ��A�`�P�b�g�͑��������A�Ƃ��������������B�{���ł���A���c�l�G�̂悤�ȓO�ꂵ�������O�����E�V�X�e���̓�����}��̂���̕��@�Ȃ̂����A���̂悤�Ɋ��S�ɌŒ艻���ꂽ����̃X�P�W���[���̒��ł͂�����܂܂Ȃ�Ȃ����낤�B���������A���{�̉̕���ȂǍ]�ˎ��ォ�烍���O�����E�V�X�e���𑁁X�Ɠ������Ă���A�]�����ǂ��ċq������Ή\�Ȍ���㉉���邵�A�s�]�œ��肪������Αł���Ƃ������ɃV���v���Ȍ`�Ԃł���B����Ƃ����n�[�h�E�F�A�̈Ӗ��������ƌ��݂ł͈قȂ��Ă���̂ŁA�����ȒP�Ɉڍs�͂ł��Ȃ����낤���A�������낻����{�̋��s�`�Ԃ��{�C�ōl�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B
�@�ŋ߂ł́A�n���̍��Z�̏C�w���s�̃X�P�W���[���̒��ɁA�����Ŏŋ����ς�Ƃ����R�[�X���D�荞�܂�Ă���w�Z�������Ԃ����B�����^���[�߂���A�f�B�Y�j�[�����h�֍s������ł͂Ȃ��B�����Ƃ����������W�����Ă��铌���ŁA���̕���ɐG���@����������悤�Ƃ����l���͎^�����B�������A����ł����Z�̐搶���͂��܂�ɂ������ŋ��̐��ɁA�ǂ��I��ŗǂ����̂��I���ɖ����P�[�X�������ƒ������B���̎d���̈�p�ɁA���������n���̍��Z�֍��̓����̉��������m�点�A�ŋ����ς����Ƃ̂Ȃ����Z���Ɏŋ��̖��͂�b���Ƃ������̂������Ă����B������C���^�[�l�b�g�����y���Ă��A���̐��̕����������������̂�������Ȃ��B
�@����Ȃ��Ƃ��l���Ă݂�ƁA���܂Ŏl�\�N�߂��ŋ����ςĂ������̂��A���ʂɂ��Ȃ��悤�ɂ���ɂ͂ǂ�����Ηǂ����Ɛ^���ɍl����B��x�ɑS����f���o�����Ƃ͂ł��Ȃ����A�����ȂƂ���Y��Ă��܂������̂������B�������A����͕ς���Ă��ŋ��̐��̖ʔ����͕ς��Ȃ��͂��ł���B�������̃R�[�i�[�͏I���ɂ��邪�A�܂�������`�ŊF����Ɏŋ��̖ʔ����₻�̐��E�������Ă�����Ȃǂ����`�����Ă������Ǝv���Ă���B
�i���j
