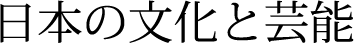
最近、続けて芝居の地方巡演に同行する機会があった。劇団民藝+無名塾の公演で奈良岡朋子・仲代達矢の二人が舞台で初顔合わせをし、三年がかりで全国の演劇鑑賞会を回った「ドライビング・ミス・デイジー」。もう一本は、左とん平が六本木の小さな劇場で初演をし、その評判が口コミで広がり、各地で回を重ねている和風ミュージカル「天切り松闇がたり」である。
東京にいると劇場の数の多さに驚くが、地方へ出てみると、それがいかに贅沢なことかが良くわかる。常設の「劇場」がある場所へ小一時間で出られるような地域は少なく、年に数回、その都市の文化センターや公民館へ回って来る芝居を待っているしかないのだ。いまどき芝居を泊りがけで観に行くというのは、相当に大変な仕事でよほどの芝居好きでなければできない。まして、このような時代だ、娯楽は最初に切り捨てられる対象となる。
マスコミもスポットを当てるのは東京や大阪などの大きな舞台が中心で、地方での演劇文化が置き去りにされているのは今に始まったことではない。しかし、その中で、先ほど挙げた芝居のように、コツコツと地方を回り、少しでも多くの観客に生の芝居を観てもらおうと努力をしている人々がいる。そこをキチンと評価するのが私の仕事の一つでもある。
こういう巡演はかなりのハードスケジュールだ。夜の芝居が終わり、深夜に近い時間に夜食をすませ、会場近郊のホテルに泊まる。みんな同じタイプの部屋だ。翌朝は朝食をすませ、決められた時間に指定の場所へ集合。次の公演地まで、バスか電車での移動となる。近い場合もあるが、バスで数時間という移動も当たり前だ。着くなり大道具の仕込みが始まり、楽屋では役の拵えが始まる。一週間に一日程度の休みはあれ、概ねこうしたスケジュールでの旅は、長ければ半年近くにも及ぶ。
奈良岡朋子、仲代達矢、左とん平。いずれも、テレビや舞台で顔の売れた名優だ。それが、まるでセールスに歩くかのように地方を回って芝居を見せる。よほどの情熱がなければできる話ではない。次にその場所をいつ訪れるか約束はできないから、まさに「一期一会」の旅である。土地によって観客の反応が違い、敏感に反応する場所もあれば、水を打ったように芝居を観ている土地もある。どの地域も「生の舞台」に渇望しており、迎える側の人々の熱意も高い。こうした瞬間に触れると、東京で惰性のように芝居をしている役者の横っ面を張り倒したくもなる。
丸三年を迎えるこの連載も、今回が最終回。毎月、一期一会のつもりで書いてきた原稿にお付き合いいただいた読者の皆様に、ただ、感謝。ご多幸をお祈りしてペンを置く。
日本の演劇シーンが大変な勢いで変化を遂げている。景気の変動もさることながら、観客の嗜好もより多様化し、多くのジャンルの舞台が数えきれないほどに増えた。今までにたびたび書いて来たが、演劇は時代と共に変容するものであり、それは当然のことだ。
東京・帝国劇場で2月、3月と堂本光一主演の「Endless SHOCK」で実に14万人を超える観客を集めている。この公演は2000年に始まった「MILLENNIUM SHOCK」以来今年で10年、観客総動員は120万人を超える。「菊田一夫演劇大賞」をも受賞しているこの舞台は、単なる「ブーム」としてとらえるには余りにも大きな現象であり、演劇界の一つの「水脈」となっているのは明らかだ。わずか21歳にして帝国劇場の史上最年少座長として話題になって以来、10年間大入り満員を続けているのは評価に値する。
「Show must go on」の精神に乗っ取りショービジネスの世界を描いているこの舞台は、ジャニー喜多川が身につけたショーマンシップのもとに構成されている。今回の舞台でもメインテーマとなっているこの言葉は、舞台に立つものすべてに通用するものだろう。
面白いもので、テレビで見る彼の姿と、舞台の姿は違うような気がする。媒体によって求められる役割の違いが理由だろうか、テレビでは陽気なトークで軽妙な明るさを見せる。その一方で、この舞台を観ていて感じた彼の生の魅力は、そこはかとなく漂う「愁い」やふとした瞬間に見せる「翳り」のような感覚だった。堂本光一の舞台には、「愁い」がある。それはマイナスイメージではなく、魅力なのだ。今のイケメンブームの中で、「愁い」が魅力となる俳優はそうはいない。それが堂本光一の色なのだ、と思う。
30歳になった彼が、3時間25分の舞台を、フライング、早替わり、和太鼓の演奏からイリュージョンまで、力の限りを見せる。若い役者のエネルギーが横溢した舞台に、劇場を埋めた若い女性客は、惜しみない拍手を送り、客席の体温の高さが伝わって来る。2ヶ月間で76ステージをこなすというのは、尋常のスケジュールではない。しかし、それでもなおチケットが一瞬にして売り切れるだけの素材の魅力とショーマンシップを、身に付けているからこそ、10年間の支持があるのだろう。
今回、堂本のたっての願いで共演している植草克秀がメンバーである「少年隊」が、昨年の夏でミュージカル「PLAYZONE」の23年間にわたる幕を閉じた。しかし、その後を受け継ぎ、また新たな形で魅せるこうした公演が、これからの若い観客を引っ張る大きな力であることは間違いないだろう。今の演劇界が模索するべき問題は、ここにあるのだ。
新年早々、不安なニュースばかりで、不透明な時代だ。演劇界とて、状況は変わらない。そんな中、東京・渋谷のシアターコクーンで「野田地図」が上演している「パイパー」。舞台を火星に置き、主宰の野田秀樹をはじめ、宮沢りえ、松たか子、橋爪功、北村有起哉、コンドルズなどの豪華なメンバーを揃えた話題の、かつ刺激的な舞台だ。
いろいろな感覚を持ったが、第一印象は、しばらくぶりに芝居が持つ同時代性を感じた、ということだ。プログラムの中で、作・演出・出演をこなす野田秀樹は、数字に追われる現代社会で、「千年かけて自滅していく幸せ」をこの芝居の中に見つけた、と語っている。
経済成長率、失業率、企業の年間売上、年間所得など、我々は実態のよすがとしている「数字」の幻の中で「幸福」を追い求めている。実感できる数字もできないものもあろうが、数字に振り回されているのは事実だ。
この芝居の舞台での火星は、地球からの移民たちが主人公だが、火星も絶滅寸前の危機にさらされている。それは、とうに地球が滅び、地球からの物資も途絶え、過酷な自然の中で疲弊仕切った結果なのだが、それは取りも直さず、今の地球の姿そのもである。
作者の野田秀樹は、そうした状況を、持ち前の才気煥発な言葉遊びを駆使し、時に笑いを交えながら、現在の我々のあり方や考え方を観客に突き付ける。幕間なしの2時間余りの芝居を一気に駆け抜ける印象があるが、原稿用紙200枚に及ぶ膨大な科白のやり取りの中で、今の我々が追い求める「幸福」の姿を浮き彫りにし、その姿が本当に正しいものなのか、という問題を我々に問うているのだ。
芝居と社会の同時代性を感じた、というのはこの部分だ。芝居に仮託された惨憺たる今の世のありさまを、我々はどう受け止めるのか。ある意味では、「厳しい」芝居だ。
その中で、橋爪功の手練れの芝居や、野田秀樹の俊敏さも見事だ。圧巻は、甲乙つけがたい松たか子と宮沢りえの速射砲のような科白のやり取りである。この二人の女優がお互いに全力でぶつかり合うシーンに、今の芝居が持っている情熱と力を感じた。
芝居が娯楽であることは言うまでもない。しかし、その娯楽を通して、今の世の中を客観視することもまた必要なのではないか。それが、芝居が持つ同時代性、ということなのだ。今の悲惨な社会情勢をありのままに受け止めるもよし、逆にこういう事態の中でもかすかな希望を持つことが人間の「業」であることを肯定し、明日へ向かうのも良いだろう。
すべてが破局へ向かうのかと思う幕切れに、荒野と化した火星に花が芽吹く。その数輪の黄色い花は、野田秀樹が観客に「もう少し頑張ろうよ」というエールを送っているような気がした。
