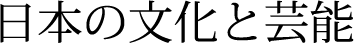
2009年11月10日、森繁久彌が96歳で長逝した。ここ数年間は、年齢や体調の問題もあり表立った芸能活動を控えていたが、昭和の一つの時代を築いた稀代の名優であったことは否定のしようがない。今の若い演劇ファンには馴染みのない役者かも知れないが、映画、テレビ、舞台、ラジオの他に、詩人、歌手など、多角的な煌めきを放った昭和を代表する役者である。
マスコミ的な言い方をすれば、「一つの時代の終焉」、あるいは「巨星堕つ」という見出しになるのだろうが、極端な言い方をすれば、そのエネルギッシュな仕事ぶりは、まさに「怪物」と言ってもよいほどであった。
森繁久彌という役者を語る際に、900回演じた「屋根の上のヴァイオリン弾き」をはずして語ることはできないだろう。日本中に大ブームを起こしたこの作品の評価は、今でも高いものがある。しかし、森繁久彌という役者を語るには、とてもそれだけではすまない。映画の「社長シリーズ」や「駅前シリーズ」で見せた喜劇人としての間の絶妙さも抜きにはできないし、抒情豊かな詩人としての才能も看過することはできない。30年ほど森繁久彌という役者の芝居を観て来たが、印象に残る芝居は、いくつもある。その中で、あまり話題にされることはないのだが、どうしても忘れ難い芝居がある。
昭和52年1月の日生劇場公演。「ナポリの王様」という、イタリアの喜劇が上演された。主演の森繁久彌、山岡久乃、一の宮あつ子、井上順、横山通乃(当時の芸名は横山道代)などが顔を揃え、お正月にふさわしいコメディだった。そこで森繁が演じたペテン師とも言える胡散臭い、それでいてどこか温かみのある芝居が忘れられない。当時中学生だった私は、お年玉の中から、奮発して二等席を買い、日生劇場の片隅で大笑いしたことを今でも鮮明に覚えている。誤解を恐れずに言えば、「社長シリーズ」の映画や他の喜劇に見られる、「インチキ臭い」とも思える「間」が、森繁久彌という役者の本質的な評価と言えるのかも知れない。
森繁がアドリブの名人で、それに困らされた共演者の数は多い。名は伏せるが、私も何人かの役者からその話を聴いた。本来であれば、台本に書かれていない科白を言うことは、作者に対して礼を失することになるし、芝居の「王道」ではないのかも知れない。しかし、即興で芝居の流れをそれることなく、絶妙のアドリブを入れることは、相当の腕がなくてはできないことでもある。私が想像するに、森繁のアドリブに対する感覚は、若かりし頃、新宿にあった「ムーラン・ルージュ」などで、当時は「軽演劇」と呼ばれていたコメディで容易には笑わぬ客を相手に舞台と客席が切り結んだ真剣勝負の中で生まれ、身についたものではなかったのだろうか。
アドリブに格があるかどうかは知らないが、森繁のアドリブは、今のテレビでちんぴらタレントが口から出まかせのように言っているアドリブとは桁が違う。同じアドリブとは言え、横綱相撲にも匹敵するものだった。「アドリブに横綱も幕下もあるものか」と言うなかれ、ここに、「芸」というものの凄みがあるのだ。その辺りがわかっていないタレントだの役者がいくら騒いだところで、到底相手にはなるまい。
これは森繁久彌に限ったことではないが、「名優」と呼ばれる人々は、少なからず修羅場を幾度も経験している。そうして観客に、あるいは演出家に鍛えられ、芸を身につけて来たのだ。金箔の厚みが違うのだ。だからこそ、名優と呼ばれる価値もあるというものだ。
芝居を観はじめてから、一体何人の名優と別れて来たことだろう。生老病死は世の習いとは言え、訃報に接するたびに「また一人…」という寂寥感をぬぐい去ることはできない。十一月十日、小春日和に、森繁久彌はその芸のすべてを持って、旅立ってしまった。昭和という時代を象徴する役者の一人であったことは誰も否定できまい。その寂寥感は、時を経るに従って大きくなる。今となっては、その謦咳に接することのできた幸せと、舞台の上と観客席で共有した時間を懐かしみ、惜しむばかりとなってしまった。大きな感動を残して。
合掌
先ごろ、秋の叙勲の発表があり、芸能の世界の人びとでは、文化勲章の桂米朝、坂田藤十郎をはじめ何人かがその栄誉に輝いた。勲章や褒章とは制度を異にする中に、「芸術院会員」というものがある。上野公園の中にある「日本藝術院」の会員で、会員の互選により会員の補充が行われるシステムだが、芸能の道を歩く人びとにとっては栄誉なことだ。
もう二十年以上も前のことだ。劇団「前進座」の五世河原崎国太郎と話をしていたら、ふと国太郎が真面目な顔で「芸術院会員になれないものかねぇ」と呟いた。私は一瞬、耳を疑った。左翼思想を持ち、かつては共産党へ集団入党した歴史を持つ前進座の役者は、当時は国が与える栄誉とは最も遠い位置にいたし、国太郎自身が、そうしたことを嫌う役者だったからだ。
不思議に思った私は、「なぜ芸術院会員になりたいんです?お客様の拍手が一番の宝物、とつねづねおっしゃっているでしょう」と質問をした。その折の、国太郎の答えが奮っていた。
「お前さん、知ってるかい?あれになるとね、国鉄のグリーン車の無料パスがもらえるんだよ。そのほかに年金もいただけるんだけど、あたしは劇団からお給金はいただいているから、国鉄のパスだけ、もらえないかねぇ」
「なぜ、そんなにパスがほしいんですか」
「ほら、うちの劇団は巡業が多いだろう。あたしは座の立場上、みんなでもってグリーン車に乗せてくれるけど、そのかかりだけだって大変なんだよ。あたしは、普通車でいいから、その国鉄のパスをくれれば、ずいぶん座も助かるだろう。だからほしいんだよ」
まだJRではなく「国鉄」の時代である。当時は国会議員も同様の特権を持っていたはずだ。しかし、巡業で使うのに劇団に負担をかけたくないから、国鉄の無料パスがほしい、という半分冗談交じりの国太郎の話は微笑ましかった。
こんなことを書いていたら、もう一人の人物を想い出した。直接のお付き合いはなかったので、直に聴いたわけではないが、彦六になって亡くなった噺家の林家正蔵の話だ。俗に「稲荷町の師匠」と呼ばれ、清貧の中に暮らしていた。私が知るのは晩年の高座だけだが、穏やかな顔をしていながらも若い頃はその正義感からか、ずいぶん喧嘩をしたらしい。あだ名の「とんがり」というのはそこから来たものだ。
その正蔵が、寄席へ出る時に、「割安だから」と地下鉄の定期券を買った。定期券は期間内であれば何度でも乗り降りできる便利さだが、正蔵は寄席へ出かける時しか使わない。「それじゃもったいない」と注進した弟子に、「何を言ってるんだ、寄席からもらったお足で買ったもんだ、寄席へ仕事で出かける時以外に使えるものか」と言ったそうだ。そう言えば、正蔵も熱心な共産党支持者だったが、二人の精神のつながりはそこではない、と私は想う。
国太郎と正蔵の微笑ましいエピソードをつないでいる一本の線、それは、「明治生まれの男の気骨」、である。
成果など、簡単に出るものではない。
歌舞伎に対抗する演劇としてのジャンル・新派ができて121年。立派な古典芸能である。いつ頃からだろうか、同じ古典芸能である歌舞伎の驚異的なブームとは裏腹に、長期低落傾向が続き、観客の離脱に歯止めが利かなくなった。時期を特定するのは難しいが、私の記憶にある限りでは昭和54年に初代の水谷八重子が亡くなったのが大きなダメージだった。それから数えてももう30年の間、新派は「自分たちのするべき芝居」の模索に悩み続けていた。人気漫画「はいからさんが通る」を舞台化して若い観客の動員を図ってみたり、歌舞伎の人気役者や杉村春子、山田五十鈴といった大女優のゲストを仰ぎ、新派の名狂言に何度目かの命を吹き込もうと苦心惨憺して来たが、なかなか思うようには行かなかった。
確かに、この時代に、いくら名作とは言え、泉鏡花の「婦系図」や「日本橋」ばかりでは観客の動員は難しいだろう。その一方で、先人たちが苦難の果てに残した珠玉の芝居を古くなったからと簡単に捨て去るわけにもゆかぬ。新派に関わる人々の多くは、新派の財産演目を活かすことと、今の時代の芝居との感覚の「ずれ」に悩んできたはずである。
しかし、ここ数本の新派の舞台を観ていて感じるのは、そうした長い暗闇にかすかな光が見えてきたことだ。今月の新橋演舞場の橋田壽賀子作、石井ふく子演出の「おんなの家」。水谷八重子、波乃久里子に沢田雅美が加わっての三姉妹の物語だ。観客は実によく反応し、笑っている。実はこの作品、昭和49年から平成5年までの長きにわたって、TBSの東芝日曜劇場で放送され、好評を博したドラマが元になっている。杉村春子、山岡久乃、奈良岡朋子という三人の名優を三姉妹に充て、「花舎」という炉端焼き屋を舞台にした笑いあり涙ありのホームドラマで、当初の好評を受けてシリーズ化されたものだ。当時、とても楽しみに観た記憶は今も鮮烈である。しかし、これをそのままというのはどだい無理な話で、主役の三人のうち健在なのは奈良岡朋子一人になってしまった。また、当時の時代感覚と今の相違もあろう。とは言え、こうして評判の良かったものを、今の新派のメンバーに当てて書き直し、時代も多少ずらして演じる。今回はこの試みが見事に成功した。テレビで描かれていた三姉妹それぞれの性格が今回の八重子、久里子、沢田の三人にぴたりとはまったことも良かった。この芝居で、「おんなの家」という作品が蘇り、新たなる命を吹き込まれたのである。これは大いに喜ぶべきことだ。
来年には有吉佐和子原作の「三婆」が同じく新橋演舞場で上演される予定である。こちらは、昭和48年に芸術座で新派の市川翠扇、劇団民藝の北林谷栄、東宝の一の宮あつ子で初演され、大好評を博した芝居だ。以来、配役を変えては繰り返し上演されてきたが、今度は新派のメンバーで演じる。これも多少の脚本の改訂は必要になるだろうが、商業演劇の名作が蘇ることに違いはない。考えてみれば、新派の「婦系図」にしても「日本橋」にしても、こうして配役を変え、連綿と受け継がれてきたものだ。今、こうして2,30年前の名作を掘り起こし、新しい酒を注ぐことによって、新派の今後の一つの方向性が見えてきた。もちろん、こうしたことばかりが新派の仕事ではあるまい。先人が遺した財産を、現代の観客が納得し、共感できるような形で上演する大きな使命は変わらない。しかし、今までの試行錯誤が観客の支持という一番ありがたい形で実り始めたことは喜んで良いと思う。
三越劇場では「太夫さん」や「女将」などの新派の財産演目や、杉村春子の「女の一生」に挑戦するなど新しい試みで新派公演も根付いてきた。ここでいきなり新派がブームになるとは思えないし、そんなことになっても困る。ただ、何度も離合集散を繰り返し、幾多の危機に直面してきた新派が、ここ数十年の中で最大の危機をどうやら乗り切ったような感覚が見えた。これは、評論家としても観客としても非常に喜ばしいことである。とは言え、八重子や久里子の跡を追いかける女優の育成や、若手の男優の育成、脇役の充実など、課題はまだまだ多く、手放しで喜んでいるわけにはいかない。ただ、同じ荷物を背負っていても、先の見えない真っ暗闇を歩くのと、いくらかの光でもトンネルの出口が見え始めたのとでは大きく心象が違うだろう。このチャンスを、うまく活かしてほしいものだ。
世を挙げての落語ブームである。古典芸能がこうして何十年かに一度のブームで今まで命脈を保ってきた、その底力は凄いものだ。こうしてブームが起きると、「迷人」が続出し、「毒演会」が盛んになる。しかし、玉石混交でなければブームなど起きないのだから、そこに目くじらを立てるつもりはない。自分の好みに合うのは誰か、は、観客が自分の眼と耳で判断すれば良いだけの話だ。
ブームが起きると、便乗していろいろなものが商売になる。これも当然のことで、こうしたチャンスに、今まで眠っていた貴重なものが日の目を見る可能性もあり、市場が活性化するのは良いことだ。また、今まで落語に縁も興味もなかった人々が、わが国が誇る話芸に関心を持ってくれるツールが増えるのも悪い話ではない。しかし、歴史と見識を持った大きな出版社がそれに乗じて荒っぽい仕事をしてはいけないだろう。
小学館が、CD付きのムック「昭和の落語名人 決定版」なるシリーズを発行している。タイトル通り、志ん生、文楽、円生をはじめとして、昭和の落語黄金期を創った噺家たちのCDが付いているのは、落語ファンには嬉しいことだ。しかし、その中の何席かの噺を聴いて、その出来の悪さにがっかりした。噺家が悪いのではない、収録されている噺の出来が悪いのだ。もしも、本人が生きていたら、絶対にCD化することなど許さなかったであろうほどにまずい。これは問題である。
何が問題なのか。ちっとも夏の暑さを感じさせない「船徳」を聴き、「ああ、これが名人桂文楽の『船徳』か」と想い、噺がもたついてしまう林家正蔵(彦六)の「中村仲蔵」を聴き、「これがあの有名な『中村仲蔵』か」と想われることが問題なのだ。今はこの二人を例に挙げたが、油が乗り切っている頃の二人の同じ噺を聴くと、天と地ほども出来が違う。いかに名人上手と言え、その時々によって噺に出来不出来があるのは当たり前のことだ。その中で、「これぞ」というものを選りすぐって聴かせるのであればまだ納得もする。しかし、そうしたものの多くはすでに何らかの形で発売されている。その中で新機軸を打ち出そうとすれば「初出音源!」などと銘打って世に出すしか方法がないのだろう。
考えてみれば、今まで商品化されなかったということは、その商品価値が決して満足のゆくものではない、という判断がどこかにあったからだ。それは「これは、あとに残す噺じゃありません」という噺家の矜持だろう。名人であればあるほど自分の芸には厳しく、ハードルは高い。そのルールを無視して、むやみやたらに「これが名人の落語です」という売り方をされたのでは、お墓の中で苦情が言えない本人たちが気の毒である。「俺の芸はあんなものじゃない!」と切歯扼腕している噺家が何人もいることだろう。もちろん、出版社側は遺族や関係者を通じて権利関係は処理しているだろうが、そこには本人の意思はない。
有名な作家が没後、「未発表の原稿発見!」というニュースとともに、それが出版されることがある。しかし、未発表だった理由の中には、本人がその作品を世に問うことを潔しとせずに「没」にした原稿も数多いはずだ。いかに高名な作家であれ、没原稿がないわけはない。それを捨てずにたまたま残っていたものが「幻の名作!」と売りに出されるようなものだ。どこの世界に没原稿を売りに出されて喜ぶ作家がいるものか。
せっかく落語のブームが起きている。落語の世界に住む人々の魅力の一つは、おっちょこちょいや間抜けはたくさんいても、根っからの悪人は出て来ないことだ。その落語を扱う人々が落語のイメージを汚してしまっては何にもならないだろう。小学館とて商売だ、道楽で本を出しているわけではない。しかし、売れれば何でもいい、という同業他社の姿勢が、日本の出版や文化を駄目にしてきた一つの要因であることを、そろそろ認める時期ではないのだろうか。
