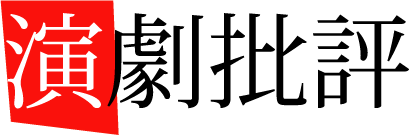

Endless Shock 2010.02 帝国劇場
2000年の初演以来、今年で11年目となる。「Show must go on」をテーマに、毎年いろいろな部分を変えながら、一つの芝居が進化をたどっている舞台だ。バックステージ物とも言えるジャンルの芝居で、堂本光一扮する「コウイチ」がショーの世界で多くの困難にぶつかりながら進んで行くという設定は当初から変わっていない。「継続は力なり」というが、31歳になったばかりの若さで、帝国劇場を11年間満員にする力はたいしたものだ。
今回の舞台を観ていて感じたことが幾つかある。まず、11年間演じていながらスピード感が全く衰えていないこと。いくら若いとは言え、今年について言えば2月、3月、7月と三カ月で合計100ステージを演じることになる。ハードスケジュールの合間を縫っての稽古で、毎年新しい要素を加えながらも舞台のテンポが落ちずにいることは評価して良いだろう。もう一つ感じたのは、堂本光一が去年のステージに比べて格段に逞しさを増したことだ。格闘技などのスポーツ選手のような体格ではないながらも、あの華奢な身体のどこにあんなにエネルギーがあるのだろうと思って今までの舞台を観ていたが、身体が一回り大きくなっているような気がした。具体的にどんなトレーニングを積んで来たのかは知らないが、ハードな舞台をこなすために、努力を重ねた結果であろう。この事実一つを取ってみても、まさに「Show must go on」のために他ならない。
昨年、ある雑誌に、彼の個性は「愁い」と「翳り」にその真骨頂がある、という内容の記事を書いた。その感覚は今も変わっていないが、今回の舞台を観ていて、ふとある歴史上の人物に似た感覚を覚えた。誰もが知っているが実像は観たことがない、悲劇的な歴史のヒーロー「源義経」である。「義経」は同じジャニーズ事務所の滝沢秀明が演じているが、どちらが良い悪いという比較検討の問題ではない。堂本光一が感じさせるものは大袈裟に言えば、悲劇的な「運命」とも「陰」とも言えるべきものを身にまとっているものの魅力だ。ある場面では、京都の五条橋で弁慶を相手に軽々と立ち回った白皙の美少年の面差しを感じさせる。その一方では、来るべき悲劇の予感をまといながらも果敢に運命に立ち向かう武将としての義経の側面をも見せる。義経の短い生涯の中でもいろいろな顔があるわけで、我々が「伝説」として知っている幾つかの顔、場面が今回の舞台から感じ取れた。悲運の武将と堂本光一の姿を重ね合わせることがどういう意味を持つのか、それが意識的に行われているものなのか無意識に彼が醸し出すものなのかはわからない。ただ、それが変にギラギラと男くさくならない「淡さ」とでも言うべき二面性が、彼の魅力であるのかも知れない。
さまざまなイリュージョンやフライング、和太鼓の演奏、シェイクスピアの「ハムレット」や「ロミオとジュリエット」の一場面など、観客をいかに多くの方法で楽しませるか、という舞台の創り方は、今までにも何度か書いて来たがショーマン・シップを知りつくしたジャニー喜多川の薫陶によるものだろう。今、景気の悪化と共に演劇界も厳しい状況に置かれている。その中で、劇場にいる数時間、いかに観客を満足させるかという、一番シンプルで重要なところに力点を置いた舞台には、それなりの価値がある。ジャニーズのファンに熱狂的な人々が多いとは言え、「満足」が得られなければ次へはつながらないだろう。そのために努力を惜しまないカンパニーの姿が観客に響き、それが11年続いている原因の一つである。
先輩に当たる少年隊の植草克秀が劇場のオーナー役で出演し、後輩の屋良朝幸がライバルで出演している。先輩を立てながら同時に後輩を育てて行くという器量は、立派な座長である。「Endless」と銘を打っている以上、まだしばらくはこうした公演形態は続くのだろう。その中でどう次の年へ脱皮を繰り返してゆくのか、そこに興味がある。

「慙紅葉汗顔見勢」 2010.01 新橋演舞場
昭和五十四年に、市川猿之助がこの芝居を復活した折に、一人で十役を早替わりで演じ、しかも宙乗りまであるというので大きな話題になった。実際に舞台を観て、それまで観ていた日本の伝統芸能の一つの殻を破ったような衝撃を受けたのを今でもはっきり覚えている。残念なことに病に倒れた猿之助が、この十八番を市川海老蔵に譲り、新橋演舞場の花形歌舞伎で、猿之助に負けず劣らずの奮闘を見せている。
市川海老蔵という役者を観ていて、ここしばらくの間に、大きな変化を遂げたように感じる。歌舞伎の宗家としての市川家の次の世代を担うべき者としての大きな自覚と厳しい覚悟、それが感じられるようになった。このことは他の芝居でも書いたが、それがどんどん顕著になっている。この公演にしても、猿之助一門を束ねる市川右近や中村獅童、それに市川海老蔵というメンバーで、本来であれば「無人芝居」と言われても仕方がない。しかし、観客は大入りで、若いエネルギーが横溢する歌舞伎を楽しんでいる。市川海老蔵という役者が放つカリスマ性に他ならないだろう。
この芝居は、「伽羅先代萩」のお家騒動を核として、そこに累と与右衛門、土手の道哲など、他の芝居でもお馴染みの役が登場する。海老蔵は立役の人であり、十役の中には政岡や累などの女形が精いっぱい取り組んでも難しい役も多い。そうした役の一つ一つの細かな点を取り上げて行けば、食い足りない部分は確かに多い。その一方で、政岡などは想像していたよりも良い出来であった、という意外性もあった。また、仁木弾正の宙乗りでの引っ込みには迫力が感じられた。若いながらも、久し振りに仁木弾正を演じられる役者が出た、という想いもある。
演技術、という観点で考えれば、同世代の役者でも海老蔵よりも技巧的に優れた役者は他にもいる。それが全般的ではなくとも、役によっては明らかに差違を感じる役者もいる。しかし、そうしたものを超えてしまう「空気」を、海老蔵が身にまとっていることは否定できない事実でもある。この稿を書きながら、今の団十郎が襲名した時の歌舞伎座のことを想い出している。団十郎も、若い頃からさんざん科白の難を指摘された役者だった。同世代の亡くなった辰之助の歯切れの良さなどと比較されもした。しかし、団十郎襲名披露の折に演じた「助六」で、花道から出て傘を広げた瞬間に、歌舞伎座の空気がぱっと華やぎ、明るくなったような気分になったのを鮮明に覚えている。俗に、「華のある役者」と言うが、団十郎の「助六」にそれを感じた。同様のことが、今の海老蔵にも言えるのだ。科白も決して巧みとは言えないし、まだまだ勉強の余地がある。しかし、身にまとっている「華」は確実に父譲りのもので、もっと言えば、「市川団十郎家」に伝わる空気とも言えるかも知れない。
彼が、何をきっかけに本気で歌舞伎に取り組もうと考えたのか、私は知らない。しかし、今月の舞台では明らかに彼が「歌舞伎」という巨大なエネルギーを持った芝居と格闘し、闘っている姿があった。それは、この芝居が肉体的、時間的に膨大なエネルギーを必要とするものだから、という意味ではない。彼が、歌舞伎役者として先輩の歌舞伎を引き受け、それにまさに「体当たり」でぶつかっている姿に共感を覚えたのである。それぞれの役の巧拙や性根の捉え方を批評する方法もあるが、この芝居に関して言えば、それはあまり意味をなさない。むしろ、一本の芝居に彼がどういう姿勢で取り組み、それがどこで見て取れるか、の方が重要であろう。そういう意味では、市川海老蔵が歌舞伎に対して大きく踏み出したここしばらくの舞台の中では一つの象徴とも言えるべき舞台であったことは間違いない。今後の歌舞伎を牽引していく世代の役者の一人として、彼がこれからどういう仕事を成して行くのか、そこに興味がある。

やみ夜 2010.01 シアターχ
聴きなれないタイトルだが、樋口一葉の作品だ。しかし、「たけくらべ」や「にごりえ」、「十三夜」のように、我々が一般教養として抱いている樋口一葉の清楚で可憐な世界を期待して劇場へ出かけると、おそらく度肝を抜かれるだろう。この作品には毒がある。タイトルの「やみ夜」に象徴されるような毒だ。しかし、その毒は「美毒」とも言えるもので、美しい明治の文体で綴られると、白昼の光の中で咲く花のような輝きを見せる。この作品を二十三歳で発表していたことにまず驚かされる。明治の人々がいかに大人であり、情報にまみれた現代を生きる我々がいかに表層的で幼稚なものしか持ち合わせていないかを、突きつけられた想いである。明治時代から見れば、新宿だの渋谷のように二十四時間人通りが絶えず電気の消えない街などは想像もつかず、また、我々から見れば、明治の夜はまさに「やみ夜」であろう。しかし、回りが暗いからこそ、かそけき灯りが美しく見えるのだ、ということを我々は忘れている。この舞台を観て、そんな印象を抱いた。
ドイツで活躍中の演出家・渡邊和子の熱望により、この作品が上演されたと聴いたが、出演者はわずかに四人。芝居も一時間半に満たない、いわば小品である。しかし、実を言えば登場人物は少なければ少ないほど、上演時間は短いほど難しいものだ。役者も演出家も、逃げ場がないからだ。横山通乃、塩野谷正幸、重田千穂子、三宅右矩と、大ベテランから20代までの四人が演じる世界は、美しくもおどろおどろしい。零落して逼塞している美しい女性・お蘭と、彼女に仕える佐助、おそよ。そこに直次郎という青年が交通事故に遭い、助けられて運び込まれて来る。お蘭の屋敷にいついた直次郎はその気高き美貌に憧れるのだが、何とお蘭は、直次郎をテロリストにしてしまう…こういう作品が、明治期に、樋口一葉の手によって描かれていたのが面白い。現実に疲れ、その中でも創作活動に専念した一葉の、「見果てぬ夢」だったのだろうか。
舞台には残念な点がいくつかある。幕が開いてから30分近く、舞台には必要以外はわずかな灯りしか差さない。時として役者の顔も判別しがたいほどで、これはいかにも勿体ない。闇夜であればこそ、白昼の眩しいような光の中で繰り広げられ、暴かれる人の心のドラマを観たかった。そこにこそ、「暗く深い闇」が口を開けているはずだ。また、幕切れに現代へ結びつけるために、映像が挟まれる。ここで舞台が十分近く伸びてしまうが、この場面はなくもがな、で、もっと象徴的に終わらせることもできるし、工夫の余地は充分にあるところだ。最近、こうした現代的な映像を使う舞台が割に多いが、私はこの手法は採らない。なぜなら、劇場を一歩出れば、どこにも溢れかえっている「日常」だからだ。せっかく明治の「非日常」の世界へタイム・スリップさせてくれたのであれば、そのままの余韻を味わいたかった。
この舞台で一番成功だったのは、おかしな「脚色」をせずに、原文を尊重し、あくまでも「構成」としたところだろう。それによって、役者が発する明治の文体の美しさが生きた。これは成功である。特に、横山通乃の朗唱術の美しさには驚いた。江戸でも大正でもなく、明らかに「明治の言葉」である。一葉の文章が持つ骨太な美しさ、とでも言うべきものがくっきりと描き出せた。巷で流行っている陳腐な朗読劇など、どこかへ飛んでしまうほどの技術だ。他の三人と比べても、明らかに群を抜いている。役者の教養というのであろう。その中で、一瞬伝法な口調に切り替わるところも見事だった。役者が科白を朗唱する、ということの大事さを、演じる方はもとより観客も疎かにしがちな時代にあって、これは評価すべきことだ。もう一つは、衣裳と装置の工夫が活きている。小劇場の芝居にありがちな、発想だけで実が伴わない貧相なものではなく、奇抜な発想がキチンと活きている。
流山児★事務所の塩野谷正幸、テアトルエコーの重田千穂子、和泉流狂言師の三宅右矩という個性的なメンバーを集めたのも面白い。所属や携わっている分野など、どこにも共通点のない役者達だが、強いて言えば役者としての体臭に共通点があると言えるだろう。それぞれの世代でアヴァンギャルドを生きている役者を選んで来たかのような印象を受けた。塩野谷には安定感があり、重田には突飛な部分がある。そういう個性で言えば、若い三宅が一番おとなしく、まともに見えるのも面白い。
勝手なことを言えば、芝居は荒唐無稽の一言に尽きる。一方、小説は「文学」だ。その二つの間を漂っているのがこの作品のような気がする。どちらか一方に偏ることなく、二つの交差するテリトリーを往来するところに、この舞台の面白さがあるのだろう。今まで、シアターχではあまりよその劇場では取り上げない芝居を演じて来た。その分、当たりはずれも大きかったが、今回の舞台は「当たり」に属すると言えよう。

新橋演舞場初春花形歌舞伎 昼の部 2010.01 新橋演舞場
今年の四月に改築のため閉館が決まっている歌舞伎座とそろってお正月に歌舞伎の幕が開き、賑やかなことだ。こちらは海老蔵、右近、獅童などの若手を中心にした花形歌舞伎。別れを惜しむ歌舞伎座に負けないぐらいの大入りである。昼の部は「寿曽我対面」「黒塚」「春興鏡獅子」と三本が並ぶ。「黒塚」と「鏡獅子」の二本が共に長唄の舞踊で、いささか狂言が「つく」嫌いはあるものの、若い才能が奮闘している。
「寿曽我対面」。今まで、昭和の名優をはじめ幾多の大幹部たちが演じて来た舞台を想うと、舞台に隙間風が吹くように感じるが、過去のものばかりを追っていても仕方があるまい。現に、今この舞台で演じている若い役者たちが、今後の歌舞伎を担っていくのである。それを、芸歴何十年というベテランと比較をして、細かいことをあげつらってもさして意味はないだろう。もちろん、大先輩が工夫を重ねて今まで築いて来た芸を学ぶ必要は絶対にある。その上で、市川猿之助一門が多いこの一座で、これからの歌舞伎をどう考えるのか、彼らの視点でどう創って行くのか、そこにこの花形歌舞伎の若い一座の意味があるのだろう。工藤祐経は右近。科白がいささか籠もり気味に聞こえるのが難点である。口跡は悪くないし、メンバーの中では適役なのだから、それを活かした方が良かっただろう。獅童の曽我五郎、役の勢いは買うが、そこの部分だけが先行気味で、見得の形が綺麗に決まらないことや、科白が聞き取りにくいところがある。こうした問題を、一つずつクリアしてゆくことが今後の課題だろう。笑也の曽我十郎は、女形の部分が勝ちすぎてしまい、もう少しきっぱりしたところが欲しい。猿弥の小林朝比奈が、仁に合っている。お正月にはつき物のめでたい芝居で昼の幕開きは悪くない。
「黒塚」。右近が初役で勤める師匠・猿之助の十八番である。猿之助が病に倒れて以来、観ることができなかったものだけに、愛弟子の右近が猿之助の当たり役をどう継承するか、興味のあるところだ。結果を先に言えば、初役ながら上々の出来である。「猿之助写し」とでも言おうか、相当細かい部分まで猿之助の風を漂わせており、この演目に賭けている意気込みがよくわかる。歌舞伎の世界では、先輩に教えてもらった芝居は、まずはその通りに演じ、次回からは自分なりの工夫を加えるのが礼儀という習慣がある。そういう意味では、猿之助の芸の多くを引き継ごうという意志が良く現われた「黒塚」だった。ただ、難を言えば、張り切りすぎて元気一杯のあまり、時として「老女岩手」から離れてしまい、「男」になってしまう部分が散見できた。これは、今後の課題だろう。身体が良く動くので迫力があるが、その分、抑制と躍動のメリハリをもっときちんと付ければ、さらに良いものになっただろう。師匠から弟子へ、こうした形で名作が継承され、やがて右近が自分なりの「黒塚」を創り上げる日が来るだろう。そのスタートラインとして、という意味ではまずまずだった。
市川海老蔵の「春興鏡獅子」。私が思うには、この舞踊の眼目は、勇壮な獅子の後ジテよりも、小姓弥生で踊る前ジテの方が遥かに難しい。そこに一抹の不安はあったが、予想していたよりも良い出来だった。体格が良いだけに女形はいささか、とも思ったが、時折振りが大ぶりになる他は、これと言った傷もなく演じおおせた。二枚扇のくだりなども、扇の扱いに変に気を取られずに、さらりと見せるのが良い。後ジテの獅子の精の迫力は、まさに海老蔵の面目躍如と言ったところで、華麗で勇壮な獅子の踊りを見せる。獅子の毛を振る所作や舞台を大きく使って踊る獅子の精に、満場は喝采である。ずいぶん前に、父の市川団十郎が踊った「鏡獅子」を想い出した。
私が、今回の舞台で感じたのは、市川海老蔵の「覚悟」である。夜の部では、市川猿之助の当たり役で人気狂言の「伊達の十役」を演じている。こちらはまだ観ていないので批評はできないものの、市川猿之助一門と一緒に一カ月興行の幕を開け、自らがリーダーシップを取って今までにないものに挑戦して行こうという意気込みに、彼が今後歌舞伎とどう対峙してゆくのか、という決意と覚悟を観た想いである。芝居の細かな点をあげつらえば、まだまだ足りない部分はある。それは先の右近と同じことで、これから自分が勉強をし、身につけてゆけば良いだけの話だ。
昨年の七月の歌舞伎座で、玉三郎と共に猿之助一門との奮闘公演を行ったが、彼が歌舞伎の宗家・市川団十郎家の後を継ぐ役者として、真剣に歌舞伎と対峙し、考えていることがその公演でもわかった。もちろん、いくら海老蔵が覚悟を決めたところで歌舞伎は一人ではできるものではない。しかし、今の海老蔵には同世代で切磋琢磨できる染五郎や愛之助、孝太郎や菊之助などの好敵手があちこちにいる。それに加えて、父の団十郎をはじめ、幸四郎、菊五郎、仁左衛門、勘三郎など、彼がこれから演じるであろう役を演じて来た先輩達も健在で現在の歌舞伎界を懸命に牽引している。そういう意味では、今が、またとない修行のチャンスだ。この機会を活かして、次の世代の歌舞伎を牽引するメンバーとしての活躍を期待したい。

細雪 2010.01 明治座
谷崎潤一郎の名作「細雪」。大阪・船場の旧家の四姉妹を中心に絢爛豪華に、また時代の変わり目と共に描いた名作は、舞台化されて四十四年になる。今回で三十二回目の公演となり、その間にキャストを何回も変えながら、上演回数が千三百回に達するという。和物の大劇場演劇の作品で、こういう上演の形態を続けている作品も珍しいとも言えるだろう。「放浪記」の森光子のように、単独主演という形ではなく、ある時期が来るとメインの四姉妹を変えて新たなキャスティングで上演をする。顔ぶれが変わらないことに安心感を覚える芝居もあれば、顔ぶれが変わり新鮮な感覚で観られる芝居もある、ということだ。
今回四姉妹を演じるのは高橋惠子、賀来千賀子、紺野美沙子、藤谷美紀。この顔ぶれでの上演は今回が初めてとなる。私がこの芝居を初めて観たのは昭和五十九年の東京宝塚劇場で、四姉妹は淡島千景、新珠三千代、多岐川裕美、桜田淳子だった。それから二十六年の間に、十一組の四姉妹がこの芝居を演じている。煩雑になるのでそのメンバーを列挙することはしないが、東宝が生み出した芝居のうち、立派な古典の一つになったと言えよう。
昭和十二年から十四年にかけて、江戸時代から続く大阪・船場の木綿問屋・蒔岡商店の没落と変遷を描いたこの芝居、どこかチェーホフの「桜の園」を思わせる。原作者の谷崎の頭の中に「桜の園」があったかどうか知らないが、芝居の重要なモチーフとなるのも大きな桜である。もっとも、谷崎がそんな短絡的な発想でこの作品を書いたとは思えない。昔から歌舞伎とシェイクスピアが対比されるように、そうしたものが「作家の運命」の中にはあるのかも知れない。
この芝居を観るたびに感じるのは、四姉妹が実に巧みに描き分けられていることだ。時代遅れと言われようが船場の旧家の誇りを第一に生きる長女の鶴子、一番バランスが取れている次女の幸子、いかにも旧家のお嬢様育ちの雪子、末っ子でおちゃっぴいの妙子。この四人がそれぞれに問題を抱え、繰り広げていくある意味大時代なホームドラマは、今はもう壊滅状態に近い「家制度」がまだ厳然と残っていた時代のものである。それを、単に「古き良き時代」であるとひとくくりにすることはできないものの、こういう時代の感覚が、かつての日本に存在していたことを考えると、わずか七十年という時間の中での日本のいろいろな意味での劇的な変化を感じざるを得ない。この芝居が指示され続けているのは、実際の体験は持たないまでも、そうした時代に対する観客のノスタルジックな想いの一部や、緩やかに時間が流れていた時代への憧れなどの感情がないまぜになって投影されているからではないだろうか。
この芝居の見せ場は、美女の四姉妹が見せる豪華な衣装である。今は、和服の展示会でもなければ目にすることのできない美しく、品のある和服姿は、観客のどよめきを誘う。美女がまさに「妍を競う」ばかりの艶やかさは、この芝居の大きな見どころだ。特に幕切れ、満開の桜の中、晴れ着を着て歩く四人の姿には観客からため息がもれていた。いかにも「お芝居を観た」という気にさせる豪華さである。ただ、気になったのは舞台装置の重厚感がいささか薄れて来て、船場の旧家の古色蒼然とした味わいや芦屋の邸宅の重厚感が今一つ伝わって来ないこと、もう一つは、戦前の船場の言葉とは思えない、現代の言葉で話している役者がいたことだ。テレビの時代劇などでも、目を閉じて聴いていると全く現代の科白に聞こえることがしばしばあるが、個々の役者の科白の調子や時代色がだんだん希薄になっているのは否めない。
今回が四回目となる鶴子の高橋惠子が、古臭く、誇り高い船場の御寮人を、わざとらしくなる手前でキチンと止めて演じている。蒔岡家という旧家の象徴の一つでもある桜の大木と鶴子自身が重なるような印象を与えた。今回が五回目となる三女の紺野美沙子が次いでいい。役の雰囲気に合ったおっとりした空気を身にまとっているのが良い。四女の妙子に恋焦がれる「啓ぼん」の太川陽介、啓ぼんの元の使用人の板倉の新藤栄作、この二人はここ十年ほど変わっていないが、すっかり役のイメージを作り上げた。橋爪淳の品の良さもこの作品に良くなじんでいる。新陳代謝する女優と固定化する男優、どちらの方法がより適切なのか、は観客の判断だろう。
時代の変遷のスピードが異常に早い中で、変わらないものもあれば、やむを得ず変わるものもある。変わるものに対しては懐古や想い出が美しくつきまとっている。「細雪」は決して単なる懐古趣味によるものではなく、原作にどっしりと描かれている「時代に遅れながらも生きている人々」の姿がある。だからこそ、半世紀に近い間繰り返し上演されるのだろう。作品の魅力、というものを改めて感じさせる芝居である。

フロスト/ニクソン 2009.11 銀河劇場
実在の人物や事件を舞台化することの難しさは今までに多くの芝居が語っている。ウォーターゲート事件でアメリカ大統領の辞任を余儀なくされたニクソンに対し、その真実はどこにあったのかを執拗に追求していくインタビュアー。日本ではお目にかかれない光景だが、海外のこうしたインタビューの追及にはすさまじいものを感じることがある。ニクソンやフロストが実際の人物に似ているかどうか、よりも、この芝居では二人の駆け引きがどう観客に伝えられるか、そこが肝になるだろう。
インタビュアーのフロストに仲村トオル。ニクソンに北大路欣也。舞台では「異色」とも言える組み合わせのようだが、今回はこの二人で面白い化学反応を起こしたとも言える。膨大な科白のやり取りで、お互いがグイグイと引っ張りっこをしてゆく芝居の醍醐味がある。休憩なしで1時間50分のうち、前半は脚本がいささか冗長な感覚があるが、後半に二人のインタビューになると、芝居の持つエネルギーが膨らんでゆくのが良くわかる。
仲村トオルという役者。テレビや映画では人気の顔だが、正直なところ、舞台の芝居は特筆するほどに巧みだとは思えない。時として科白が一本調子になる部分もあるし、役の「肚」が浅い部分は否定できない。しかし、不思議なことに、芝居を観ているうちに、いつの間にか仲村トオルの世界に引き込まれている自分がそこにいる。これは、彼の個性が持っている魅力だろう。もっと舞台での芝居を鍛え、個性にテクニックが加われば、良い舞台役者になるだろう。
対する北大路欣也のニクソン。フロストが繰り出す追求の矛先をかわし、のらりくらりと交わす老獪な政治家のさまが見事なものだ。北大路欣也と言えば「時代劇の大御所」というイメージがあるが、新しい境地の発見だ。年齢に関係のない役者の挑戦が刺激的な舞台を生んだ一例である。今の時期にこうした翻訳劇に出会うというのは、役者としてのある種の運命かもしれない。「時代劇の役者」としてしか観ていなかったプロデューサーの側にも責任はあるが、よくこの膨大な科白劇に挑戦をしたものだ、と感嘆した。
仲村トオルと北大路欣也のやり取りを観ていて感じたことがある。海外の芝居でありながら日本の歌舞伎などに象徴される「肚芸」だ。例えていわば、「忠臣蔵」で、真正面から切り込んで来る一本気な仲村トオルが浅野内匠守、それを泰然自若と腹で受ける北大路欣也が吉良上野介、という図式である。もちろんそっくりそのままあてはまるものではないが、いわゆる「新劇」と呼ばれる分野の芝居において、そうした感覚を覚えるのは面白いことだ。それほどに二人のやり取りが緊密な、切迫したものであった、ということだ。もっとも、この勝負は北大路の横綱相撲で、ストーリーはともかくも演技術という点で言えば、北大路に軍配が上がった。年功を積んだ役者の芸が光芒を放つのはこういう時だ。その重さや貫録、間など、記録にならないものが「芸」なのだと、改めて感じる。
ただ、1時間50分の芝居の中でこの盛り上がりに達するまでの運びに、いささかもどかしいものを感じる。上演台本と演出を受け持った鈴木勝秀に一考を促したいところだ。客席のライトを切り替えることで、観客の意識を変える演出方法は面白いものの、時にそれを「うるさい」と思う瞬間がある。
二人を囲む役者に佐藤アツヒロ、安原義人、谷田歩ら。佐藤アツヒロが芝居の進行係とも言うべき役どころである。ジャニーズ事務所の中に舞台で活躍する人は多いが、彼の舞台に対する視線には独特のものを感じる。安原義人はコメディの老舗、テアトル・エコーで長年鍛えられた安心感がある。
テレビでは見られる顔合わせでも、それを生の舞台で観る、ということ。また、新たな作品を生み出す力。芝居が持っている面白さはここにある。昨今、不況が長引き、芝居どころではない、という声もあるが、こういう時代にこそ良い芝居を観たいものだ。今回の舞台は、家に寝転がってくだらない芸能人の馬鹿笑いを観ているよりも遥かに価値がある。舞台との出会いは一瞬だが、想い出は何十年と持つものだ。そこに、チケット代金の価値もあるのだ、と言えよう。
アメリカなら「フロスト/ニクソン」だが、宮内庁を恫喝した傍若無人極まりない小沢一郎と、法律で制度化する前に日本で最初に「お母様から子ども手当」を受給していた鳩山総理大臣辺りを主人公にした芝居を創るぐらいの勢いが日本の芝居にも欲しいものだ。もっとも、それでは茶番にしかなるまいが。
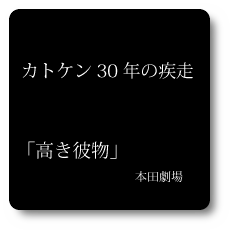
加藤健一事務所が30周年記念公演の一環として、マキノノゾミの「高き彼物」を上演している。カトケンにしては珍しい脚本を選んだものだと思う。過去に繰り返し上演し、高い評価を得ている作品はいくつもあるが、30周年の記念公演では過去に好評だった作品を演じるのではなく、新作を立て続けに上演するのだと言う。カトケンの30年は、まだ過去を振り返るものではなく、今後の疾走に向かっての通過点である、という意味なのだろう。
昭和53年の静岡を舞台に、一軒の家で繰り広げられる家族のドラマ、と言ってしまえば簡単だが、ディテールに作者のこだわりを見せながら、大詰めに向かって舞台を盛り上げ、収斂させてゆくマキノノゾミの脚本は緻密である。一幕65分、二幕65分という上演時間のバランスも悪くないが、一本の芝居の中に重い場面、明るい場面を巧みに取り交ぜて、ドラマは進んでゆく。いささか偶然のこじつけが目につくところもあるが、相対的には家族のありように幾つもの方向からライトを浴びせ、登場人物の姿を炙り出して行く。
加藤健一を中心に、小泉今日子、滝田裕介という個性的なメンバーでの舞台、今まで好んで取り上げて来たスピーディなコメディとは趣を異にしている。そうした芝居だけが加藤健一の本領ではないことは、今までの活動を観ていてもわかる。彼の舞台を観ていていつもながらに感心するのは、面白い脚本を見つける才能と、その配役の妙だ。七人の登場人物に多少のでこぼこはあるものの、安心して観られる役者をきちんと押さえているところはたいしたものだ。
本多劇場の舞台に、静岡の昭和の家の立派なセットを組んだのは見事だ。どっしりした地方の家に漂う昭和の空気感、とでもいうものが漂っている。今の時代に誰もが懐かしむ昭和の一家庭の姿がそこに見える。しかし、それは単なるホームドラマではなく、懊悩や暖かい無視、想いやりに囲まれた家族の姿なのである。加藤健一の元教師の役は、一見フラフラしているようでも、その奥底に心のわだかまりを抱え、日々の暮らしの中に時折見せる懊悩が面白い。小泉今日子の教師、彼女の芝居を観ていて「凛烈」という言葉が思い浮かんだ。きっぱりとした科白の調子、すっとまっすぐに伸びた背筋。このところ小劇場での舞台を何本か観たが、だんだん舞台の調子をつかんで来たような印象がある。ベテランの滝田裕介が、何とも言えないゆったりした芝居で、自分のペースで芝居をしながらも、芝居の中でキチンと自分の役割を果たしている。こういうベテランの味は捨てがたいものだ。何でもない芝居で幕を切るのだが、そこに別段力が入っているわけでもなく、ごく自然体で芝居を見せる。こういうことは、十年二十年の修行でできる芝居ではない。今回の舞台で殊勲賞を出すとすれば、警官の役を演じた石坂史朗だろう。扉座出身の役者で、今までにも加藤健一の芝居には何度か出演しているが、静岡ののんびりした、それでいて人間関係の濃い町と時代を表現する良いアクセントになっている。狂言回し的な役どころを、見事に演じた。何よりも、科白に昭和の時代感覚が生きているのが嬉しい。
さて、この芝居のタイトル「高き彼物」という耳慣れない言葉だが、この言葉は短歌の一節である。芝居の中で、結局「高き彼物」が何であるか、という結論は提示されない。その言葉を受け取る登場人物がそれなりに考え、それでもわからないままに終わる。乱暴な言い方をすれば、舞台の一人一人の考え方が「高き彼物」であるとも言えるし、観客に「高き彼物」とは何か、それを持って帰って考えてもらいたい、というものでもある。とは言え、芝居を観た後で家に帰り、その言葉の意味を調べる必要はない、と私は思う。「高き彼物」という言葉が、「語感」として観客の耳に残り、頭の片隅に残れば、そこであえて結論を出す必要はないのだ、と思う。「高き彼物」という言葉に想いを馳せ、時折想い出せばそれで良いのだ。現に、作者も出演者もこの言葉に対する感覚は違っているはずだ。芝居にはいろいろなパターンがあり、みんなが同じ結論を出す必要はない。とは言え、私が批評家として一つの結論を出すのであれば、この言葉は、最終的には「これだ」という正解を見つけることがかなわぬ「人間の生き方」であるのではなかろうか。人間がその生を全うする数十年の間に、自分が疑問に思っていることのすべてに対して明確な結果が出ることなどはあり得ない。自分なりの「高き彼物」とは何か、ということを考えながら日々を暮らしてゆく、その生きようそれ自身が「高き彼物」と言えるのではないか。
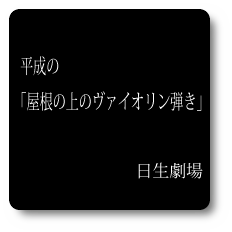
市村正親のテヴィエが今回でもう三回目になるという。森繁久彌が初演し、上條恒彦、西田敏行と受け継がれてきたこの役が、市村正親のテヴィエで「平成の屋根の上のヴァイオリン弾き」になった。今の観客には信じられないだろうが、この芝居、1967年の初演の折には後のブームを予想するべくもないほどの不入りだったのだ。私は初演を観ていないが、想像するに、こうした民族や信仰を根に据えたテーマのミュージカルが、まだ日本の観客に受け入れられる土壌ができていない時代だったのであろう。今でこそ、「レ・ミゼラブル」のようなミュージカルも何の違和感もなく受け入れられる時代だが、ここへ来るまでに40年以上の時間がかかり、また、最初にこうした作品を日本に持って来た菊田一夫、という劇作家であり東宝の重役の名プロデューサーの慧眼があったことが、今のミュージカル全盛の水脈になっているのだ。
我々日本人には、「民族の迫害」という感覚が理解しにくい。宗教に根差した生活も同様である。しかし、ユダヤ人は、そうした歴史の中で長い歴史を生きて来た。ロシアの寒村・アナテフカに住む貧乏だが人の良い牛乳屋・テヴィエ。五人の娘を抱えて、日々の暮らしに追われる中、それでも小さな日々の幸せに包まれ、家族の愛情に包まれて生きている。それが、やがてアナテフカを追われるまでを描いたミュージカルである。「人生に乾杯」「金持ちなら」「サンライズ・サンセット」などのミュージカル・ナンバーが優れているのは言うまでもないが、愛情に溢れた作品が、多くの観客の支持を集めている理由の一つだろう。
市村テヴィエは、一言で言えば「フレンドリー」なテヴィエだ。森繁久彌や上條恒彦のそれが、日本の家父長制度の中で生きる父親の姿を炙り出したものだったが、市村正親はそれよりも近寄りやすい雰囲気を持っている。それが、時として軽く見える嫌いがあるが、それは、この芝居が日本で生きるための宿命でもあるのだ。というのは、この重いテーマの芝居を日本人の観客に身近なものにするために、今までに演じた役者たちが、観客の理解のためにあえて役を軽く演じようとして来た歴史がある。その流れの中で、市村正親が役を創った上の結果だろう。それが正しいことであるかどうか、は非常に解釈が難しいところだ。ただ、森繁が演じていた頃よりもずいぶんアドリブめいた科白がなくなり、芝居のテンポアップがなされていたのは評価できる。
テヴィエの妻・ゴールデを演じるのは鳳蘭。この女優が今までこの役を演じていなかったのが不思議なほどである。今までのゴールデの中で、私が一番すぐれていると感じたのは淀かおるだったが、同じ宝塚の後輩が演じる鳳蘭のゴールデは、淀のそれを彷彿とさせる立派な「おかみさん」だ。明るくってしっかりしていて、しかもテヴィエに全幅の信頼を寄せている。特に感心したのは、大詰め、アナテフカを追い立てられ、アメリカへ渡る準備をしている一家。立ち去る家をいつまでも掃除し続けているゴールデを催促するテヴィエに、「汚くしたままで出て行きたくないもの!」という科白をぶつける。この一言に、ゴールデという女性がこの寒村で生きて来た半生が込められているような想いを感じ、胸が締め付けられた。さすが、である。時として太陽のように明るく、娘を叱る時は叱るが、立派な「おっかさん」である。何よりも、貧乏を恥じることなく、テヴィエと共に堂々と生きている姿が良い。昔はこういう人が町に普通にいたものだ。
この二人の夫婦は見事なコンビだが、他の役にはいささかの不満がある。貴城けいのツアィテル、笹本怜奈のホールデ、平田愛咲のチャヴァ。この三人の娘の個性が際立たないので、一緒に見えてしまう。本来は性格が描き分けられているのだから、そこをきちんと演じなくては意味がないだろう。また、舞台全体に感じられたのが、「民族」「信仰」といった、ユダヤ人の生きる「誇り」とも言うべきものが希薄だった点だ。科白の中では繰り返し登場するテーマなのだが、形で見せられないものだけにどう表現するかが難しい。しかし、その感覚が「何となく」でも良いから観客に感じられるかどうかで、この芝居が持っている厚みが全然違って来るのだ。そこが今後の問題だろう。
この芝居を貫く大きなテーマの一つの「伝統」−芝居の中では「しきたり」と呼んでいる−がある。古き伝統の中で、それをよすがに生きて来た人々が、新しく入って来た思想の中で古き伝統を打ち破って新しい世界へ旅立つ芝居でもある。その感覚で言えば、今回の平成版の「屋根の上のヴァイオリン弾き」も今までの先輩たちが創ってきた「伝統」から抜け出し、新しい二十一世紀の思想や感覚を盛り込んだものなのだろう。これは悪いことではない。一つの芝居を長い間演じるには、そうした「洗い直し」は必要な作業だ。しかし、それはよほど慎重にやらなければ、単に「軽い」で片づけられてしまう恐れがある。一つ感じたのは、以前の上演の折に比べて随分科白が変わっているのに、訳者が「倉橋健」としか記されていないことだ。新たに翻訳に手を加えたのであればその人の名を記さないと、両方に対して失礼に当たるだろう。細かいことだが、ここをキチンとしておかないと、「平成版」の新しい「屋根の上のヴァイオリン弾き」の土台が固まらない。今後の上演のために、あえて書いておく。
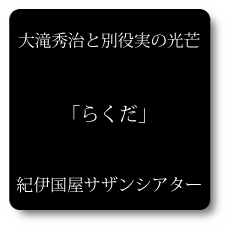
舞台には落語の高座がしつらえてある。「正札附」の出囃子が聞こえてくる。昭和の名人・三遊亭圓生の出囃子だ。生で聴くのは三十年以上前の高座以来だ、と思いながら観ていると、大滝秀治が羽織袴で登場した。顔立ちは亡くなった春風亭柳昇を思わせる。何となく、こうした噺家がいたような気になる。こうして別役実作、大滝秀治主演の「らくだ」の幕が開いた。
ご存じない方のために少し注釈をすると、「らくだ」とは落語の演目である。傍若無人で嫌われ者の「らくだ」という仇名の男がふぐに当たって死ぬ。そこへ通り合わせた人のいい屑屋を巻き込んで、「らくだ」の兄貴分と称する男と長屋で騒動を繰り広げる、という噺だ。ここまで書いていて思ったのだが、落語の粗筋を書くほどばかばかしい話はない。
この噺を下敷きにして、別役実の世界観が広がる。題材は落語の古典名作であっても、それが別役の手にかかると、まったく違った、まさに「世界観」が広がるものだ。つまり、いつもの別役作品のように、登場人物に固有名詞はなく、「男1」とか「女2」としてあるだけだ。落語の世界の話だ、普通であれば「熊さん」だの「馬の奴」、「長屋の大家さん」となるところを、あえて自分の世界観の中で展開する別役の筆は冴えている。面白かったのは、「らくだ」という男がふぐに当たって死んだという事実を、「政治的な事件」にしてしまうことだ。単にふぐに当たって死んだのではなく、そこには別の人物の思惑が介在していた。これは、完全に落語から離れている。その離れ方が、ある意味で新鮮であり、この感覚こそが、別役実という劇作家の真骨頂なのだ、と思う。「ええじゃないか」も登場することから、幕末とおぼしき時代を想定して書いているのだろうが、時代も場所も特定はしない。別役作品においては、そうしたことはたいした意味を持たないからだ。そして、別役作品には象徴的なシンボルである「街灯」が出てくる。それが時にはベンチであったり、椅子であったりするのだ。これは、単に「らくだ」という古典落語を劇化したものではなく、その設定を借りた別役実の世界なのだ。普通に劇化したのでは、こうはならないだろう。
この作品に臨む大滝秀治、84歳である。民藝の大先輩、瀧澤修や宇野重吉の薫陶を受け、それを体現しながらここまで重ねてきた芝居というものが活きている。芸の伝統は歌舞伎などの古典芸能だけではなく、新劇でも充分に活きている。先人の精神を受け継ぎ、それを自分の中でどう換骨奪胎し、新しい自分の芝居を生み出してゆくか。そこが役者の苦しみどころであり、はまった時の楽しみでもあろう。このところ、小幡欣治作品などで快調なヒットを飛ばし続けている大滝秀治の畢生の当たり役と言っても良い気がする。酒を飲み、酔いを発して「らくだ」の兄貴分に絡んでゆく辺りは、落語と芝居の間を行ったり来たりしているような心地よさがあり、客席の笑いを誘う。人のよさそうな温顔の中に時折見せる硬骨漢ぶりが、別役実の作品とマッチしているのだろう。老境にある作家と役者の、見事な光芒と言えよう。
今回の舞台で二人の役者が眼に残った。まずは、大家のおかみの塩屋洋子。放り投げるような科白の言い方に性根の悪い女のさまが良く見える。良い意味で、昔の新派のわき役の芝居を観るような気がした。もう一人、「らくだ」の兄貴分の和田啓作。姿もそうだが、科白の切れがいい。アクセントや間の問題など、細かいことを言い出せばまだまだ修行の余地ありだが、こういう芝居を演じられる世代が今の民藝にいることが嬉しい。ここが、劇団の強みなのである。
今、劇界にも大きな不況の波が押し寄せている。それだけではない、膨張しすぎたこの世界が、今後どういう形になるのか、不安な要素はたくさんある。誰もがその中で試行錯誤を繰り返している。膨張の果てにくるものは収縮だ。その折に、残る芝居は何か。言うまでもなく「良質の芝居」だ。その時に、バブルに眼もくれずにコツコツ芝居を重ねて来た劇団の強み、というものがわかるのだろう。観客の笑い声がそれを語っていた。

2002年にイギリスで初演され、その後アメリカでトニー賞の栄冠に輝いたイギリスの劇作家、トム・ストッパードの「ユートピア ユートピアの岸へ」三部作が一挙に上演されている。各部が約3時間、休憩時間を含めると、一日で三部を全部観劇しようとすると約10時間30分に及ぶという超大作である。一部の「船出」、二部の「難破」、三部の「漂着」がそれぞれ二幕の構成で、上演時間の長さやキャストの顔ぶれの豪華さが話題になってはいるが、芝居の本質を考えると実に緻密に構築されており、上演時間の長さが苦にならない。
舞台はロシアで幕を開ける。1833年、前近代的な農奴の制度が色濃い世相の中、「革命」に闘志を燃やす若者たちが1861年の農奴解放を経て、1868年までの約35年に及ぶ物語だ。世の中の動きに対して青雲の志を持った若者たちも、それぞれが家庭を持ったり幾多の恋愛を経験したりして、だんだんと「大人」になってゆく。その中で、志を一にしていた仲間の考えも現実の前で微妙な食い違いを見せ始める。世俗の栄光を手にする者もいれば、政治行動に没入する男もいる。作者はそうした人々を細かな場面の連続を重ね、時間を行きつ戻りつし、事実と虚構を混ぜながら構築して見せる。登場人物の中には、我々でも知っているツルゲーネフなどの実在の人物が登場し、主人公のゲルツェンもまた実在の人物である。一人の役者が複数の役を演じているケースもあるので、登場人物は延べにすれば70人を超えるだろう。こうした大人数の処理は、演出家・蜷川幸雄のもっとも得意とするところである。登場人物の衣装を「白」を基調にまとめ、素早い舞台転換で芝居のテンポを作っているところは評価するが、特筆すべき目新しさはない。むしろ、目新しさをあえて求める必要もないだろう。「大がかりな蜷川演出の芝居」という一つのブランドでもあるのだから。
芝居は、阿部寛が演じる思想家・ゲルツェンを中心に展開し、別所哲也の作家・ツルゲーネフ、勝村政信の革命家・バクーニン、石丸幹二の詩人・オガーリョフ、池内博之の文芸批評家・ベリンスキーなどが主な登場人物となる。麻実れい、水野美紀、京野ことみ、佐藤江梨子、とよた真帆、毬谷友子などの女性キャストも多いが、男性が中心の芝居である。この芝居の本質を一言で言えば、「議論」と「対話」の芝居、ということになろうか。そういう意味では、純然たる科白劇で、役と役との対話によって感情の流れや摩擦が起き、ストーリーが展開していく、典型的な「新劇」だ。そうした議論のやり取りが、すとんと観客の心の中に落ちてゆくのが、この芝居が飽きない原因だろう。今どき、「革命」などというものについて、延々と議論をしている芝居を観れば、一歩間違えれば一時間も持たないだろう。しかし、その時代を生きた人々の思想のみならず「気持ち」や「人間くささ」がリアルに伝わって来るから、この長編が飽きないのである。トム・ストッパードが膨大なエネルギーを費やしてこの芝居を書き、世に問う意味、それを考えたい。
主演の阿部寛、最近の仕事ぶりは目覚ましいと思っていたが、この仕事は見事だ。最初に登場した瞬間に、「若き思想家」に見えた。一番の要はここで、どんなに長大な科白を完璧に暗記しようが、その言葉が、「思想家」としての役・ゲルツェンの口から出たものでなくては、観客は納得も共鳴も反発もできまい。歌舞伎などでも「出」の瞬間が大切だと言われるのはそこだ。彼が演じている役に見えてしまえば、後は彼がどう言おうが、その言葉を観客は受け入れる。この最大の難関を突破したことは、きちんと評価してよい。時間を重ねるごとにうまく年を重ねているが、それは厳しい言い方をすれば役の上の工夫であって、最初の「役になる」という大前提が崩れてしまえばこれも徒労に終わる。それが徒労に終わらずに功を奏したのは、最初の科白の若々しさで、外見の問題ではなく彼の役柄を造型して観客に見せたことだろう。以前、「熱海殺人事件」初演の折に「変わったな」と思ったが、この芝居でまた再度彼は「変わった」。今回の稽古では相当に苦労をしただろうが、それは報われるはずだ。ただ、第三部にもう少し悠揚迫らざる感覚が出てくればほしい。物質的なものに恵まれ、常に自分の回りにサロンを築いている中年男性の優雅さが欲しい。それでこそ、若き思想家に突き上げを食う中年の矛盾が漂うというものだ。
瑳川哲朗が第一部で見せたバクーニン家の家長が良かった。いかにも旧弊なロシアの貴族の俗臭をぷんぷん漂わせた芝居、さすがにベテランの味である。こういうことが一朝一夕にはできないところが芝居の面白さである。その夫人である麻実れい。いささか典型にすぎ、むしろ第三部で演じた家庭教師の方がこの女優の魅力が出ている。毬谷友子が第三部で見せた崩れた女の姿が印象的だった。
別所哲也、石丸幹二ら、ゲルツェンを取り巻く人々について言えば、想いのほかの健闘ぶりを見せたのが池内博之の批評家・ベリンスキーだった。貧困の中で、一途に理想に燃える青年のいらいらした行き場のない焦燥感がよく見える。別所哲也のツルゲーネフは、後半になって良くなってきたが、前半の仕事ぶりは特筆すべきことはない。一部では狂言回しのような役どころの勝村政信の革命家・バクーニン、第三部での芝居がいささかあざとく、それまでの努力が帳消しになった感がある。石丸幹二の詩人・オガリョーフも、幕を追うごとに良くなった。銀粉蝶が出番は少ないものの、他の役者に代え難い味を持っていた。
今の日本人が、茶番劇を繰り返している国会の体たらくを観てもわかるように、まともに議論を闘わせる機会がめっきり少なくなった。その背後にあるのはIT社会による人間関係の希薄さなのか、時代に漂う虚無感なのか。今は、自分の意見を堂々と開陳すれば変な眼で見られる時代でもある。しかし、若い時代にそうした議論を交わし、熱く語った人々もやがては中年になる。現実を知り、社会を知り、分別を弁え妙に落ち着き、理想を語ることも少ない。若い頃に夜を徹して議論したことなど想い出の彼方になり、日々の生活に追われている。そうした現状を、若者に「だらしない」と批判をされる。これはおそらく、古代から繰り返されてきたことなのだろう。かつて自分が批判をしてきた人々の年代に差し掛かり、「今の自分はどうなのだ」と、若者に問われ、自分にも問い掛ける。
ゲルツェンが夢見た「ユートピア」は、どこにもなかったのかも知れない。しかし、ユートピアを探す行為だけは、やめてはいけないのではないか。それが、この芝居の一つの本質であるような気がする。折しも、日本という国が政治的にも社会的にも大きな舵を切るタイミングにこの芝居がぶつかったことは、あながち偶然ではないのかも知れない。10時間20分の間に、そんなことも頭の中を居来する一方、この骨太な芝居に関わった多くの人々に賞賛を贈りたい。
※参考までに、今回の舞台のタイムテーブルを記す。
第一部「船出」12:00〜13:15、13:30〜15:00
第二部「難破」13:35〜16:55、17:10〜18:30
第三部「漂着」19:15〜20:30、20:48〜22:20

来年四月で取り壊しが決まっている歌舞伎座としては、最後の七月公演である(これからの公演はすべてそうだが)。七月の歌舞伎座と言えば、猿之助奮闘公演として夏芝居の目玉だったが、玉三郎を中心に猿之助の一門を加えての夏芝居もすっかり定着した感がある。病に倒れた猿之助の一門をまとめて引き受け、次々に大役に抜擢し、自らが一ヶ月の責任興行を行う玉三郎の姿勢には頭が下がる。夜の部は「夏祭浪花鑑」と「天守物語」。玉三郎を座頭に、海老蔵、勘太郎らの若い役者、そして上置きに片岡我當。
上方の芝居である「夏祭」、上演の時期としては最高で、人気の海老蔵がこの伊達男・団七九郎兵衛をどう演じるか、そこがまずは興味の焦点だ。出の瞬間から「目」の効く役者である。特に、大詰めの殺し場、緋の下帯で市蔵の義平次を相手の立ち回りには色気がある。今までに、いろいろな団七九郎兵衛を観たが、イキが良くて身体の線が美しい。これは、初代の尾上辰之助以来だ。他の団七は、すでに中年の体型で身体にセクシーさがなかったが、腹筋が割れているのではないか、というぐらいの海老蔵だからこそ、色気が出る。これでこそ、男伊達の侠客なのだ。ただ、肝心の科白がどうにもならない。「こりゃこれ男の生き面を…」というせっかくの聞かせところがオペラのような声になってみたり、上方訛りがおかしかったりする。また、大詰めの立ち回りで、見得を決めるたびに「ふんっ」とか「はっ」という音が漏れ、これが気になる。もはや、今の時代に純粋に上方訛りを聴かせる芝居を求めるのが無茶なのだろうが、容姿が美しいだけにその差がもったいない。まずは科白、だ。若ければ良いというものでもなく、年輪を重ねることによる芸の味わいもある。芸の難しさはここだ。
団七の良き相手役の一寸徳兵衛が獅童。困ったことに、こちらがどう努力しても歌舞伎の科白に聞こえないのだ。二本目の「天守物語」の朱の盤坊の方がよほど良い。ということは、「古典歌舞伎」の科白ができていない、ということだ。現代にあって、古典歌舞伎の科白を一点一画守ることは不可能であり、意味をなさない部分もある。変容するのは芸能の本質だから崩すのは役者の力量次第だ、と思う。しかし、行書は楷書を学んでからのことであって、楷書がきちんと書けないうちに行書を書くのは無茶苦茶な話で、狂言は違うが「そりゃ聞こえませぬ徳兵衛さん」とでも言いたくなる。
徳兵衛女房お辰が勘太郎。観ている途中で気がついたのだが、彼の祖父である先代の勘三郎、現勘三郎と、中村屋三代のお辰を観たことになる。気持ちの良い役だが、勘太郎は無闇やたらと科白の調子を張り過ぎて、まだ外見だけのお辰だ。あんなに調子を張ってしまうと、相手の科白の調子が崩れる。この役は、女の意気地と性根を見せる役だ、まずはそこを押さえずに、科白だけには頼るべきではないだろう。役の性根がつかめて、その上で上方の年増の匂いたつような濃厚な色気が出るかどうか、という難しい役なのだ。
「夏祭浪花鑑」は現在上演されている場面構成は良くできた楽しい芝居である。まずは三人とも、芝居を楽しく見せるための勉強をしよう。芝居は観客が楽しむもので、役者が楽しむものではない。
「天守物語」。泉鏡花の作品は玉三郎専売特許の感がある。富姫の美貌を保っている玉三郎には驚嘆するばかり。相手役の姫川図書之助は海老蔵。夜の部二本の大活躍で、こちらの方が「夏祭」よりはまだ観られる。これも、獅童と同じ理由だろう。亀姫は勘太郎。近江之丞桃六に我當が付き合って、朗々とした科白を聴かせる。
歌舞伎座で上演するとは言え近代の作品であり演出家が必要で、戌井市郎、坂東玉三郎演出とある。二人とも鏡花の世界には理解が深いはずだが、なぜ背景にCG映像を使うのか、理解できない。空の色が夕焼けや青い空に変わったり、亀姫を乗せた籠が宙を飛ぶ映像を見せたりする。現在の映像技術をもってすれば難しい話ではなく、歌舞伎と映像のコラボレーションを否定するつもりはない。しかし、それも時と場合によりけりだろう。鏡花の綾錦を織るような絢爛豪華な科白に酔いながら、観客がイメージを掻き立てる楽しみがあるのに、そこで「これが答えです」と言わんばかりに映像を見せてしまっては芝居の楽しみがなくなる。鏡花の科白が活きなくなる、ということだ。もう一つ、その時間、観客の集中力は映像へ分散されるために、映像が変化する間、観客の興味が芝居から離れてしまう。こんな子供だましのような補助手段を使わずとも、科白だけで充分に成立している芝居なのだ、邪魔以外の何物でもない。
「天守物語」の幕が降りた後、カーテンコールがあった。最近はそう珍しいことではないのだろうが、歌舞伎座への観客の想いを感じた。もう残り少ない現歌舞伎座での芝居だからこそ、我々の眼にいつまでも残るような芝居を見せてほしいものだ。

「まあ、あんなに汗をいっぱいかいて…」という一言で客席に笑いが弾けた。これは、役者の科白ではない。観客の言葉だ。「うちでテレビを観ているんじゃないんだから、思ったことを言わないように!」と即座に役者が切り返し、また笑いを誘った。
池袋にある小さな劇場「シアターグリーン」でのひとコマだ。劇団鳥獣戯画が「跳び跳びロングラン」と称して続けている公演、「三人でシェイクスピア」も七年を超え、200回に達したという。わずか90分でシェイクスピアの37本の戯曲のダイジェストを見せるという無謀な芝居だが、初演の頃に新宿のプークで観て非常に面白かった記憶がある。それ以降も観たいという想いは持ったままにチャンスを逸してきたが、久しぶりで三度目の観劇となった。
やはり面白い。まずは、脚本が良く出来ていること。次に、三人の固定メンバーがベテラン揃いであり、完全に芝居が手に入っていること、それでいて力を抜いていないこと、この三つだ。どれも至極簡単な理由であり、ことごとしく分析をするまでもない。しかし、この三つの要素が揃った芝居が少ないのが現状だ。
客席数100に満たない小劇場で、決して儲かる芝居ではない。申し訳ないが、装置や衣装にお金をかけているとも思えない。一歩間違えば、素人が自己満足で終わる芝居に変身する可能性もある。そうならずに、七年もの間細々とではあるが上演が続いているのは、三人の役者が紛れもなく「プロ」だからである。わずか二日間の公演のために、他の仕事のスケジュールを縫い、稽古を重ねるだけの愛情をこの芝居に持っているのだ。劇団の創立メンバーであるちねんまさふみ、石丸有里子、そして赤星昇一郎。1975年に創立した劇団だから、もう35年近く活動を続けている。学校公演や子供むけの芝居などをコツコツと積み重ね、そこで得たものが次の舞台に反映されての積み上げである。赤星などは、「怪優」とも言える風貌だが、そこでとどまらないのは、芝居の骨法を身につけた上での抑制を知っているからだろう。
芝居の数が多いことはあちこちでさんざん書いている。しかし、どんな規模のどんな芝居であれ、「お客様が喜んで劇場を後にする」ということが究極の目的であることは変わらない。最初の観客の言葉は、芝居を楽しんでいるあまり、咄嗟に出た言葉だ。言わば、観客の生の反応が即座に舞台へ反映されたものである。これは小劇場の芝居の良さであり、ともすると、これをきっかけに悪い意味での「客いじり」を始めることもあるが、嬉しいことにこの芝居ではそこまで下司な真似はしない。一瞬芝居の本筋からはずれることはあっても、即座に芝居に戻る。何でもないことのようだが、実はこれは技術のいることだ、と私は想う。今の若い役者やテレビタレントを観ていると、「客いじり」をして、その反応に助けられているような無様な体を見せている人がいる。その上、それで自分が受けていると、ご丁寧に勘違いまでする輩がいるが、ここの芝居にはそれがなかった。
この芝居だけではなく、こうした地道な活動になかなか眼を向ける機会が少ない。これは我々の責任でもある。しかし、たまにこういう密度の濃い芝居に出会えた時の嬉しさはまた格別なものがあるのだ。
三人が汗みずくになって90分をぶっ飛ばす「三人でシェイクスピア」、地道な仕事で良いから、質を落とさずに続けてほしいものだ。

「新劇の神様」とまで呼ばれた劇団民藝の瀧澤修が当たり役にしていた三好十郎作の「炎の人」。ゴッホの生涯を描いたドラマだが、この芝居によって日本人の中にある種のゴッホ像が出来ていると言っても良いほどに、緻密に構築された芝居だ。それだけに、演じる方には相当の力量が必要で、そのせいもあって最近眼にする機会がなかった。瀧澤修の芝居に憧れていた市村正親がこの役に挑戦すると聴き、「とうとうか」という想いで劇場へ足を運んだが、結論を言えば予想以上の収穫であった、と言える。
今の若い演劇ファンには知る由もないが、瀧澤修が演じたゴッホは、「毎日踏み出す足の位置が変わらない」という伝説が生まれたほどに緻密に計算された演技だった。ゴッホを演じるに当たって、フランスへ渡り、ゴッホが歩いた道をたどりながら役作りをした、というのは事実だ。1989年、83歳の折に演じたものが最期になったが、狂気の人・ゴッホの奔流のような情熱のエネルギーに圧倒されたのは今でも鮮やかな記憶である。こうして、半ば伝説化した舞台に挑むのは、並大抵のことではない。最近はもっぱらミュージカルに活躍の軸足を置いている市村正親だが、ストレート・プレイでも多くの佳品を残している。その本領を発揮すべく、60歳を迎えた今、大役に挑んだのだろう。時宜を得た、と言える。
ただひたすら描くことのみに執着し、その中で生まれた狂気のために、37歳の若さで自らの命を絶ったゴッホ。世界的な画家であることは言うまでもないが、その生涯を日本の劇作家が描いていることは注目に値する。外国人を主人公にした芝居を日本の作家が書いた例は他にもあるが、ここまで固着したイメージを創り上げたのは、三好十郎の大きな仕事である。脚本がしっかりと隙間なく書かれているために、作品が役者を選ぶ、という性質も持ち合わせたのだろう。それだけに、市村正親がこの役に執着し、舞台の上でゴッホをねじ伏せようとした気持ちが良くわかる。膨大な量の科白はまさにゴッホとの格闘に等しい。その格闘を通じて、言葉を変え場所を変え、「絵」に対する情熱を訴える市村ゴッホの迫力は見事なものだ。もっとも、たった一つ気になるのは、この人が生来持っている舞台での愛嬌がふとした瞬間に出て、それが緊張の糸をほぐしてしまうことだ。意図的なものかも知れないが、言葉が追い付かないほどに絵のことを語りたいゴッホに愛嬌はいらないだろう。
ゴッホが影響を受け、尊敬した画家・ゴーギャンを演じる益岡徹が良い。堂々たる態度に適度な嫌らしさがいい具合に混じっている。傲岸なゴーギャンである。こうでなければ、仕事も家族も捨てて南の島へ走ったゴーギャンにはなるまい。ゴッホと絵との格闘に時折参加するセコンド、あるいはレフェリーのような感覚が面白い。荻野目慶子の弾けた芝居がいいアクセントになっており、助演陣の好演もいい効果を挙げている。中嶋しゅう、原康義のようなベテランが顔を見せることで、芝居の厚みがぐっと変わる。芝居のキャスティングの妙である。さとうこうじのロートレックに期待していたが、いささか直球勝負しすぎた感があるのが残念だ。
15分の休憩を挟んで3時間10分に及ぶ芝居は、観客にとっても格闘である。誤解を恐れずに言えば、観ていて疲れる芝居だ。しかし、幕が降りた後、ゴッホの人生と自分の人生を比べてみたり、生きるテーマについて考えることのできる芝居だ。たまには芝居を観て我が人生に想いをいたすのも悪いことではあるまい。一枚の絵を生む画家の人間ドラマ、などという美辞麗句だけではすませることのできない、生臭い泥濘のような人生がそこにある。嫉妬深く、猜疑心にあふれ、小心でだらしなく、女好きで…。だからこそ、ゴッホという一人の「人間」の懊悩と魅力がくっきりと浮かび上がって見えるのだろう。自分自身が発する炎で自らを焼き尽くしてしまった男。もしかすると、それは市村正親という役者に共通する部分があるのかも知れない。
最近、日本の過去の名作を新たな演出で上演する試みが増えている。今回の舞台は栗山民也の演出で、大いなる名作が甦った。名作に出会える観客は幸せである。芝居が一期一会であることを、こういう舞台で感じるのだ。

幕が降りる瞬間の拍手が、お義理で叩いているかどうかはすぐに分かるものだ。「ああ、楽しい芝居を観たな」という満足感溢れる拍手は、こちらも叩き甲斐がある。そういう芝居がとんと少ない昨今、加藤健一事務所が上演しているレイ・クーニーの「パパ、I LOVE YOU!」。ロンドンの病院の医師談話室を舞台に起きるコメディで、15分の幕間を含めて2時間15分、観客が実に良く笑っている。こういう時代だからこそ、良質のコメディが必要なのだ、ということはあちこちで繰り返し書いて来たが、この作品をこそ、そう呼ぶに値する。初演の好評から15年を経ての再演、今回は加藤健一が演出も担当し、満を持して、という感がある舞台だ。
主役となる二人の医師に加藤健一と村田雄浩。このコンビの間合いが絶妙で、コメディの命が「間」なのだ、ということを改めて感じさせる。村田雄浩という役者が、改めて舞台の人なのだ、と感じる生き生きとした躍動感を見せてくれたのは嬉しい。加藤健一が起こすトラブルに、同僚から家族までが巻き込まれていく、というドタバタ喜劇で、野暮ったらしく粗筋を書くまでもない。ある側面から見れば、何ともご都合主義で強引な設定の、傍若無人な芝居である。それを、そう思わせずに観客を笑わせ、楽しませてしまうのは、レイ・クーニーという劇作家の腕の凄いところだ。残念ながら、日本では、オリジナルの喜劇の土壌がここまで達していないことを認めざるを得ない。小田島恒志の翻訳がこなれていて、駄洒落を巧みに散りばめているので、違和感がない。かつて、海外の芝居を上演する際に、翻訳というものがもっときちんと意識されていた時代があったはずだが、ここをきちんと観るのは我々の仕事であもる。
加藤・村田の二人の芝居の足の速さが素晴らしいので、回りの役者とのスピード感や芝居に距離ができてしまう。特に、加藤健一の息子で、役の上でも親子になる加藤義宗や、かんのひとみ、この二人は若いゆえもあっていささか力み過ぎの感がある。一柳みるや山野史人などのベテランは自分のペース配分で二人の芝居に伍しているから不安はないものの、どうしても役者の技量によって凹凸ができる。逆に言えばそれほどに、コメディは難しいのである。
最近、「人を笑わせること」と「人に笑われること」の境界が曖昧になり、お笑い芸人などもプロとアマの境界がほとんどない。そんな中で、緻密に練り上げられたコメディを観ると、そこに笑いの本質がちゃんと描かれているのがわかる。どんなに傍若無人な設定であろうが、芝居全編を通して流れている作者の「友情」や「家族愛」というテーマはぶれない。そこが、良質になるかならないか、の大きな分かれ目でもあるのだ。ただギャグを連発して笑わせてしまえば良いというものではない。そういうものは、後に何も残らないからだ。
私が加藤健一事務所の一連の仕事を評価している理由は、「作品を選ぶセンス」と「丁寧な上演」である。この二つは簡単なようでいて非常に難しい。特に、作品を選ぶセンスは、自分では良いと思っても観客との体温差が激しければ成功はしない。このセレクトの眼が良いのである。芝居の半分は作品の選定にある、と言ったら誤解を招くだろうか。しかし、根っこに据えるものが良くなければ、いくら巧い役者を揃えてもエネルギーの浪費になる。加藤健一事務所は、所属俳優は本人ただ一人であり、上演のたびに作品に合わせてキャスティングをしている。いわゆる新劇と言われる分野において、このスタンスを続けてきたことは評価に値する。もう一つの「丁寧な上演」。初演で大好評だったこの芝居が再演されるまでに15年の歳月がかかっている。いろいろなタイミングの問題もあっただろうが、初演よりも良いクオリティの芝居を見せなくては意味がないことを知っているからこそ、練り上げるのにそれだけの時間をかけたのだろう。初演よりも再演の方が難しいのはどの芝居も共通だ。最近は、「この芝居は前にもやっているので楽だ」などととんでもないことをのたまう役者がいる。

清水邦夫の一幕劇「楽屋」。1977年初演の作品である。いわゆる「新劇」の分野では古典的な名作の部類に入れても良いだろう。有名無名を問わず、ずいぶん多くの役者がこの作品を演じて来た。今回は、生瀬勝久の演出である。
考えてみると、劇場の楽屋は、芝居の関係者以外には異空間であろう。「怖いもの見たさ」や「憧れ」で覗いてみたい人もいるだろうし、華やかな舞台の裏側は見たくない、という人もいる。芝居に関わる人びとにとっては日常